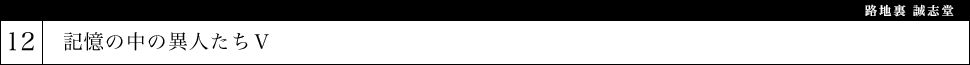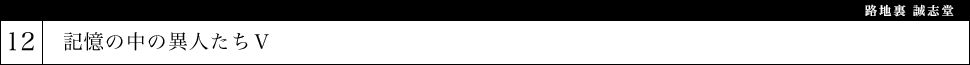写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
彼女は異人であったでしょうか。否、異人であろうはずがありません。ですが、村にやって来る「巡礼伶人」たちに思いを馳せると、その対偶的存在としての彼女の記憶が必ずや、私の脳裏を過ぎるのでした。彼女のことを語ろうと思います。
〔いや、もう〕
私は何ごとに付け堅いとされる家で、その家の女主人がおガンジンのお訪いに対し居留守を使っていたところに出喰わしたことがあります。何気なく裏庭から覗くと、更年期に中る年恰好の家刀自が玄関横の壁の内側に、両手を貼り付けて息を潜めていました。彼女は私を見咎めると、顔全体を尖がらせて、突き出した口唇に指を一本立てたのです。かくれんぼ? とんでもない、彼女はおガンジンをやり過そうとしているのでした。そして、やり過しました。
私はそこに、何か不思議な動物を見たような気がしたものです。
彼女ほどの人が、なぜそのような真似をするのでしょうか。というのも、彼女は村の指折りのインテリゲンチャで、俳句のひとつも捻れば書もこなします。こざっぱりと着物を着こなし、村主催の文化的な催しではいつも貴賓席に座っているようなお人なのです。今の今、その光景を思い浮かべてみるに、そのような振る舞いは彼女の吝嗇のなせる業というより、私はそこになんらかの精神的な変調を感知します。その奇矯さは吝嗇の故としても、余りに常軌を逸しているように思えるからです。そうではないでしょうか。
まだ、村には「憑く」という言葉が生きていたと思いますが、その表現を用いれば村の文化人たる彼女にこそ、実はその名の下に何かが憑依していたのです。いや、私は何もその一事をもって、彼女をそのように特定しようというのではありません、日頃の彼女の立居振舞いと思い合わせて、そんな感想を持ったまでのことでした。村人に先生と言わしめ、子供心に、学校の先生でもないのに彼女がなぜ「先生」なのか不思議でした。別に強制して言わせていたわけではないと仰言りたいのなら、そのような呼称を恬として恥じずと言い換えてもよいでしょう、それがお得意であったことは間違いのないところなのですから。そう言わないと機嫌が悪いのよ、口さがない村のご婦人たちの証言を、当時、私は得ています。
更に言葉を継げば、子供でもないのにお河童頭で、お河童はその頃の女の子用のヘアースタイルだったのですから、大人のくせにやっぱり変です。子供の私は童女を衒った彼女の、常に間歇的に揺れるこの頭部が何より気味が悪いと思っていました。
彼女の挙動はいつだってせわしなく、今ならわかります、女史風とでもいうのでしょう、催し事の準備の際には、その痩せぎすの体躯で齷齪と一切を取り仕切り、もたもたしていると見境なく、大の男たちをも怒鳴りつけました。そして、何より奇異に思われたことは、当の男たちが唯々諾々と彼女の言いなりになっていることでした。だからといって、私の見るところ、男たちに彼女への尊敬があったとはとても思われません。だって、そこには半ば呆れた時に村の男たちが何かと多用する、あの「いや、もう」があったのですから。その独特のエロキューションを持つ感嘆詞は、言わば西洋人がちょくちょく見せる、肩をすくめては小首を傾げる、あの「肩すくめポーズ」の気分に近かったでしょう(「肩すくめポーズ」を仔細に描写すれば「両肩をあげ、手のひらを見せ、眉をつりあげ、頭をかしげ、口を『へ』の字に曲げる」となります)。
後日、私は何やらの翻訳書で、そのような仕種を「肩をすくめた軽蔑」とする、我が意を得たりの訳語を見つけたものですが、それはもはやここにまで至ればお手上げの態を意味し、要は小馬鹿にしているのです、どっちもどっちですねーー尚、この手のジェスチャーの良き参考図書としてはピーター・コレット著「ヨーロッパ人の奇妙なしぐさ」(高橋健次訳、草思社)を、ここに忘れずに挙げておきます。
さて、「憑く」とは所有すべきものに所有されることです。憑かれたら最後、その人の本性とも思しきものが励起され、存在そのものがけたたましく成り果てます。ですから、これらの「憑きもの」は今にあっては、もはや動物の名を借りないまでも、至る所で見ることができます。流行思想やイズムと名の付くものはそのようなものだと看做すこともできますし、イデオロギーは論理の憑依だし、カルト的宗教では教祖が信者に憑きます。ブームやトレンドと呼ばれる風俗現象などもその一種ではあったでしょう。無論、あらゆるアディクション(依存症)、および性的偏奇などは言うまでもありません。いずれも人に憑き、人を所有し、その大方は厄介なものと化すはずです。
挙句、人は現在的な病理といえる「私が私に憑く」自我肥大狂になり果てるというわけです。そこで、期せずして、私はその処方箋となるべき文言を、エリック・ホッファーの「波止場日記―労働と思索」(みすず書房)の中に見出したりもしますーー「自分自身の幸福とか、将来にとって不可欠なものとかがまったく念頭にないことに気づくと、うれしくなる。いつも感じているのだが、自己にとらわれるのは不健全である」(田中淳訳)。尚、私が愛惜措く能わなかった文化人類学者・岩田慶治は「自分からの自由」を、夙に一冊の新書の形で世に問うています(興ある方は是非のご一読を)。
ここで余談のひとつも挟めば、私が心底この沖中士の哲学者・ホッファー氏に惚れ込んでしまったのは、その日記の中に次なる一文を発見したからでした。曰く「私は一人で死んでいくつもりだし、寂しさを感じたところでもう手遅れである」。私はその一行を見るや、思わず吹き出し、多大な共感を覚えたものでした。「…もう手遅れである」のもの言いが(例え翻訳であったしても)可笑しく、何ともよろしいではないですか。
とまれ、いつの時代も、いかなる場合も、何やらの憑きものなしでは人間は人間をやっていけないものなのでしょうか。この国の巷にあって、街に犇く人々の顔つきを見遣る時、その挙動も含めて、私はそこにあらゆる動物相を見出し、愕然としたことがあります。何かに憑かれている! 勿論、私も以上の事情から免れているわけではありません。私などはさしずめ「言葉憑き」、どんなに詰まらないしゃっ面を曝して世間をほっつき歩いていることか、貉、鼬の類いが相場というものです(ショーペンハウエルならそんな私にかく言うでしょう、「そんな面でよくも外出することが出来るなあ」、たしかに!)。
さてこそ、ここは何やらに向かって、私の吐息のひとつもあるところです、まったく以って「いや、もう」と。
☆☆☆
「正午(丸ビル風景)」
あゝ十二時のサイレンだ、サイレンだサイレンだ
ぞろぞろぞろぞろ出てくるわ、出てくるわ出てくるわ
月給取りの午(ひる)休み、ぶらりぶらりと手を振って
あとからあとから出てくるわ、出てくるわ出てくるわ
大きなビルの真ッ黒い、小ッちゃな小ッちゃな出入口
空はひろびろ薄曇り、薄曇り、埃(ほこり)も少々立つている
ひよんな眼付で見上げても、眼を落としても……
なんのおのれが桜かな、桜かな
あゝ十二時のサイレンだ、サイレンだサイレンだ
ぞろぞろぞろぞろ、出てくるわ、出てくるわ出てくるわ
大きなビルの真ッ黒い、小ッちゃな小ッちゃな出入口
空吹く風にサイレンは、響き響きて消えてゆくかな
――中原中也「在りし日の歌」より。
「五月の人ごみ」
どんぐりまなこ
かなつぼまなこ
ししっぱな
だんごっぱな
にきびづら
らんぐいば
にじゅうあご
ぶしょうひげ
でっちり
はとむね
だいこんあし
しゃーべっととーん
ケロイド
――谷川俊太郎「落首九十九」より。
「……とにかく、人が大勢いるなかでも、まあ合格といえるのは、どんなに少ないことだろう――例外として、美しい・善良な・聡明な顔は、――ほんの時たま、ごく稀に、あるにはあるけれども、――感覚の繊細な人々にとって、たいていの新しい顔は、おおむね、或るー驚きに近いー感じを起させるであろう、というのは、たいていの顔が、いまさらながら吃驚させられるようなものの組み合わせで出来上がっていて、要するに、不愉快きわまる印象を与えるものなのだから・とわたしには信じられるのだ。(中略)しかも、それらの顔のうえには、心構えの卑俗さ低劣さが、むきだしに現れているばかりでなく、よくも、あんな面していながら外出することが出来るなあ、なんだって、わざわざ仮面(マスク)をかぶらずにいるのかしらと、怪訝の思いにたえられないほどー人間ばなれのしたー悟性の狭さ浅はかささえ、はっきりと刻みつけられている。じつに、たった一と目みたばかりでも、こちらまで汚されてしまいそうな感じのする顔もあるのだ。(中略)けだし、長い一生を通じて、心の中に、ちっぽけな・低級の・けちくさい考えや、卑しい・利己的な・羨ましがりの・間違った・そのうえ性の悪い願望のほかには、ほとんど何ものをも思い浮べてもみなかったような人間の顔に、果して、どういう人相が期望されるであろうか・と。(中略)しかし、そのような顔でも、だんだんと、慣れるに従って、いいかえると、その印象に対して鈍感になってしまうと、それはもはや何らの作用をも及ぼさないようになるのだ」。……
――ショーペンハウエル「人相鑑定術によせて」(石井立訳、「女について」角川文庫)より。
※付記
「憑物(ツキモノ)」 いろいろの霊力あるモノが人間にとり憑く現象、またはその個々のモノをいう。自然に憑くものと、求めて憑かせるものの二種がある。狐(クグ・ニンコ・イヅナなど異称多し)・犬神・ゲドウ・トウビョウ・蛇・猫・狸・ゴンボグネなどと呼ばれるモノが特定の家もしくは家人に憑いていると信じられている。(中略)憑物筋の発生した理由はいろいろ考えられる。まず特殊な職業を持ち、その奉仕する神が他と異なっていた家が、その神による託宣を効果あらしめるために本体を特殊化してきたこと。さらに仏教の普及などによって、その託宣の威力が減少し、一般と疎遠となって次第に邪宗・魔法めいた印象を強くすると共に、かつての霊談だけが誇張されて今日の狐持・犬神・トウビョウ持などと称せられる家筋が極端に忌み嫌われることになったと考えられる。こうした実在もしくは信仰上の動物の霊が、人に憑くという精神現象の原因は、狐や蛇などの動物を神の使、または神が仮に姿を託しているものとして信じ、その託宣を定期的に求め、もしくは彼らが時あって、その啓示を自ら人間界に与えてくれるものと信じ敬した遠い時代からの隠れた心意伝承に基づいている…(以下略)」。
――柳田国男監修「民俗学辞典」(財団法人・民俗学研究所編、東京堂出版)より。
******次回は、8月10日の予定です******
HOME
|

おかっぱ頭の少女
(つげ義春「紅い花」より)
|