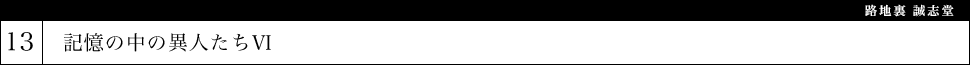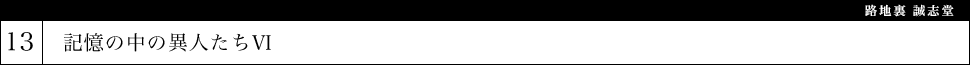写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
私は踊り子のことも語っておこうと思います。「伊豆の踊子」ならぬ、村にやって来た踊り子のことです。後にも先にも、私の記憶ではたった一度切りのことでしたが、私の村にも踊り子一家がやって来たことがあるのです。
〔旅芸人の記憶(踊り子)〕
秋の農事が一段落も着いた頃のことでした。そのメンバーは五人。未だどこかにその道の華やぎを留めた太肉(ふとりじし)の母親と、役者顔を渋く老けさせた痩せぎすの父親。花も恥らう年頃の娘さんが表看板で、そこに若衆盛りの、彼女の兄と私は思っているのですが、美貌の青年。彼らは夫婦だったかもしれません。というのも、私と同い年ほどの、まだ幼女と呼べそうな少女が一行には加わっていて、少女は初老の二人をお母さん、お父さんと呼び、若いふたりを兄(あに)さん、姉(あね)さんと呼んでいたところから、子供の私は単純にそう判断していたわけで、今ともなれば、少女こそはふたりの娘さんだったかもしれません。いや、やはり、年の離れた妹だったでしょうか。さて、その実際はどんなものだったでしょう……。
ともかく、一行の芸事は村一番の豪農の庭で披露されました。見料はありませんでしたが、では彼らの報酬はどうしたのでしょうか。多分に、そのかみは名主も務めたという、元は地主であったこの家の主を始めとする、村の主要な旦那衆の「はな(ご祝儀)」で賄なわれたのだと思われます。「元は地主」に関して若干の言葉を継げば、戦後の農地解放で一介の自作農になりましたが、村での社会的地位と尊敬までも失ったわけではありません。また富農であることには変りがありませんでした。
果して、旅芸人たちは春を鬻いだりしたのでしょうか。そんな憶測がないでもありませんでしたが、そのようなことはなかったと思います。せいぜいが催しの後、先の村の旦那衆との酒宴の席で、お酌はもちろんのこと、ひとつや二つの「拝舞」や、田舎芸者の真似事をさせられたぐらいでしょう。いずれにしろ、以上のようなことは取り立てて、私の関知するところにありません。
ですが、私は「童子考」の名著でなる郡司正勝の「おどりの美学」から、ご祝儀を意味する「はな」と、その返礼ともいうべき踊子たちの「拝舞」についての確かな註釈となるだろう一節を、一応ここに引用して措きますーー「芸人に祝儀をやるのを〈はな〉といって〈纏頭(てんとう)〉といいう字を当てるが、具体的にははなと纏頭はおなじものではない。纏頭とは、かしらにまとうという字のごとく、芸能者に、衣服を首に投げかけて与えられた風習の名残であって、殿上で舞人が皇帝より賜った衣装を左肩に懸けて、その恩寵に応じて舞うのを〈拝舞〉という。……(以下、略)」。
また、和歌森太郎の「花と日本人」(角川文庫)には「纏頭とは、摘んだ花を頭髪のかざしに挿す、あるいは頭に巻きつけたところから考えられた文字であろう。花笠のもとになる風儀ではあった。この『纏頭』という文字で思うのは、遊芸人や力士へのご祝儀としての『花』を『纏頭』と書いていたことである」が見えます。なお、「纏頭」は「遊戯之賄賂」だと、室町時代の辞書の「下学集」にあり、その説明として「傾城(けいせい)白拍子の類への、大名高家からの下されものをだとされている。多くは衣装など下されたのを、押しいただき、頭にかずき巻くようにして辞去したから、かずけものを纏頭と書くのだと解されている」と、氏に抜かりはありません。
(また、和歌森太郎の〜氏に抜かりはありません。2020/6/28 追加)
踊りは日の暮れない裡に、早い午後には始まりました。
村の有力者たちは座敷框に陣取り、村人たちは庭で彼らをぐるりと囲むようにしてその踊りを観覧しました。なんの前宣伝もありませんでしたが、今にいう口コミニュケーションで、かなりの村人たちが集まりました。私は観衆の、半円の輪の最前列に陣取り、彼らの一挙手一投足に目を丸くしたものです。
音曲は父の三味線と母の小太鼓だけで、踊り手は若いふたりが担当しました。ソロで舞い、カップルで踊り、時には滑稽な所作の演しものも交えて、見物衆を飽きさせません。ふたりでしっとりと遊牝(つる)んで舞う時には何やらそこにはお話があるらしく、ラブ・ストーリーに決っています(因みに「つるむ」とは交尾のことです)――子供の私には単に退屈なシロモノでしたが、今様に表現すればカッタルイとでもするところです、大人たちは恍惚(うっと)りしていましたけれど。
合間合間に、少女がその稚い舞い姿で村人のやんやの喝采を得ました。
私はそれらの踊りそのものにはさしたる記憶を持ちません。が、踊り手たちの化粧(けわい)された顔容(かんばせ)には深い印象を持ちました。見惚れました。三人三様、私にはこの世の人とは思えぬほどの妙なる者に思えたのです。
男は女のように艶冶(コケットリー)だったし、女はどう目を凝らしてもその目鼻立ちが朧に見えるのでした、臈たけたとでも言うのでしょうか。
自分とさして年の違(たが)わぬ少女はわざとのように鼻筋を白く立て、口唇にはおちょぼに紅を差したりしていて、彼女は私の目にはもはやお人形さんそのものなのでした。息をしているのさえ不思議な気がしました。三人の口唇には、その紅(くれない)の艶めかしいものには小さく刻んだ金箔が塗されていて、何かの加減でキラキラと輝きました。私は華美な衣裳にはさほど驚きませんでしたが、この口唇の金箔の煌きには気を惹かれ通しでした。
世の中にはこんな絢爛豪華な人たちがいるものなのか、私は夢見心地でそのひと時を過ごしたと思います。このような人たちに浚われてしまったらどうしよう、などと想像したりしました。まさか? いやいや、子供心にもそのような境遇は私の身の上には訪れないだろうと承知しつつも、その想像にはどこか甘美なところがあって、しかも、その気分はすこぶる濃厚で幼い私を途方に暮れさせました。
その夜、私はいつになく元気がなく家人を心配させました。というのも、そのような異な催しの後には、私ははしゃぎ回り、さっそく家人の前で見よう見まねの種々を再現してみせてはお茶目の限りを尽し、いずれは埒のない有り様となるのが常のことでしたから。それなのに、ああ、それなのに、この消沈ぶりはどうしたことでしょうか。尋常なことではあるまいとの判断があったのでしょう、私は母から痛くもない舌を出させられたり、痒くもない額に額を押し当てられたり、挙句には宵の裡から母屋でのいつもの寝所と違う中坐敷(お客さまが寝る所!)にムリヤリ寝かされました。
私はその頃、事情はともあれ、別棟として庭先に設えられた、祖母用の簡易な離れで祖母と歳の離れた姉と同居していました、といっても、夜、眠りに帰るだけの話でしたが。だから、ここは母の目の届く所でという配慮があったのでしょう。
祖母は事情の許す限り私の側に侍っていましたが、姉などがわざわざ離れから私を見舞いに来たのには驚きました。表座敷と中座敷を仕切る中戸をそおっと開けるや、真面目くさった顔を神妙に覗かせ、口の形だけでフ・ヌ・ケ、そのようなことを囁き、私のところにまで躄って来ては、少女期特有の冷たい手を私の額に乗せたりもしました。よほど、私はぐんなりしていたのかと思います。
果して、私は褥の中でどんな夢を追い求め、どんな夢見があったのでしょうか、今となっては解ろうはずもありません。
私の旅芸人の記憶は後にも先にもこれだけであり、これ以上でもこれ以下でもありません。しかし、私の記憶の中では花の乏しい晩秋の農閑期のこととはいえ、いや、それだからこそでしょうか、わが踊り子たちは真っ赤な夕焼けを背景に、富農の庭前に咲き誇った豪奢な花、そして少女はその大輪を予感させる可憐な蕾なのでした。
☆☆☆
はるかに後年、ハイネの「精霊物語」の中に、グリム兄弟の採録による以下のようなお伽話を見出した時(別に踊子の話ではありませんでしたが)、私はあの遠い日の記憶、晩い秋の庭の踊り子たちのことを思い浮かべはしなかったでしょうか。甘く苦しい、胸を焼くような「憧憬」(換言すればそれは未来への追憶)、忘れかけていたそのようなゲミュートが不意と、私を襲ったのでした。
そっくり書き写してみます。さほどには長尺でありませんので、興のある方はお楽しみください。では。
「ジンツハイムの近くのエブフェンバッハでは、大昔から毎晩三人のすばらしい美しい、白い衣をきた乙女(おとめ)が、村の紡(つむ)ぎ部屋にやってきた。彼女たちはいつも新しい歌やメロディーをうたってきかせ、かわいいおとぎばなしや遊びを知っていた。彼女たちの糸まき竿(さお)と紡錘(つむ)はなにか独特なもので、どんな紡ぎ娘も彼女たちほどきれいに早く糸を紡ぐことはできなかった。しかし十一時が鳴るとすっと立ち上がり、糸まき竿をまとめて、どんなにせがまれてもそれ以上は一瞬もそこにとどまらなかった。その乙女たちがどこからきて、どこへ去っていくのか、だれにもわからなかった。人びとは彼女たちをただ湖からくる乙女たちとか、湖からくる姉妹とよんでいた。若者たちはその乙女たちに会うことを喜び、恋い慕った。
なかでもっともはげしく恋したのは学校の校長の息子だった。その若者は乙女の声を聞き、乙女と話をするだけではとても満足できなかった。とりわけ残念でならないことは、乙女らが毎晩かならず早い時刻に帰っていってしまうことだった。そこで彼はあるとき一策を案じ、村の時計を一時間おくらせておいた。夜になったがおしゃべりと冗談に花がさいてだれも時間のおくれに気がつかない。そして時計が十一時をうったとき、じつはすでに十二時だったわけだが、三人の乙女は立ちあがり、糸まき竿をまとめて帰っていった。翌朝、数人の村びとがその湖のそばを通りかかった。するとすすり泣く声が聞こえ、水面に三か所、血のにじんだところが見えた。そのとき以来その姉妹は紡ぎ部屋に姿をあらわさなくなった。校長の息子は衰弱し、まもなく死んでしまった。」
――ハインリヒ・ハイネ著「流刑の神々・精霊物語」(小沢俊夫訳、岩波文庫)より。
※付記
〈おどり〉は、ふるくから〈躍〉とか〈踊〉などの漢字があてられていて、はじめはいわゆる芸術としての舞踊をのみ意味するものでなく、たんなる跳躍を主とする日常の動作を意味するものとして使われた。〈おどり上がる〉ということばはそれを示している。だからもとは、この語は舞踊のみをあらわすことばではなかったといってよい。〈踊〉という字には足篇が附いているように、シナでも足を主とした飛び上がる動作を指したものであった。だからもとは、この語は舞踊のみをあらわすことばではなかったといっていい。(中略)〈まい〉は〈まわる〉という旋回運動をあらわすことばであった。
―(中略)―
これを日本の場合にかぎっていえば、おどりは、はじめの踊手であった巫女のかみがかり的な跳躍に発してこれを繰返しているうちに、またはその準備運動として意識的に儀式化したものが〈まい〉であって、これを形式化してみると、〈おどり〉は乱舞形式であり、グロッセのいわゆる体操舞踊である。それは多分に無意識的であり、パッショネートであった。このことは文字とは結びにくいものにした。これに反して〈まい〉は儀式的であり、人工的であり、意識的であったから、物真似になりやすく、文学や物語と結びつきやすかった。……(以下、略)。
――「おどりの美学」郡司正勝著、演劇出版社刊より
(2019/8/10)
******次回は、8月20日の予定です******
HOME
|
|