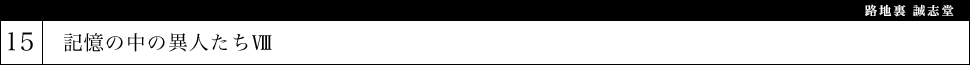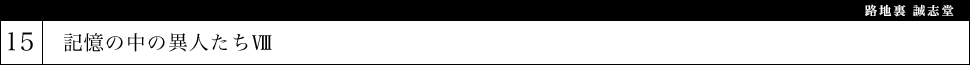写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
……
サーカス小屋は高い梁(はり)
そこに一つのブランコだ
見えるともないブランコだ
頭倒(さか)さに手を垂れて
汚れ木綿の屋蓋(やね)のもと
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん
それの近くの白い灯(ひ)が
安値(やす)いリボンと息を吐き
観客様はみな鰯(いわし)
咽喉(のんど)が鳴ります蛎殻(かきがら)と
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん
……
――中原中也〈サーカス〉、「山羊の歌」より。
〔サーカスの話〕
私はここで、小村に過ぎない私の村にも小屋掛けされた見世物のことや、近在の町場にやって来たサーカスのことなどを語ろうと思います(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
私が初めて実見した曲技団擬きについていえば、驚くべき異能の持ち主たちの前口上で「命懸け」なる言葉を知るのでしたが、彼らはイノチガケでなんと口から火を吹いたり、ガラスの電球をムシャムシャ食べたり、挙句の果てにはお腹の上に大きな臼を据え置き、見物衆の有志の者にお餅を搗かせたりもしたのでした。そのお餅は演者によって得々と見物衆に振る舞われたりしたのですが、今にして思えばイノチガケなどとはとてもだに呼べない、お粗末な代物ではありました(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
まあ、それはそれとして、さして遠からぬ後、私は祖母と歳の離れた姉とに連れられて、近在の町場で然るべきサーカスなるものを体験することにもなるのです(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
大きな円形の天幕の中には底抜けに間抜けな道化師や(彼がオナラをするとお尻からは小麦粉と思われるものが噴射されるのでした)、いかにも意地悪そうな猛獣使いがいて、芸をする象やライオンもちゃんといたのです。はたまた、スパンコールのレオタードに身を包んだ、眩しい人たちによる眩いばかりの空中ブランコや綱渡りがあります。この二つのコンテンツこそ、当時も今も変わらぬサーカスの華でありました(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
勿論、訓練を施され綺麗に着飾ったお馬さんだってなん頭かいて、入れ替わり立ち代わり、リングのステージ、彼らの言葉で言えば「丸盆」の縁を走り回りますし、馬上ではカウボーイ・ハットを被ったキラキラしたお姉さんたちが、立ったり跳ねたり逆立ちしたり、それはそれは見事に駿馬を乗りこなすのでした。サーカスが曲馬団と言われる通り、西洋に於いてはメーンの演しものです。ですが、日本の近代サーカスにはなかったと、宇根元由紀さんはその「サーカス放浪記」(岩波新書)に書いています(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
そういわれると、確かにそのように私にも思われました。ですから、私の曲馬の思い出は後年のテレビで見たボリショイ・サーカスなどが混在したものに違いがありません。ですが、それはそれで、私は良しとします。記憶の捏造、そのようなことは別に怪しむに足りない、むしろ尋常なことと思われるからです(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
そんな中でも、私が何よりも感動し驚愕してしまったのは、ひとりの勇敢なオートバイ乗りの青年のことです(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
彼のオートバイには飾り気などが一切ありません。防音マフラーを始めとして、走る以外の要素は全て排除され、まるでオートバイの骸骨、いわば剥き出しの走る原理そのもの、一個の鉄のオブジェですね、その赤裸々な佇まいが、子供の目にはどうにも素敵なのでした(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
彼は日本の姓とアメリカ人のようなファースト・ネームを持ち、フルネームでアナウンスされる時には、必ず、英雄的に「選手」を付けて紹介されたものです。このような紹介の仕方はボクシングの選手紹介時のアナウンスでお馴染みなものですね。彼こそは確かに、命知らずのオートバイ乗り、選ばれしもの、子供の私にしてみれば、まさしく選手なのでした(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
彼の出立ちなどもここで語っておくべきでしょうか。そんなことは不要かとも思われますが、あえて一言あれと言われれば、それは往年の戦闘機乗りを思わせるものでありました。さすがに白いマフラーまではしていませんでしたが、小豆色の丈のつまった革ジャンと頭には同じく革製のヘッドギア、そして風防用のゴーグルがとても印象的でした(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
さてこそ、青年ライダーは満場の拍手に応えるやいなや、颯爽とオートバイに跨り、頭上にあったゴーグルを顔に下すと、右手でアクセルを目一杯に噴かし、耳を劈くばかりの轟音とともに網状の鉄球(アイアン・ホール)の中を疾駆します――始まりは水平に、おもむろに放物線状に(しかる後、何と垂直にさえ!)、オートバイは排気音もけたたましく、バリバリバリバリ、バリバリバリバリ、もはやデスぺレート(絶望的にやけくそな)と形容したいような轟音と猛スピードで、アイアン・ホール内を縦横無尽に走り回るのでした。時に両手をハンドルから離し、手放し運転! これぞ命知らず。その上、彼は真ッ逆さまになっても落っこちないのでした(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
なぜ、落っこちないのか――しかし、しかしですよ、歳の離れた姉に言わせると、そんなことは少しも驚くにあたらないのだそうです。彼女の説明によれば、オートバイ乗りが逆さになっても墜落しないのはエンシンリョク(後々に知る「コリオリの力」)のなせる業で、何もあの青年が「命知らず」ってわけではないのだそうです。更には、スピードを出していればこそ落っこちないのであって、バッカみたい、そんなことも知らないでコーフンしているのは、ただの愚者!
――グシャ?
――アンタのこと。
まあ、よい。そんな理屈がなんになる、おんな風情に何がわかる! (ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
後日、やや頭の中身が足りないとされる、その当時の私が何かと慕っていた同じ集落のオンツァが、そのエンシンリョクなるものを、私のために実演してくれたことがあります。秋の夕泥む庭先で、水の入ったバケツを、これでもかこれでもかと回してくれたのです。バケツの水は零れない、確かに、これが遠心力というものなのです(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
今、手元の辞書に中ってもみれば「遠心力」なる項には「回転運動をしている座標系に対して運動する物体に作用する力の一。回転軸からの距離と座標系からの距離と座標系の角速度の二乗との積に比例する」と端的に定義されています。オンツァはそのことを身を以って教えてくれたのです、ありがとう(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
とにもかくにも、近在の町場にやって来たサーカスはもう、どれもこれもが目眩めくシーンの連続なのでした。サーカスってそういうことなのよね(ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
それを思えば、だから、私の村にやって来た曲技団もどきの一行は、大道芸に毛の生えた程度の身窄らしい見世物にすぎませんでした――でもね、そうであったとしてもですよ、それらだって、記憶の中の私にしてみれば、町場で見たサーカス同様に随分と命ガケ、開いた口が塞がらないほどに感嘆久しくしたものではあったのです。 (ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん)。
上海雑技団
※付記
サーカスは起源は古いが、形態は新しい。近代サーカスは十八世紀の末にあらわれたといわれている。一般にフィリップ・アストレイがその祖とされる。彼は一八四二年にイギリスのニューキャッスル・アンダノ・ライムに生まれた。兵役に服している間に、馬術をおぼえ、ロンドンのランベスで曲馬を見せるようになった。サーカス・リングを考案したのはアストレイであったといわれる。彼は馬が同じ円周をぐるぐる走っている時の方が、馬上に立ちやすいことを発見した。馬とその上に立つ人の中心を結ぶ線は、円の中心の方にやや倒れ、遠心力によって、立っている人が馬の背にすいつくので立ちやすいのだ。
(中略)
さらにアストレイは曲馬だけでなく、アクロバット、綱わたり、手品、道化、畸形の見せ物といった要素をとりこみ、一七七〇年ごろには客席に屋根をかけ、一七七八年には、サーカス全体に屋根をかけ、アンフィシアター・ライディング・ハウス(円形乗馬劇場)としてオープンした。ほぼ近代サーカスの形態がそろったのであった。
海野弘「都市とサーカス(近代サーカスの誕生)」――「サーカスの世界〈全特集〉」別冊新評より。
文化の研究者である民俗学者は、その探究にふさわしい対象として、社会成員の間に品物や象徴を伝達するあらゆる組織をとりあげて研究しています。今日広く認められているように、ひとつの文化を特徴づける交換や相互関係の多くは、コードとして、あるいは隠喩的に言えば言語活動として分析できます。この見立てに立てば、サーカスとは一個の言語活動なのであります。サーカスの団長がひとつのショウを構成したり、芸人がある芸を創案しこれを実演して見せる時、観客は一連の視聴覚的な出来事に直面することになりますが、実際にはこれはメッセージに他ならないのです。観客はこれらのメッセージを「消費」し――ということは、リングで演じられていることを理解し――楽しさや賞賛の気持ちを表す記号を示すのです。このコミュニケーション過程は、演技者と観客の双方に共有されるコードが存在していることによって初めて成立します。そればかりか、明らかにこのコードは特定の集団、国民、階級などに限定されるものではなく、違った言語を用いて違った生活を経験している人々にも、分けへだてなく共有されています。
――ポール・ブーイサック著、中沢新一訳「サーカス――アクロバットと動物芸の記号論」せりか書房刊より。
******次回は、9月10日の予定です******
HOME
|

サーカスの世界
|