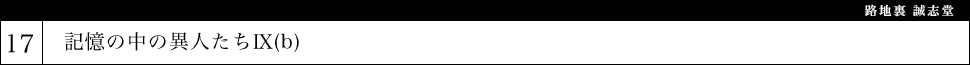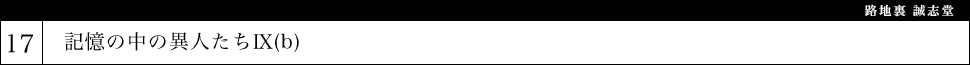写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
「風の老婆」の擱筆後、なぜか、私には不如意な気持ちが残尿感のように残りました。「口裂け女」の一バリエーションと思われる「風の老婆」の真相が、果たしてそんなこと(=大陰、鰐口)でよろしいのだろうか、と。
「歯の生えた膣(ヴァギナ・デンタータ)」
私の見るところ、口裂け女の噂は、子供たちの間に周期的にたち現れる現象に思われます。そのことは周知の事実と申してもよいでしょう。つまり、子供たちは口裂け女が好きなのです。このことは何を意味しているのでしょうか。はたまた、そこにはどのような民俗的心性が関与しているというのでしょうか。巷に噂が巻き起こる度に、私は私の「風の老婆」について、首を捻ったことでした。
寡聞にして、私たちは口裂け男の話は聞きません。そんなところからも「風の老婆」の事情はむしろ、巷間で囁かれる男性側のヴァギナ幻想の方に求めるべきではないか、と考えたのでした。ただ、幻想のレベルが好色家の間で取り沙汰される名器願望、あるいはその裏返し程度のもので果たしてよかったものかどうか、私の不如意感はそこにありました。
以上のことから、私はその後、婿殿の側の精神的疾患や、あるいは男性一般に見られる性的病理など、私の「口裂け女」の事の真相はそのようなところまで遡って考えるべきではないか、そんな風に思うようになったのです。
そこで、東南アジアに見られる抜歯習俗や文化人類学で採集されるヴァギナ幻想、所謂「歯の生えた膣(ヴァギナ・デンタータ)」などに思いを馳せるようになりました――世界には「歯の生えた膣(ヴァギナ・デンタータ)」のヴィジョンを持つ説話が分布しています。その文化人類学的分析に拠れば、これは男性の去勢コンプレックスの表出と言われています。ジグムント・フロイトならそこにお得意のエディプス・コンプレックスを見るのでしょうが、果して、私たちの口裂け女は何を私たちに示しているのでしょうか。去勢コンプレックスとは周知の如く、挿入した男根を直ちに切断してしまう女陰への根源的恐怖のことを指すのですが、それが精神病理学的に進展すれば女性恐怖(所謂「女嫌い」)、ひいては性愛の嫌悪にまで高まることは必至です。
そこで、私は気付くのです、件の「風の老婆」の婿殿がかくいう精神障害の持ち主ではなかったかと。してみれば、私は翻って反省もするのですが、風の老婆は「鰐口(大陰)」でさえなかったのでは、と。
しかし、たとえ、それがそうだとしても婿殿の性愛への嫌悪や拒否、そのことに纏わるそのものずばりの侮蔑はあり得るわけですから、あったはず、彼女の悲劇に関する私の先の記述は、とりあえずは有効かと思われたりもするのでした。と同時に、一方、私なりの「口裂け女・考」を書いてみたいとさえ思うのです。
さてこそ、以上のような心算(つもり)とエクキューズを条件に、私はこの「風の老婆」は先の叙述のまま保存しようと思いました。ここに諸兄諸姉の了を乞います――「身体全体を男根に同一視し、口と膣とを無意識に同一視することは、いわば古典的な性格を持っている」(R・カイヨワ著「神話と人間」久保博訳、せりか書房刊)。
※付記
ノートより――(東南アジアの抜歯習俗)。
我が国の、と云うよりは世界的にもヴァギナ・デンタータ説話研究の嚆矢とされる、博学博捜の著者の手になる「Vagina Dentata」(金関丈夫著、「木馬と石牛」所収)に中ってみる。と、金関博士はその論考の中で台湾諸族のかかる諸説話を、古今東西に亘るその学識を以って比較検証した上で、この陰歯説話の拠って立つ処を、東南アジアの婦人の習俗である欠歯風習と絡めて考察していた。かつて、東南アジアの諸民族の間では、結婚適齢期に達した女性はその前歯を抜歯、あるいは歯根に達するほどまでに磨耗さす。なぜそのような風習が可能なのか。単なる厭勝的習俗でもあるまい。博士は有力な解釈のひとつとして「Oral coitus」説を挙げておられた。即ち、口淫の便宜(!)を図っての故ではなかろうかというのである。以上は私が言うのではない、学問がそう語るのだ、念の為。要は「口歯(dentes oris)」も「陰歯(dentes vaginae)」も「夫の危害せられるのを恐れてこれを除去する」わけだ……(以下、略)。
ノートより――(「戦慄」と「魅力」の弁証法)。
去勢コンプレックスとは周知の如く、挿入した男根を直ちに切断してしまう女陰への根源的恐怖のことを指すのだが、それが精神病理学的に進展すれば女性恐怖、所謂「女嫌い」、とどのつまりは性愛の嫌悪から拒否にまで至る。しかし、そんな情動も心理学的には両義的、アンビバレントな感情として捉えられるから、短絡は禁物。嫌悪は願望の裏返しとも云えるのだし、恐怖と魅力は表裏一体なのだ。怖いもの見たさなどがその端的な例ではあろう。「戦慄すべきもの」は「魅了するもの」であり、その逆も亦、真なり、と云うわけだ。戦慄は魅力を強化すると云う簡明な指摘がジョルジュ・バタイユにあったと思うが、とするなら、この私たちの女性生殖器、「インテル・ウリナス・エト・フアエクス――尿(いばり)と糞便(くそ)との間」(フロイト)の背後にだって、聖なるものが控えてはいそうだ。ルドルフ・オットーの「聖なるもの」を巡る論考には聖なるものの与件として「魅惑的ではあるが戦慄的」、つまり、そこにはヌミノースな性質(ヌミノーゼ)があるとあった筈、以下、気なるところを2、3引用してみる。
ノートより――(オットーの「聖なるもの」から)。
・オットー著「聖なるもの」(久保英二訳)は第2章「ヌミノーゼ」より――わたしはさしあたって、ヌミノーゼ[ドdas Numinose]という言葉を作り([「前兆」を意味するラテン語の] omenから[「不吉な」を意味するドイツ語の]ominosという形容詞を作りうるなら、[「神霊」を意味するラテン語の]numenから[「神霊的」ないし「ヌーメン的」を意味するドイツ語の]numinousという形容詞を作っても差し支えないだろう)、その上で特殊固有のヌーメン的解釈と評価の範疇について論じ、さらにこの範疇が適用される場合に、つまりある対象がヌーメン的対象であると見受けられる場合にかならず生じてくる、あるヌーメン的な心的状況について論ずることにする。……
・「聖なるもの」は、第4章「戦慄すべき神秘」より――「戦慄すべき」という要因は、「神秘」という名詞のたんなる修飾語ではなく、「神秘」という要因に付けくわえられた一つの特性を表わす用語である。確かに、両要因のどちらか一方に対応する感情反応は、いともたやすくもう一方に対応する感情反応へと流れこむことはある。実際、われわれの言語感覚からすると「神秘」という要因とはきわめて緊密に結びついているため、一方の名を挙げると、かならずもう一方の要因の響きもともに聞こえてくるほどである。「神秘」はなんら問題なくそのままで「戦慄すべき神秘」なのだ。……
・「聖なるもの」は第17章「アプリオリな範疇の歴史における現れ」よりーー強い嫌悪感と身の毛もよだつ感じの間には非常に顕著な類似がある。そのことから、相互に類似する諸感情がたがいに引き付け合うという法則により、どのようにして「自然的な」不浄がヌミノーゼの領域に入りこみ、そこで成長していったかということがあきらかとなる。(中略)すなわち、ヌーメン的な不浄感は、逆にすぐにまた容易に自然的嫌悪感を呼び起こすという事実、つまり、もともとぜんぜん嫌悪されておらず、ただヌーメン的恐怖しかもたらしていなかったものが、嫌悪すべきものとなるという事実である。実際に、そのように呼び起こされた嫌悪感は、ヌーメン的不浄感が呼び起こしたもともとのヌーメン的おそれがとうに消え去ったあとでも、ずっとそのままに独立して残りつづけることができる。……
・ノートより――(オットーの「聖なるもの」を巡って)。
さて、そこで正直に書くが、私はかつて愛した人へのクンニリングスを頑なに回避したくせに、稀に見ず知らずの、しかも、蔑まされた境遇の若きご婦人への性器接吻を無性に欲望することがあった。ここにも同様のヌミノース的心理が関与してはいまいか。それとも、それは私個有の病理にすぎないものか。
告白ついでだ、もうひとつの追加を図れば、私は余りにあけすけに美しい男や美しいとされる女性をみると、そこに剥き出しの生殖器をまざまざと窺い見るような気分になることがあって、挙句、身も世もなくゲンナリしてしまう。
果たして、そんな心情が諸兄諸姉にお解り頂けるものだろうか。有り体にいえば、私にはある種の美男美女は面映く、なぜか直視が憚れるような心持ちに襲われると申しているのだが、では、これはどんな私の心的病理とするのか。それとも単なる妄想、そこに醸成される「姦淫への予感」に、唯にたじろぐだけのことなのか。ああ、そうであるなら、むしろ、私にあってはどんなにか気が楽であっただろうか。
ジグモント・フロイトには「蔑視された性愛対象にしかその官能が発露されない」とする男性心理の卓れた分析があるが(「男性にみられる愛人選択の特殊な一タイプについて」)、それはオットーの「元型を伴った神的な情動」であるとするヌミノーゼなる概念同様に、私にとっては大変に「魅力的かつ戦慄的な」話柄ではある。我が国の荷風散人などにその典型を見るが、ここではこれ以上は触れないつもりだ。煩瑣を嫌ったのではなく、余りの聞き齧りにすぎないから。
いずれの時にか、満を持してその課題に対し踏み込む時もあろう、その日までの我が身の宿題として措く……(以下、略)。
ノートより――「西鶴作品の近代性」(対談 吉行淳之介×松田修)、「文学界」昭和五六年五月号。吉行淳之介訳「好色五人女」(中公文庫)に再録されたものから。
松田 ええ。そこに個性的なものが投影してるし、西鶴の激しい好みがあって、世間での通用ということは離れてしまっているのではないかと思うのですが。
たとえば「椀久一世の物語」でも、椀久が最後に心をとめたのは、髪の毛を切って売れ、と言ったら、いやだと断った乞食(こじき)の女とか、当時としては貶(さげす)まれ、およそ性愛の対象にならないものに興味を持ち、関心を持つ。それが西鶴だけの構造なのか、西鶴以外の作家にもそういうのがあるのか。(後略)。
吉行 性愛というのは、時代によって、ずいぶん違ってくるものなのですね。たとえば平安朝ではよろこぶべきものとされていたし。
松田 そして、性愛だけに限ったことではなくて、生活全体に出てくることじやないかと、私は思うのです。(以下、略)。
「性愛というのは」、吉行が言うように「時代によって、ずいぶん違ってくるものなの」であるなら、男性にとっての女性美の在りようも時代の産物です。美人画の変遷を見ればそのようなことは一目瞭然なことですが、エクリチュール(文章表現)の上ではどうなのか、一例を挙げてその一端を覗いてみよう。
まずは西鶴は「好色一代女」(丹羽文雄訳、河出書房・日本古典文庫16「西鶴名作集」)より。
かの老人、桐の軸物箱から美人画をとり出し、だいたいこれに似た女を召しかかえたいものという。その絵を見ると、まず年は十五より十八まで、当世顔の少し丸く、色は薄桜色、顔立道具は、四つとも不足なくそろっていて、目の細いのはおきらいとある。眉(まゆ)は厚く、鼻の間は窮屈でなく、鼻筋高く、口もと小さく、歯並みは白くかがやくようで、耳は長めで、肉は薄く、つけ根よりはなれ気味で、その根元まで透かし見えるようで、額はつくったものでなく、自然のはえぎわ、首筋はすっきりと、おくれ毛なしのうしろ髪、手の指はたよやかに、長めに、爪薄く、足は八文三分、親指は反りかえり、その裏が透(とお)れるように美しく、胴は普通の人より長めで、腰がしまり、肉つきはたくましくなく、尻(しり)つきゆったりと、身ごなし着こなしじょうずに、姿に品があり、気立ておとなしく、女のなすべき芸事という芸事に明るく、からだはほくろひとつないのを、お望みとある。……
次は西鶴の三〇〇年後の極めて先鋭的なエクリチュールーー澁澤龍彦による「金子国義への美少女についての10の質問」(ユリイカ臨時増刊号「金子国義の世界」)から。
澁澤 質問1 あなたにとって美少女の魅力のポイントはどこでしょうか。肉体の部分をいくつか具体的に挙げてください。
(金子) 顔―小さいこと。斜めに向いたときに、頬骨が出ないこと。目はつぶったときに、瞼の上から眼球のかたちがはっきりと分かること。鼻は寸がつまっていること。口は小さすぎないこと。鼻と口のあいだが短く、人中(じんちゅう)がくっきり割れていること。
髪―金髪。ショート・カットなら、暴走族の若者がウェーヴのある髪を手で無造作にかき上げた感じ。そぎそぎに切った囚人のようなヘア・スタイル。ロングなら、できるだけ上の部分にひっつめて、背中の中ほどでゆっくり垂らしたポニー・テール。
首―細く、長いこと。横を向いたとき、頭部と肩に対してバランスがいいこと。
肩―いかって、骨帳って、痩せすぎるほど痩せていて、ポーズをとると骨が外れるのではないかと思われるほどなこと。
胸―薄いこと。少年のように。
手―細くて長いこと。ショウ・ウインドウのマヌカンのように。
腰―腰骨が出ていること。
お尻―まるくて小さいこと。
脚―腿が太くて、下に行くほど細くなること。脚が曲げたとき、膝小僧の骨がくっきり出ること。踝もはっきり出ること。……
******次回は、10月10日の予定です******
HOME
|
|