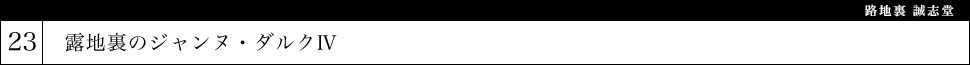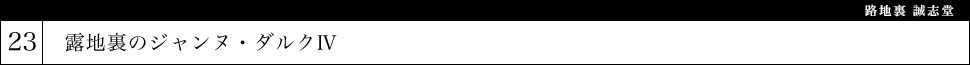写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
(Ⅳ)
黒いラ・ピュセル!
私たちの乙女よ。
黒姉え、私のラ・ピュセル!
私の乙女よ。
終に、私はあなたとのことを書こうかと思う――私たちには決して触れ得なかったあなたのことを、私とあなたの個人的な体験のことを。果して、あなたとの「マーメッチョ」はあったのだ。だから、先の女の子はあなたと私のことを予知していたのだともいえる。なんたることだ!としても、そのことを。
季節は判然としない。
木々の新緑の葉裏が目に痛いほどに煌めく頃だったか。それとも、春とも紛う麗らかな日和の秋の日のことであったか。彼女の身なりの印象からは前者のようでもあり、他の要素を思い合わせれば後者のようでもあるが、ここで私が語ろうとする事柄には、どちらがどちらであっても不都合はない。だから、私としてはこれ以上をここでは問わないつもり。どちらにしろ、記憶の中の美しい季節のことではあった。
午後も早い時間のことだった。身を持て余した私がなんの気なしに「彼女の木」の下に行ってみると、居るはずもない黒姉えがいつもの場所にいた。学校がお休みだったのだろうか。黒姉えは剥き出しの太腿もあらわに、二股に分かれた枝の上に片膝を立て、もう一方の足は枝下にぶらぶらさせていた。頭の後ろには、肘を張った恰好に組んだ両の手があり、黒姉えはそれを枕にその身を幹に委ねていた。彼女は深く微睡んでいるようだった。その余りの無防備さと危うさ。私は木の枝に微睡む不思議な生き物でも見る思いで見上げていたが、その不思議さは彼女のコスチュームの上にあったのかもしれない。だって、あの黒姉えがスカートを穿いている!
ここで、あの頃のスカートのことに一言触れて措けば、少女たちのスカートはいつもツンツルテンであったような気がする。それは私だけの思い過ごしであったろうか。物があり余っている時代のことではない。思うに、スカートの丈の方が少女たちの成長の速度に間に合わなかったのだ。この場の黒姉えもご多分に洩れまい。当時、簡単服と呼ばれたワンピースの、その寸詰りのスカートはお腹の方まで捲り上がり、申し訳ない程度の布切れが彼女の痩せたお尻の下で風にそよいでいた。お尻近くの黒姉えの腿の肌えは思いのほか白かった。枝下へ、健やかに真っ直ぐに垂れた彼女の足はもとより素足だったが、踵の方から足首へと包帯がきつく巻かれていて、その白いものには赤く滲むものがあった。私はそれを眩しく見た。
どれほどの時があったろう。気がつくと、彼女は彼女特有のあの皮肉そうに見える、例の口を歪めた笑みを作って、私を俯瞰(みおろ)していた。黒姉え、痛くしたんだ。それが私の第一声だったと思うが、彼女は答えず、黙ってお尻を乗せていた枝の上で反転した。スカートの下の、お尻を包んだまっ更なものが私の目の中で素早く回転すると、黒姉えは両手を巧みに操って枝に逆手にぶら下がり、トンと痛くはない方の足で地上に下り立った。黒姉えは足を痛くしたのだ。だからスカートなのか、そんなことを繰り返し繰り返し思っていると、来る? と黒姉えは言った。
簡単服姿の黒姉えは、男の子がムリヤリそんな恰好をさせられた時のようにぎこちなかった。無理もない! 片爪先立ちで歩くその後ろ姿は彼女の手足の長さだけがやけに強調されていて、簡易なワンピースのウエスト・ラインは肩甲骨の辺りまでずり上がり、全くもって「スカートを穿いた少年」のようだった。黒姉えのスカート。黒姉えがねえ、私はその後ろ姿をなんとも擽ったく思い、彼女の後に従った。
私たちは彼女の家の納屋にいた。たくさんの藁束が積み込まれた納屋の一角には白色レグホンや地鶏の類いが放し飼いにされていて(矮鶏や軍鶏もいた)、その土間のあちらこちらには卵が産み落とされている。稀に、とんでもない所に卵を見出すこともあるが、産み落とされたばかりの鶏卵は変に生温かくて、その上、産卵の際の擦れたような糞の痕や血糊さえも付いていたりもするから、私には手にすることも憚れた。おまけに、私は鶏が嫌いなのだった。どこか爬虫類を思わせる団栗眼の薄い瞼(あれは蜥蜴のものだ)や鱗状に罅の入った黄色い肢(これも亦、爬虫類からの進化の名残りだろう)などを見るにつけ怖気が走った。しかも、生きた鶏の鶏臭い、あの匂い。
そんな藁小屋の隅に私と黒姉えはいた。
黒姉えは手持ち無沙汰を持て余し、しばらくは土間と藁置き場の狭間の辺りを徘徊したが、目慣らしでもしていたのであろうか。私たちは光り輝く外界から薄暗い納屋へと闖入したわけだから、当初、私は常闇の世界に落ち込んだようにも覚えたほどだった。とこうする裡に、黒姉えはその辺に産みっ放しになっていた鶏卵のひとつを拾った。と、矢庭に剥き出しの膝小僧にぶつけ、口を歪めて、呑む? と私に差し出した。滅相もない。目を丸くしていやいやをすると、あっと言う間もあろうか、黒姉えは手にした卵を一気に啜った。呑んでしまうと、目をまん丸くしている私に彼女は単刀直入だった。そこにはいつもの表情はなく、私と正対し、見る? とだけ言った。
その意味は私には直ちに察知された。というのも、この日に近い然る日、庭の片隅で白いズロースをずり下げて蹲踞する彼女を、私は至近の距離からまともに偸み見したことがあったのだ。そのようなことは同年代の女の子だったらよく見かける類いの振る舞いであって、私にあっても少しも珍しい見ものではなかった。しかし、それは黒姉えだったからか、それとも年嵩の少女ということであったからか、判然とはしないが、私は最寄りの庭木に身を潜めて注視したことではあった。尾け狙ったわけではない。偶々、そういう場面に遭遇したばっかりのこととはいえ、私はある疚しさを以って覗いたことには違いがなかった。そこにはうっすらと淡い翳りが窺えたが、あれはなんだったのか。
彼女が立ち去った後、私はその現場にまで赴き、乾いて赤茶けたローム層の地上に描かれた少女の放尿の迸り、その瑞々しい痕跡をぼんやりと眺めさえした。このこと人にや語らまし! 由なきことを人に語りて聞こえなばと思えばこそ、つまり、詰まらない評判が立っても詰まらない。だから、私としては件の翳りについては私だけの秘密なのだと思っていた矢先、何やらの遊びの最中に、見たでしょ、と黒姉え直々から耳元で囁かれたことがあったのだ。
見る? 黒姉えの問いかけに、私は俯き、頭(かぶり)を振った。すると、私の前に膝まずいて、彼女は私の半ズボンに手をかけた。半ズボンにはベルトはなく、それはお兄さんたちのものだ、その腰周りはゴムのものであったから、黒姉えは両の拇指をズボンに差込み、お尻の方からゆるゆるとずり下げた。この人は何をする気なのだろう。私はこの意外な成り行きに気を呑まれたものか、まんじりともせず、彼女のなすがままになっていた。半ズボンの次はパンツだった。さすがに、その時ばかりは私も抵抗の素振りを見せたのだろう、シッ! 愚図る私を黒姉えは烈しく叱咤した。
私は下半身を曝したまま、蹲踞した彼女の前に立っていた。彼女の顔は私の前にあって、冷たい指が私を抓み、ゆっくりと剥いた。外気が当ってスースーとした。私は息を呑み、身を捩った。そして、なんということだ、私のペニスは幼いなりに硬直していたのであって、間もあろうか、生温かいものがそこを覆った。私は含まれたのだ。
私は黒姉えの口に含まれていた。黒姉えは今や、剥き出しのお尻の双丘を両の掌で抱え込み、私を支え、やがて黒姉えの生温かいものは熱を帯び、ヌラヌラと私の根元まで襲い、私の根元を甘く噛む。
…私はしゃくりあげていたらしい。気が付くと足元には私のものと思われるオモラシの痕さえあった。納屋の内ではそちらこちらで鶏たちが忙しげに餌を啄ばみ、所かまわず脱糞し、キョトンとあらぬ方を見遣っていたかと思えば、小首を傾げては左見右見した。遠くに覗いている納屋の戸口に目を遣ると、そこには輝くばかりの外光があるばかりで、そこはいつまでも一枚の白いスクリーンなのだった。
その後、私たちはどうしたことであったか。失禁し、その上に泣き出してしまった私は反って度胸が据わり、黒姉えのものも見せろ、などとこちらから要求したりもしたのだろうか。それとも、悪態のひとつも吐いて逃げ出したであろうか。あるいは意気消沈の態でしょんぼりと家路についたであろうか。はたまた、近在の大人の者に助けを求めたりしただろうか。そのどれもが違った、私はしゃくりあげているばかりなのだった。彼女はそんな私の頭を強く抱き、私の心を落ち着かせると、しどけなくなっていた私の身なりをまるで実の姉のようなやさしさで、戻した。然る後、柔らかい藁蘂だけが堆積している納屋のもうひと隅へと私を導き、その中へと寝かしつけた。私は日向臭い藁蘂に包まり、黒姉えの薄っぺらな胸の裡で小一時間も眠ってしまったかもしれない。
黒姉えは私たちの前から忽然と消えた。だからといって遠い地に去ったというわけではない。さればといって、私たちと幽明界を異にしたわけでもない。が、その消えっぷりが余りに見事だったからか、まるで彼女がこの地上から消え去ったような印象を、かつての露地裏に集う仲間たちに与えた。
彼女も中学の最上級生だった。もはや、私たちとは遊ばないだろう。中学生になったばかりの頃は、それでも私たちと夢中になって戸外で遊んでいたが(そのことは書いた)、いつしか露地裏には一切、顔を覗かせなくなったのだ。もう、私たちとは遊ばない。黒姉えに私たちへの「アバな、チバな(また明日)」があったのだ。それだけのことに過ぎなかったから、再び、私は上の学校へ進んだ彼女を、村のバス停辺りに見かけることがあった。しかし、そこには剽悍な「黒姉ちゃん」の面影はなかった。その身のこなしからも、小鹿のような俊敏な気分は一掃されていた。あの黒姉えはどこにもいなかった。
彼女は大人になったのだ、私には解った。背丈も見違えるほどに伸び、あんなに小振りだったお尻も新しい制服のスカートの下でどこかふっくらと見えたし、黒姉えは色さえ白くなったように思われた。いつも不機嫌そうだった表情も穏やかになって、もう、手に棒切れなどを持った私を見ても口を歪めて笑わなかった。かつて黒姉えだった人は私と出会うと、訝しげに目で追う私に、いつも小首を傾げては莞爾(にっこ)りと頬笑むばかりなのだった。
私の「露地裏のジャンヌ・ダルク」は私の前から永遠に去ったのだ。
さて、余談だが、小学生の頃にはその将来をも何かと囁かれた彼女の脚力は、中学生の後半ともなれば著しく低下したそうだ。クラス代表が精々で、学校を代表しての陸上(徒競争)の選手に選ばれもしなかった。果して、そんなことがあるのだろうか。そんなこともあるのだろう。因みに、上の学校では、極めて趣味的な水泳クラブに所属していたと聞く。
更に、蛇足を承知で、私はその頃の黒姉えに纏ろう思い出をひとつばかり報告しておこうかと思う。こんなことがあった。
黒姉えの家の近くで、思えば「彼女の木」の辺り、私は紙ヒコーキを手にひとりで遊んでいた。私はこのような際、飛ばした紙ヒコーキに導かれるままに、どこへだって闖入して憚らない。興が乗れば尚更のこと、気が付けば、私は黒姉えの家の軒前にいた。すると、私を見咎めた彼女のお母さんから、あら、いい案配、とか言われてお赤飯のオニンコ(お握り)を振る舞われた。元来、私は赤いお豆の入ったお赤飯が大して好きでもなかったし、生憎なことには遅いお昼を食べたばっかりだったから、お腹も空いてはいなかった。そこで、要らない、子供なりにやんわりとご辞退申し上げたつもりなのだが、何、言ってんの、やけに大きなものを小母さんから押し付けられた。益(やく)もない遠慮とでも受け取られたのだろうか。とにもかくにも、そのお握りを手に、私はそそくさとひとまずの家路に着いたものだが、露地の途中で験しに一口遣ると、桃色のお握りは糊状を呈していて、私は子供の癖に、甘く、柔らかく、生温かいものを苦手としていたから、これはいかん、稀には娼家を兼ねたかもしれないお茶屋の塀の中へと、投げ捨ててしまったことだった。
話はこれだけでは済まない。
しばらくの後、何食わぬ顔で黒姉えのお家の界隈を徘徊していると、ここにおいで! 私は彼女のお母さんに捕まり、大変、きまりの悪い思いをした。実はお握りは塀の下から露地に転がり出ていたらしく、なんとも間が悪いことには、当の小母さんが砂に塗れたそれを見つけたものだ。その動かぬ証拠、私に捨てられ、小母さんの手によって拾われたオニンコは黒姉えの家の庭前で、今の今、入れ替わり立ち代わり放し飼いの地鶏たちが啄ばんでいた。要らないのなら要らないと言うの。どうにもはっきりしない子だろうね、黒姉えのお母さんからたっぷりと嫌味を言われたことではあった。
以上が、この蛇足の顛末である。私の為すことといったらいつだってこんな始末さ。
☆☆☆
当時の民衆に「ラ・ピュセル(乙女)」と呼ばれた中世のオルレアンの少女には、有体に申せば終に月のものがなかった。いつの日にか、彼女に纏ろう著述の中で、私はそんな記述を目にしたことがある。その節、私はとある感興に撃たれ、その感慨の下に「黒いラ・ピュセル、私の乙女」を巡って、しばしの「架空の思い出」に耽ったことではあった。と同時に、擱筆後、卒然とこれはもうひとりの失われた「美登利の物語」(私は一葉女史の手になるこの少女をこよなく愛する)、私なりの「たけくらべ」なのかもしれない、などと思ったりしたことも告白しておこう。
以上を記して、ここに私の少女奇譚を了とする。
付記
〔参考図書〕
・「ボルヘス詩集」鼓直訳篇(思潮社、海外詩文庫13.)。
・「ジャンヌ・ダルク処刑裁判」高山一彦編・訳(現代思潮社)。
・「ジャンヌ・ダルク」ジュール・ミシュレ著、森井真 田代葆訳(中公文庫)――(「彼女のやさしい思いやりと信仰心とは誰もが知っていた。彼女が村一番のできた娘だとみんなは心底思っていた。その彼らが知らなかったのは、上からのいのちが彼女の心の内にあってもう一つのいのちをつねに呑みこんでおり、それが彼女の世俗的な発展をおさえていた、という事実である。彼女は心身共に、子供のままでいるという神の賜物をうけていた。彼女は背丈ものび、逞しく美しくはなったものの、からだの苦しみは相変わらず知らないままだった。思想や宗教的霊感のおかげで、女のからだの苦しみを免れていたのだ。教会の鐘の音を子守唄に、さまざまな聖人伝説を耳にして育った彼女は、その誕生から死に至るまでが、束の間のまた清らかな、聖人伝説そのものだった」――尚、J・ミシュレはその原注に、彼女の老従者、ジャン・ドーロンの供述として、「ほんとうに、多くの女たちにあることがいわゆる乙女には…決してなかった」を挙げている)。
・「嬉遊笑覧(一)」喜多村筠庭著、長谷川強・江本裕・渡辺守邦・岡雅彦・花田富二夫・石川了校訂(岩波文庫)。
・「遊びと人間(増補改訂版)」ロジェ・カイヨワ著、多田道太郎・塚崎幹夫訳(講談社文庫)。
・世界の名著8「アリストテレス」は「詩学」(藤沢令夫訳)――「すなわち、その一つは、描写(まね)するということであるが、これは子供のときから人間にそなわる自然の傾向であって、人間が他の動物よりすぐれている点もこの点にある。つまり、人間はあらゆる動物のなかで、ものまね(描写)の能力を最もよくもっていて、最初ものを学ぶ(「学ぶ」に傍点)のもこのまねび(「まねび」に傍点)によっておこなうのである」。
・「陰名語彙」中野栄三編著(大文館書店)。
・「たけくらべ」樋口一葉著(新潮文庫)――(「美登利はかの日を始めにして生れかはりし様の身の振舞(ふるまい)、用ある折は廓(くるわ)の姉のもとにこそ通へ、かけても町に遊ぶ事をせず、友達さびしがりて誘ひにと行けば今に今にと空約束(からやくそく)はてし無く、さしもに中よし成けれど正太とさえに親しまず、いつも恥かし気に顔のみ赤めて筆やの店に手踊(ておどり)の活溌さは再び見るに難(かた)く成ける、人は怪しがりて病ひの故(せい)かと危ぶむも有れども母親一人ほほ笑みては、今にお侠(きゃん)の本性は現れまする、これは中休みと子細(わけ)ありげに言はれて、知らぬ者には何の事とも思われず、女らしう温順(おとな)しう成つたと褒(ほ)めるもあれば折角の面白い子を種なしにしたと誹(そし)るもあり、表町は俄(にはか)に火の消えしやう淋しく成りて正太が美音も聞く事まれに、唯夜な夜なの弓張堤燈(ゆみはりぢょうちん)、あれは日がけの集めとしるく土手を行く影そぞろ寒気に、折ふし供する三五郎の声のみ何時に変らず滑稽(おどけ)ては聞えぬ。」)。
(2019/12/22)
****** 次回は、1月10日の予定******
HOME
|

夢見るテレーズ
(バルテュス)
|