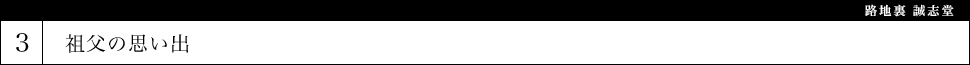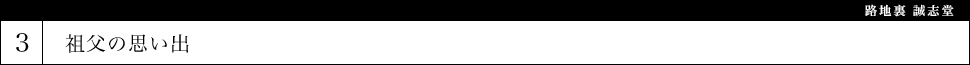私はここで、祖父の思い出を語りたいと思います。
とはいえ、私の幼児期には外祖父はおりましたが、同居した祖父は居ないのでした。なぜなら、祖母の連れである祖父は一人の孫も見ずに、五十歳そこそこに身罷っているからです。その祖父の思い出を綴ると言うのですから、自ずと非在の思い出となります。そんなことが果たして可能なのでしょうか、お楽しみ下さい。

〔白い軍鶏〕
猛暑の続く夏の日の、気だるい昼下がりのことでした。
家人との暑気払いのお昼寝から目覚めてみると、私の周りからは誰も彼もが消えていました。ぼんやりと頭を捻っていると、一挙に、耳を劈くほどの蝉しぐれが私を襲いました。が、耳慣れてもみれば、余りの一様なその喧しさはむしろ、深い静寂(しじま)のようにも感じられてくるのでした。中座敷で一緒に寝ていたはずの母や姉を叫ぶように呼んでみましたが、一向に返答がありません。漸(ようよ)う、私は無人の家屋にひとりであることを卒然と覚るのでした。うろうろと大して広くもない屋内を捜してみたが、当然、彼らはどこにも見当たりません。離れに居るはずの祖母に母屋の座敷框から呼び掛けてみても、梨の礫です。
どうしたものか、私はいささか心細くなって隣家に助言を求めようと思った矢先、庭前に、忽然と白い軍鶏が現れました。近所では、決して見かけたこともないような真白い軍鶏でした。其奴は悠然とその歩みを進め、上がり框に佇む私の眼前を、そこに私という人間がいるにも拘らず、何一つ臆することなく座敷に上って来たのです。その臆面のなさ、無礼さはいかばかりであったでしょうか。軍鶏の傍若無人の振る舞いには半ば呆れ、半ば気を呑まれ、私は何なすところもなく佇立していたことではありました。
こんなことは通常、許されないことなのです。開けっ放しの人気のない百姓家の座敷に、しばしば放し飼いにされたニワトリが上り込むことがあります。ありますが、直ちに土間の方から家人の声が掛かり、そんな時こそ私たち子供の出番、不埒な侵入者を一喝! それでも言うことを聞かないようなら、座敷箒のひとつも手にして、追い出しにかかります。その程度の働きは農家で育った子供であれば、幼児ほどの年嵩の者でも自然と身につく「小さな大人」(F・アリエス)としての矜持でもあります。そこはたとえ大振りの軍鶏の類いであっても、同断。だから、この白い禽獣の行為は私の人間性に対する侵犯、大袈裟を承知で記せば、私たちの「類」に対する侮辱ですらあるわけです。私は軽い眩暈さえ覚えました。
それにしても、白い軍鶏とは! そう、あれは白色レグホンなどではありませんでした。だって、あんなに大きなニワトリなんているはずがないもの、軍鶏としたってかなりの大物です。巨大な体躯と威風辺りを払う堂々とした物腰はやはり、闘うために飼育されたその手の一羽だったのです。幼児との対比で云えば、巨大と云う形容もさほどに誇大とは思われません。ほぼ等身大(と、どんな錯視が働いたのか、その節の私にはそう思われたのです)の一羽の禽獣があなたの目の前に、突如出現したところを想像しても欲しいのです。
尚、わが地方の一部では当時、闘鶏が盛んに遊ばれ、私の近所のとある家でも、近々、闘う予定の軍鶏たちに、活餌として、シマヘビなどを与えていました。私は実見したことがありますが、そんな際での軍鶏どもの獰猛さには心底、慄然とさせられたものです。
さて、頭部の天辺に一点だけ鶏冠の紅を載せた白く耀く軍鶏は座敷框に跳び上がるや、二度三度、小首を傾げていましたが、やおら悠然と表座敷から裏の座敷へ、その歩みを進めたのでした。道を譲ったのはこの私の方です、なんともはや! さてこそ、私は好奇心に駈られたものか、その後を尾けた、尾いて行きました。行くと、奥座敷の母の嫁入り道具であった桐箪笥の上に祖父がいたのです、箪笥の上部に腰掛けた格好で。
今にして思うと、そのシチュエーションが不思議に感ぜられます。祖父は矮躯などではなく、偉丈夫と聞いていましたから、天井に頭をつっかえもさせないで、箪笥の上などによくぞ座っていられたものか、随分と怪しくもあるのです。でも、その時の私にはどんな違和感もなく、祖父は自然に、尚、立派に見えました。爾後の、記憶の捏造があったのでしょうか。
とまれ、祖父は紋付きの羽織を羽織ったいでたちで、私の名前を呼び、来たか、そのようなことを言った気がします。私はとても恥かしいような気がしてもじもじしていると、玄関の方で母や姉の笑い声がしました。周章てて、私は表に戻りました。戻って、どこに行ってたのと詰る遑もあろうか、お祖父ちゃんがいるよ、と家人に告げていたのです。歳の離れた姉は疳高い笑い声を挙げて、また寝惚けた、と馬鹿にしました。なぜか祖母もそこにいて、まじまじと私の顔を見遣り、どこだ? と尋ねました。私は黙って父と母の寝室でもあった奥の座敷の方を指さすと、何やら深く頷き、仏間も兼ねている居間の「仏さま」へ、そこでお線香を上げ始めました。
私はその頃、祖母と同居していました。そのことはどこかで語ったと思いますが、祖母の寝物語の解説によれば、私の父方の祖父はもう、随分と昔に逝去していたのですが、ひとりの孫の顔を見ずに虚しくなったから、男孫の私の顔を見に来たということです。私には兄がおりましたから、なぜ兄ではなく、私なのかとも思いましたが、ここではそのことを問いません。
以下は当時の私の解釈ですーーあんなに生身の人間らしく見えたのですから、あれは生身の人間で、誰か見ず知らずの、偶々、私の祖父に肖(に)ていただけの初老の男が、子供の私をからかうためにあんな所業に及んだのだということです。それとも、私の白昼夢、単なる幻視の類い?
いや、そんなことは今となっては、当時ですら、私にとってはどちらでもよいことのようにも思われていました。それよりも何より、白い生きものの方にこそ、当時も今も私の関心は向かうのでした。姉の素頓狂な声で、奥座敷に何やらの有り難い置き土産があったらしいことからも、その実在が疑い得ないかの軍鶏のことです。こちらが子供とはいえ、人を人とも思わぬ、しかも耀くばかりに白く、猛々しくも美しい、あんな立派な禽獣が実際に存在し得たということが、私にはむしろ、夢の中の出来事のように思われるのでした。
以上が、私の「祖父の思い出」です。
因みに、我が家の中座敷の壁には、写真から描き起こしたと思われる八号ほどの祖父の肖像画が、早世した叔母に中る少女の、いかにも昔然としたセーラー服姿の画像とともに掲げられていました。だから、祖父の面影は、子供の私にはとても馴染みの深いものではありました。


☆☆☆
ところで、飛来する白鷺などの白い鳥は祖霊の来臨、その回帰現象のひとつなのだとする民間信仰を、私はものの本で読み齧ったりもしますが、そのような原始感情(アニミズム)には、先のような経験を持つ私にはかなりの親しい気分を持ちます。
思えば、日本の白は喪の色でもありました。白の本来は「忌々(ゆゆ)しき色」なのだと宮田登に見えますし(「女の色〈白〉」)、16世紀のイエズス会の宣教師の書には「われわれは喪に黒色を用いる。日本人は白色を用いる」があります(「ヨーロッパ文化と日本の文化」ルイス・フロイス著、岡田章雄訳注、岩波文庫)
ところで、白い生き物の中でも「白蛇」については子供の頃、そのような蛇の実見譚は時に耳にし、祖母などに又聞きのそんな話を告げたりすると、決して虐めてはいけないと、くれぐれも戒められた思い出があります。そのことは拙著「筑波の牛蒡」は「白い蛇の話」でとうに書きました。
※付記
梅原「日本では鳥、特に渡り鳥、白い鳥ですね。それは先祖の霊が化したものじゃないかという考えは、まだついこの間までありました。アイヌの古老としゃべっていたら、やはり先祖の霊は普通成仏するけど、成仏出来ん霊があって、どうしてその成仏出来ん霊があるのを知るかというとですね、しきりに鳥が来て、チュンチュンとする。鳥がそうしてるのを見ると、アイヌの人は、これはあの人の霊は成仏出来てない、まだ怨みを、執着をこの世に残していると考え、その霊を手厚く祀るのだと言っていました。平安時代の話を聞くようでした。「万葉」の時代から、いや、もっとずっと以前から現代まで、その考えが続いている。それがまだアイヌの世界に残ってるということに驚きました。」……
――白川静・梅原猛対談「呪の思想(神と人の間)」(平凡社)より。
…日本古来の「しろ」は、古代中国の権力や権威を示す色彩名の「白」ではない。日本古来の「しろ」は、当時の日本人が不思議と感じたことで、人間や自然現象以外のもの、つまり当時の信仰の対象に関係のある何らかのものや、怪異的なものを表すときに用いた、とみるのが適当であろう。
――ものと人間の文化史「色―染と色彩」前田雨城著(法政大学出版局)より。
茨城県下では、葬儀、法要の御飯を「白ふかし」という。餅米で作るのだが、赤飯のように赤小豆を用いず、白いんげんを入れ、味つけに白ごまを使っていた。昭和十年代までは、近親の女性は、嫁入りの時に白むくの着物を着て会葬した。白い手拭を被り、足ははだしで、わらぞうりを履き野辺送りに行って、帰りには履物を脱ぎ捨て、素足となる。葬儀の行われる門前に立てる白提灯、その立ち柱、墓標、位牌はいずれも白木でなくてはならない。黒わくなどはもちろんない(『茨城の民俗』十七号)。全て真白の装置で白ずくめの人々によって、葬儀は行われたのである。……
――宮田登著「ヒメの民俗学」(青土社刊)より。
二疋の大きな白い鳥が
鋭くかなしく啼きかはしながら
しめつた朝の日光を飛んでゐる
それはわたしのいもうとだ
死んだわたしのいもうとだ
兄が来たのであんなにかなしく啼いてゐる
……
――宮沢賢治「白い鳥」(「春と修羅」に所収)より抄出。
****** 次回は、5月25日予定です ******
HOME
|