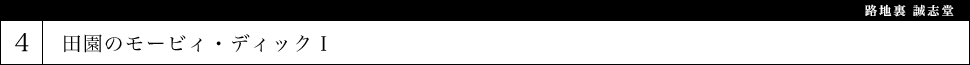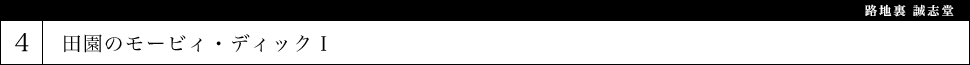写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
俗(くにひと)いはく、蛇(へみ)を謂(い)ひて夜刀(やつ)の神(かみ)と為(な)す。其の形(かたち)は、蛇(へみ)の身(み)にして頭(かしら)に角(つの)あり。率引(ひきゐ)て難(わざはい)を免(まぬが)るる時、見る人あらば、家門(いへかど)を破滅(ほろぼ)し、子孫(うみのこ)継(つ)がず。凡(すべ)て、此の郡(こほり)の側(かたわら)の郊原(のはら)に甚(いと)多(さわ)に住(す)めり――「風土記」秋本吉郎校注(岩波書店―「日本古典文学大系2」)。
小学校も低学年のころ、同じ集落のガキ大将の下、私は数人の仲間と共に白い蛇と死闘を演じたことがありました。以下、小説仕立てにして、その思い出を書いてみようと思います。なぜ、小説仕立てにしようとしたのか、多分にその方が活劇的興趣が出るかもしれない、という判断が働いたのかもしれません。ご了承下さい。
☆☆☆
《ガキ大将》
蛇の季節とは言い難い、秋も随分と深まった時分だったと思う。陽もやや傾いた頃、村の旧家の、私たちよりはうんと年嵩の悪ガキから急を告げるお声が掛かり、何ごとかと彼の家に行ってみると、その裏庭には近在の遊び仲間が都合七、八人ばかりが集まっていて、何やら興奮の態。その中心には我らがガキ大将がいて、もうすぐ中学生だと云うのに、ズボンのベルト代わりの荒縄には、篠竹が二本ばかり、なんのつもりか二本差しに差されている。丸首の手編みのセーターの胸には、何やらの瓶の王冠が何個か付けられている。年少者たちの大将であるこの少年は日柄年中、そんな恰好で近在の幼い手下を始めとして、やや年嵩の者、時には同年輩の猛者たち、場合によっては少しくトロいとされる、彼よりはずっと年上の者までも引き連れて、季節(とき)を選ばず、田野を駆けずり回っているのだった。
私たちの村ではこのような少年をやや蔑みを込めて、野良坊と称した。
彼は年嵩の割には小柄な口だったが、その身体能力には群を抜くものがあった。身軽で、目敏く、足も速い。しかも、手先が器用、どんな遊び道具も自前で作る。その一端をここに示せば、自転車の車輪のスポーク(輻)をバインダーで尖らし、それらを竹棹の尖端に取り付けては長短様々の簎(ヤス)に仕上げてみたり、一尺三寸ほどの竹筒の先にY字の金具を取り付け、そこに腰の勁いゴムを張っては命中精度の高いゴム銃(と)(パチンコ)を作ったり。
中でも、彼の手になる針金の弦を張った小振りな弓などは絶品だった。縦に裂いた孟宗竹の本体は要所要所に焼きが入り、その握り、弓束(ゆずか)には棕櫚を裂いて綯った紐が律儀に巻かれ、その他にも色々と工夫を施し、例えば弦を結わえる竹の端、末筈(うらはず)にはちゃんと切れ目が入っていて、弦の弛みを決して許さない構造になっていた。どうして粗野そのものと申してもよいガキ大将に、あれほどの丁寧な仕事が可能なのか。しかも、多分にそれらは当時、村の野良坊たちの必須の持ちもの、あの「肥後の守」と呼ばれた簡易なナイフ一本でなされた細工であったと思えばこそ!
そもそも、大将のそれらは遊び道具と云うより、主には実戦に用いられた。つまり、彼は村の採集の民であり、村の周辺で彼の関心を逃れ得た木の実や果樹の類いは絶無だったろう。その採集の際には、そのスポーク製のヤスが活躍した。また、近在の湖沼や河川にあってはあらゆる伝統的漁法をマスターした漁る人でもあり、野にあっては俊敏な狩人だった。私たち年少者はその異能異才振りに、文句なしの畏敬を捧げた。
そして、私たち幼き者は彼に忠義を尽す替わりに、その獲物のおこぼれに与った。彼は彼が獲得したものにそれほど吝嗇ではなかった気がする。むしろ、淡白なほうと申してもよかった。
そして、私たち幼き者は彼に忠義を尽す替わりに、その獲物のおこぼれに与った。彼は彼が獲得したものにそれほど吝嗇ではなかった気がする。むしろ、淡白なほうと申してもよかった。
そんな彼でも、その頃の少年たちのもうひとつの関心ごとであった模型ヒコー機の製作などには、いっかな興味を示さなかった。とはいえ、彼とは別のタイプの工作少年、その少年たちのヒコー機が村のひと際高い喬木の尖端に遭難したと見るや、逸早くその場に駆けつけるのは、決ってこのガキ大将だった。それも不思議なことではあった。
彼はどのような状況下であれ、猿(ましら)のように木に登ると、木の天辺で枝を揺らし、時には持参した長い篠竹を曲芸師もどきの身のこなしで操り、必ずや遭難機を救出するのだった。救出するや、彼の関心はもう、そこにはなかった。礼には及ばぬ、その態度は一貫していて、彼は工作少年たちとハッキリ一線を画しているようだった。そのことはこちらの少年たちにも了解されていて、互いに軽く頷き、暗黙の裡に別れた。
私はどちらかと言えば工作派のお兄ちゃんたちにシンパシーを抱いていたから、そんなお兄ちゃんたちの後を、金魚の糞のように付いて回った。だから、そのようなシーンには一度となく遭遇した。そして、その辺りの両者の機微には、子供心にもどこか大人めいたカッコよさを感じたものだ。
そのガキ大将が、今や私たちを自分の屋敷に蒐めて、白い蛇が終にお出ましになったと言うのだった。この眼でしかと見たのだから、しかもデカい、それはそれは大きい奴なのだと身振り手振りよろしく繰り返した。その実体は多分に白く変異した青大将あたりであったろうが、こちらの大将によればこれが二度目の邂逅なので、一度目は一瞬のことでまさかと思い、今回は結局見失ったが、その存在はたしかに確かだと言う。
私たちは何度も繰り返される彼の話に、固唾を呑んで聞き入った。しかる後、まずは現場へということとあいなった。戦雲、急を告げるとはまさしくこのこと、だ。大将ん家の屋敷内のそこかしこから、それぞれがそれぞれの適当な得物を手にした。得物といったって、主にはやや長尺の女竹、太目の篠竹、はたまた納屋の心張り棒ほどの棒切れなどだ。中には、私の地方では稲架(はざ)をオダと呼んだが、その脚の尖端を槍状にした竹棹を持ち出す兵(つわもの)さえいた。今にして思う、あのオダさえ持って!
これは只事ならず、私は幼いなりに武者震いをした。これは大変なことになったものだ、いやはや。
私たちは思い思いの武器を携え、大将の言いつけに従った。
私たちは皆、決戦に備えまずは裸足になった。予めそのようなしている者もいた。そうだった、私たちはとかくに裸足を好んだのだ。学校へはさすがにそうともいかなかったが、一旦、我が家に帰れば、下駄(!)やズックを早速脱ぎ捨て、野良へと飛び出した。当時の村の子供たちの放課後は、大方、そんなようなものだった。
我らが一行は、旧い農家ならではの、鬱蒼と生い茂った屋敷林の木の下闇を通り抜けた。裸足の蹠(あうら)に日陰の湿りを含んだ地べたはヒャッコく、朽ちた葉っぱがこそばゆかった。が、そそくさとそこを抜ければ、そこには屋敷と田のフィールドを分かつ小幅な流れが流れていて、粗末な一枚板の石橋が架っている。渡れば、その流れに沿う小道の自然に出来た二本の轍の上は、晩い秋の陽をたっぷりと浴びて乾き、裸足の足に心地良いのだった。私たちは小川沿いの、未だ青きを残すものを踏み、流れを遡り、小さな冒険の旅に着いたのだった。



******次回(6月1日予定)へ続く******
HOME
|
 
肥後の守
|