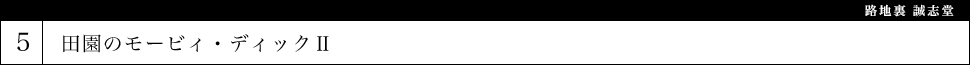
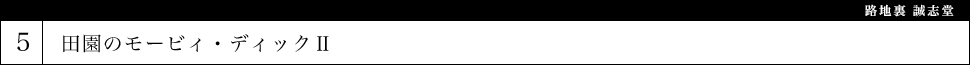 |
文 田中秋男 1948年生まれ
|
《白蛇伝説》 《探索》 さて、私たちは餓鬼大将の指図により、本格的に、川沿いの探索に中った。 大将は小川を跳び越え、単独で向いの淵やその周辺の捜査に掛かった。我らは小川沿いの叢や畦の隈々を竹棹や棒切れで探った。所々に架かる丸太の小橋や土橋を利用しては岸を交互に換えて、はたまた橋の下などは腹這いになってまでして必ず覗き、入念に調べた。しかし、探索の成果はすぐにとは揚がらなかった。秋の日は短い、急がなければならない。私たちにもやや焦りの色があった。 ところが、私などはまだ小半時も過ぎてもいないのに、もう探索に飽きあきしていた。それが幼少時以来の私の地金でもあるにはあったのだが――白い大きな蛇? そんなものがホントウにいたのだろうか。大将の思い込み、あるいは早とちり? あり得ることだ。だって、大将はその白いとされる蛇に常日頃からあんなにご執心だったのだから、見間違うってこともないわけではない。人並みの青い太い蛇や赤茶けた小振りな蛇、あるいは黄色い縞の細身の蛇などは、こんな私だって掃いて捨てるほど見てはいるが、いくらなんでも白い蛇だなんて。そんなものは単なる噂話に過ぎないのだ。きっとそうだ、そうに違いない。 私はもう、白い大きい蛇などいないと勝手に決め付けてしまっていた。でも、年長者の後に粛々と随いながら、体裁だけは整えて、フデチクと呼ぶ女竹の釣竿で川面を捨て鉢気分で、掻き混ぜ、掻き混ぜ、探しているフリだけはしていた。 いない、いない、いない。いない、いない、いない…、 そんな時だ、足早に堀の上流に向かっていた連中の方で、癇高い悲鳴が挙がり、誰やらの川に嵌る水音がした。 もしや! 私たちがそちらに向かうと、ひとりの男の子が腰まで水に漬かり、声の限りに喚いている。い、い、居たのだと言う。かの男の子はそのものを見て腰を抜かさんばかりに驚き、挙句に小川に足を滑らしたらしい。居たんだ、ホントに居たんだ。私たちの問いかけに、彼は、白いものは下流へ泳ぎ去ったと言う。下流からやって来た私たちは水面を蛇行する、そんな姿を見てはいない。 ということは、どういうことなのか…、驚くべきことに大将はいつの間にかその場にいて早速の下知、彼の命により川上へ、私たちは速やかに川面を探った。居ない。念のため、川下へも、居ない。私たちは慌ただしく二手に別れ、小川沿いを右往左往した。大将は? と見るとその場を動かずに、とある一点を曰く有り気に凝視めていた。何や、ある。私たちは大将の下に足早に駆け戻った。戻ってはその視線の先を目で探る――い、居る! 私たちの目と鼻の先、草深い小川の淵に、彼奴はその身を真っ直ぐに伸ばし、潜んでいた。なんと云う狡猾、逃げたと見せかけて、おのれはあくまでもその場を離れずにいたのだ。うぬ! ******次回(6月5日予定)へ続く****** Tweet HOME |
|
| © 2019 路地裏 誠志堂 |