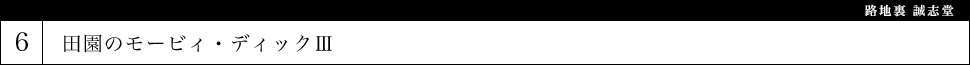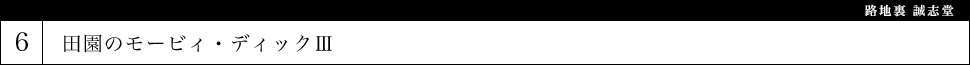写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
《死闘》
私が生まれて初めて実見するそれはなんと言う、白さだ。その白さはもはや発光する銀(しろがね)。そして、なんと言う偉丈夫なことであったか。その胴回りは私たち子供の脛ほどもある太さで、その長さは優に一間、あるいは越えていた、か。その静謐な佇まい、その不気味。威あって猛からぬとはこのこと、か。そして、何より、白皙の頭部に赫奕と耀く一点の眼(まなこ)。私たちは夢でも見ているような気分で、何なすこともなくその一本の姿に見惚れていた。
しかし、我が大将は豪胆だった。そして、細心だった。
しばし、その白く耀く姿を睨(ね)めつけていたが、私たちの集合を確認するや両の拳をうち震わすほどに握り締め、疳高く、裂帛の叫びを叫び、そのものに敢然と挑む気構えを示した。まずはその行く手を阻むことを我らに命じ、更には刈田の稲の切り株を引き抜き、それをもって速やかに彼奴を攻撃すること。
自ずと、私たちは二手に分かれた。
白い蛇はそんな我らが気配を察すると、悠然と、そして逸早くその身を移動させた。水面に揺曳する白い帯。
幼き者たちは手にした得物でその行く手を遮るべく、盲滅法、先々の川面を叩いた。やや年嵩の者たちは土くれのたっぷり着いた切り株を、そのもの目掛けて投げ込んだ。しばしの遣り取りがあっての後、当のものはこれは敵わぬとでも思ったのだろうか、身を翻して小川を脱し、刈田の方へと逃れた。しめた! それが我らが大将の付け目だった。
大将の思惑通り、稲の刈り取られた田圃が、私たちの主戦場と化した。
野良坊大将は誰よりも勇敢だった。そして、剽悍だった。二本の細身の篠竹を手に、率先してその白く「ながすぎる」ものとの闘いに臨んだ。行く手を遮り、絶妙な間合いを保ち、隙を見つけては二本の篠竹を巧みに操り、その体躯に比しては著しく小振りな白蛇の頭部を果敢に鞭打つのだった。
彼の叱咤に励まされ、私たち幼い者も彼に倣った。多少、腰が引き気味、おっかなびっくりの態ではあったが、白い長すぎるものの周囲に群がり、喚き散らしては自分自身を奮い立たせ、挑んだ。ある者は土くれを投げつけ、ある者は手にした棒で撲りかかり、ある者は竹棹を突き立てた。
私だとて、ここに至れば遅れは取るまい。身に余る長尺のフデチクを良いことに、たとえ遠めからであってさえ、それでも果敢に、一度ならず、二度三度と竿の尖端で彼奴を打った。しばしば稲株に足を取られ、幾度となく転(まろ)びながらも、私は必死に戦ったことではあった、なるべく彼奴との正対は避けたが。
では、他の幼い者たちはどうであったか。彼らだって、私と相似たものだった、田圃を転げ回っては、当のものよりは地べたの方を頻りに叩いていた。私たちはなにやらの童児祭祀の所作事でもしていたのだろうか。淡い夢の中でのスロー・モーションのような動き――今ともなればそんな感想を持つが、いやいや、それでも幼い者には幼い者なりの手柄はあったのだ。蛇の行く手を遮る程度の役目は、それでも果していたのだから。
そこへ行くと二三の年長者の実直な戦い振りには、目を瞠るものがあった。確実に彼らは彼奴を追い詰めていた。
当初、多勢に無勢、逃げるに若くはない、太く白い蛇はこの難を避けることだけを心掛けているように思われたが、私たちの執拗な攻撃に業を煮やしたか、あるいは逃れ切れないと観念したものか、やおら攻撃に転じた。時には鎌首を半身ほども擡げ、頭部を二つに裂いては私たちを威嚇した! 爛れたような、どす赤い口裏が見えた。更には二つに割れた舌先を、か細い火焔のようにちらつかせ、すわ、白く長い帯状のものは跳ぶ。宙に太くS字が舞った。私たちは跳び退った。
しかし、私たちも気丈だった。逃げ出したい気持ちを堪えに堪え、ここは私たちなりに私たちの面子がかかっている、逃げるわけにはいかないのだ。ましてや大将への義理もあった。彼が終戦を宣告しない限り、この場を立ち去ることは出来ない。その思いはやや年嵩の者たちも同様だったろう。
戦いは一進一退だった。蛇は逃げると見せかけてはこちらに手向かい、私たちはたじろぎ、其奴はその間隙を縫って逃走を試み、私たちはそれを許さず、ここまで来るともはや、互いに意地の張り合いだった。
ガキ大将はまるで発情した猿(ましら)だった。終始、奇天烈な喊声を挙げ続け、当のものが逃げ去る素振りを見せるや、至近の距離にその身を曝して挑発した。あろうことかコンチキショ、その尻尾を掴もうとさえしたのだ。果して鷲掴むと、一刹那のことではあったが引きずった! なんと云う豪胆、大胆不敵。蛇は真っ赤に口を裂いて、身を翻し、電光石化、その手元を襲う。しかし、不発に終るや、彼奴は怒りに駆られて私たち幼い者の方へと突進を図るのだった。
すると、大将は悲鳴とも笑いともつきかねる雄叫びを一際高く挙げ、コンチキショ、一層奇怪な身振りを交えて蛇の周囲を駆けずり回るのだった。機を見ては蛇体を跨ぎコンチキショ、幾たびも跳び越え、その鼻先でフット・ワークよろしく右、左、左、右とタップもどきを踏んだ。舌を突き出しコンチキショ、お尻ペンペン、コンチキショ、卑猥な仕種も交え、身をくねらせては、コンチキショ。大将は「こん畜生」の目の前で、とうとう、お得意のトンボさえ切った。しかも、二度、三度と!
今や大将は闘っているのではなく、白蛇と戯れているのではないのか、私はそんな疑念さえ抱いた。ふと、彼の日頃の振る舞いが私の頭の中を過ぎる。常々の彼の説明に拠ると、垂直にぶら下げられた蛇は、尻尾を掴んだ手元にまではその身を翻すことができない。つまり「し」の字がせいぜい、彼は並の蛇ならポケットから取り出し、いつだってそんなことをして幼い私たちをからかった。どころか、暑い日にはこうして涼を取るのだとばかりに首に巻いたりもしたし、挙句にはその頭部を口に含んだりもする(!)。
…闘いは続いた。
日は暮れ始めていた。互いに隙を窺っては、攻め、あるいは退き、子供たちと白い生き物は精魂を込めて渡り合ったのだった。そして終には、この生き物は私たちの手を見事に逃れたのだ。思えば、それはなんと言う狡猾さだったろう。蛇は私たちと死闘を繰り返しながらも、その戦いの場を巧みに操り、枯れ田の際の、葦深い沼沢地へと傷だらけの大身を移動させていたのだ。その上で、息も絶え絶えにその身を横たえた。と、私たちには見えた。なぜなら、我らが白蛇は肥えに肥えた不気味な蛇腹を、今にして思えばわざとのように覗かせ、横臥していたのでもあったのだから。
私たちは恐る恐る私たちの半円を縮めた。互いに顔を見合わせ、この事態はたしかに確かなことなのか、おのが疑念を確認しあいながら――と、その油断の一瞬を衝いて、彼奴のどこにそんな力が残っていたのだろう、まるで見えない手に引き摺られでもしたかのようにスルスルスルスル! 移動は一陣の疾風だった。干上がって今や枯れた葦原めく沼地に、その眞白き姿を晦ました。
もはや、これまでであった。
《終戦》
日はとっぷりと暮れていた。遅い秋の真っ赤に焼けた西の空は暮れ泥み、地平近くに大きくうねる雲の腹は、残照の、血の色めく臙脂に染まっていた。その棚引く雲の背はドブ色に変色し、その果ての澄んだ藍色の空には、やがて、私たちに馴染みのあの一番星が耀き出すだろう。
餓鬼大将は何も言わなかった。我々にどんな下知もなかった。大将は白い蛇の去った葦原を幾分、肩を落し気味に見遣っていた。そのだらりと下げた両の手には篠竹が力なく握られていて、私には小刻みに震えているかのようにも見えた。無念遣る方なかったのだろう、か。それとも? いやいや、この期に及んでそんな斟酌は無用の配慮、私などの分際のよくするところではない。
幼い私たちは我らが餓鬼大将をその場に残し、「アバナ、チバナ、マタ明日」――いつもの唱え言を交えた喧しい別れの儀式もせずに、ひとり去り二人去り、互いに無言の裡に別れを告げたのだった。年嵩の者たちもいつしか去った。私は後ずさりしながらも、子供ながらに大将の孤影を目に焼き付け、やおら踵を返し、皆に倣った。
すると、私の背後で、さわさわさわ、さわさわさわ…と、枯れた葦原が幽けく騒めいた。一陣の野分が葦原を裂いて行くような、さわさわさわ、さわさわさわ…。
私は決して後を振り向きもせずに、一目散に家路を急いだことではあった。
☆☆☆
以上が、私たちと白蛇との戦い、その思い出のあらましです。
私はこの日の出来事を、同居を余儀なくしていた祖母を含めて、家人には何ひとつ告げはしませんでした。が、その幼少時に、私が親しんだ年嵩のお隣のお兄ちゃんには、その一部始終を巨細に亘ってお話したことは憶えています。かの悪ガキも私のお兄ちゃんには一目も二目も置いていましたし、やや後輩に中る年恰好のこの大将を、お兄ちゃんもどこか悪からず思っていた節があったのです。
きっと大将は…、私の多少の虚構と想像を交えた報告に、お兄ちゃんがどんな感想を洩らしたかは、私には何ほどの記憶もありません。それとも、あいつのことだから、まあ、そんなこともあり得るね、と静かに頬笑んだほどの反応だったかしら。
今の私なら、あの時のあの大将は長すぎる白い生き物に取り憑かれた、田園の小さな「エイハブ船長」のようだったな、そんな所感も持ち、こころ妖しく思いも出されるのでした。
王冠の勲章付けてガキ大将(崩彦)

付記
メルヴィルの作品群は、海洋冒険小説、幻想的・風刺的な小説、詩、短編、そして畢生(ひっせい)の大作たる象徴的小説「白鯨」から成る。短・中篇の中で想起されるべきは、義と掟の葛藤を主題とする中編「ビリー・バット」、コンラッドの「ナーシサス号の黒人」をある面で先取りしている「ベニト・セリーノ」、そしてカフカ晩年の諸作品と似た雰囲気を持つ「代書人バートルビー」である。「白鯨」の文体にはカーライルとシェークスピアの影響が見てとれ、実際、劇の一場面のように構成された章もいくつかある。忘れがたい語句が作品じゅうにあふれている。作品がはじまってまもない章で一人の牧師が出てくるが、説教壇にひざまづいて一心に祈るその姿は「海の底でひざまずいて祈ってるように見えた」と形容される。モービー・ディックとは悪の化身である白い鯨の名であり、この鯨を追う狂える追跡行が作品の筋となっている。興味深いことには、鯨は九世紀のアングロ=サクソンの動物寓話集でも悪魔の象徴として出てくるし、白はおぞましいという発想はポーの「アーサー・ゴードン・ピム」のテーマのひとつをなしている。メルヴィルは作品のなかでわざわざ、これは寓意物語(アレゴリー)ではないと断っているが、実のところこの作品は二つの次元で読むことができる――作者によって思い描かれた一連の出来事を綴った物語として、そして象徴的な寓話として。
――「ボルヘスの北アメリカ文学講義」(柴田元幸訳、国書刊行会)より。
ここで私は、衝撃を受けた別の本、メリヴィルの「白鯨」を思い出します。エイハブ船長を信じているかどうか、私には自信がありません。白鯨との闘いを信じていることにも自信がありません。登場人物をいちいち区別することもできません。しかし、私はストリーを信じています。つまり、一種の寓話と信じています(もっとも私は、それが何の寓話なのかを正確には知りません。恐らく、悪に対する闘いの、悪との間違った闘いかたの寓話でしょう)。こんなことが言える本が他にあるでしょうか?
――「ボルヘス、文学を語る」(鼓 直訳、岩波書店)より。
******次回は、6月15日の予定です******
HOME
|

|