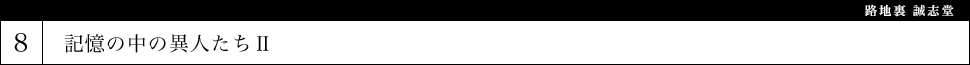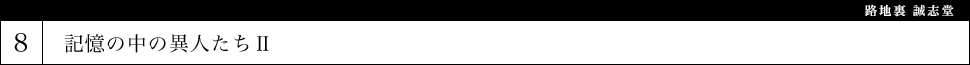私らの在所では、惣領以外の庶子を「オンツァ」と言いました。
オンツァは叔(オ)ン父(ジ)の転訛、丁寧に云えば「オンツァマ」となります。オンツァマは叔父さまの約まった形です。どちらも一定の文脈で、特定のニュアンスを籠めて使用されると、覿面、その意味は貶められ、虚仮、愚者の謂いとなります。何ほどかの知的障害を持った青年などは殊更にオンツァマの尊称で呼ばれ、その名の下に蔑まれ、いや、ある種の畏敬を以って対処されました。以下、そのような青年の思い出です。
ある「計測フィリア」の話
彼は色白のまだうら若い青年で、その個人的事情による表情の弛みなどを差し引けば、白面の美しい若者とさえ言えたかもしれません。が、如何せん、彼の鼻孔からは浅黄色した洟汁が人中を挟んで、いつも二本ほど垂れていました。洟汁の周辺部は元の色味を多少は残し、干からびています。とまれ、その濃度の高い洟汁を私たちはブドッパナと殊更に貶めて呼び、鼻孔と上口唇の間を忙しなく行き来する水っ洟とは、その応対を異にしました。
因みに、ミズッパナが口唇を不覚にも横断してしまう事態を、私たちは「利根川を渡る」などと揶揄したものです、思うに滅多にはないことでしたが。なぜなら、ミズッパナはその寸前、鼻孔の方に律儀に啜りこまれるか、袖口でこまめに拭い去られたからです(テッシュで鼻をかむ? 当時、そんなことを誰が行い得たでありましょう)。ですから、「川を渡る」ような事態は尋常とは思われず、多分に風邪引きの初期症状とみなされるか、あるいは当事者の油断、落ち度として軽い非難を受けるに止まりました。稀なることではあるし、まあ、許せる範囲のご愛敬といったところでしょうか。
閑話休題。
ことほど左様に、水っ洟が大目に見られるとは違い、ブドッパナは私たち幼児の間にあってもイタダケ無イことでありました。それは見た目の奇異さだけに止まらない、異様な状態を告知していましたからーー重度の風邪、副鼻腔炎の症例、あるいは自尊心の著しい欠如、また、それに所以する「超俗性」などを意味しました。シーニュ(記号)としてのブドッパナのシニフィアン(能記=意味するもの)から導かれるシニフィエ(所記=意味されるもの)は、そういうことでありました。
つまり、私の思い出の中の彼は、何よりもブドッパナを垂らす人でした。
その上で、彼の彼たる所以の奇矯な振る舞いを、今にして思えば「計測フィリア」、そう、彼は計測狂だったのです、そのことを語ります。
オンツァマは常時、長短様々の竹竿を所持し、その篠竹の竿のことごくにはどのような基準で取り付けたものか、色とりどりの布切れがリボンのように結ばれていて、その間隔は私たちにはとてもデタラメ(恣意的)に思えましたが、それが彼の物指しなのでした。それらの竹竿を駆使して、彼は村の家々の建造物、主に納屋、家畜小屋等々を計測するのです。その奥行、間口等を微に入り細に亘り、計りました。されど、私の見るところ、鼻孔から垂れたままの決して処置されない洟汁と同様に、高低には関心を示しませんでした。但し、長尺の竿の一本を地面に立てては仔細あり気に遠くを望んだりしましたから、建物の傾きはチェックをしていたのかも知れません。
しかし、早計は禁物です。そこには彼ならではの、どんな深慮があるのか計り知れないからです。計測してはしばしば凍り付いたように沈思黙考し、やおら、再び己の仕事に没頭します。家人不在の農家であれ、農事に忙中の農家の只中でさえ、彼はそういうことには一切頓着せず、喜怒哀楽を超越した面持ちで家々を横断し、ひたすら彼我の「世界」を計り続けるのでした。彼は物乞いではなかったので、何ほどかの供応にも無関心でした(「人間はパンよりもなお至高性を必要としている」! ジョルジュ・バタイユ)。村人たちもそのことをしかと理解しており、オンツァマの赴くところ、彼のなすがままに放置しました。その真の孤高の姿には気を呑まれるのか、村の悪童たちが彼に悪さを働いたという話は聞きませんでした。また、村人の次のような会話は紹介するに値するものと考えます。
――オンツァマに計られたか。
――ああ、どうやら計られたようだ。
オンツァマは近郊の村々を、彼の計画に則って黙々と計り続けたものと思われます。いずれにせよ、私たちの世界はオンツァマの竹竿によって計測されてしまったことには違いがないのでした。
「…基本的形態を規定手段として、いくつかの、そして結局はすべての理念的な形態を操作的に規定するというこの幾何学的方法は、すでに学以前の直観的な環境において、最初はまったく幼稚な仕方で、次いで技術的におこなわれていた測量的規定や、さらには測定的規定の方法にまで遡られる。この測定的規定のねらいは、この環境の本質的形式のうちにその明白な源泉をもっている。環境のなかで感性的に経験される諸形態や、感性的直観によって思い描きうるかぎりの諸形態と、普遍性のあらゆる段階において考えうるかぎりの類型とのあいだには連続的な相互移行の関係がある。こうした連続性を形づくりながら、これらの諸形態と普遍的な類型は、その形式であるところの(感性的―直感的な)空間時間性をあまねく満たしている。この開かれた無限性に属するすべての形態は、たとえ実在の世界においては事実として直観的に与えられるにしても、やはり『客観性』はもっていない。それは、すべての人にとって――それを実際に同時に見ていない他人にとっても――相互主観的に規定可能であったり、その規定性を伝達できたりするようなものではないのである。客観性を与え、相互主観的なものにするのに役立つのは、言うまでもなく測定術なのである。この測定術なるものは、多層的なはたらきからなっていて、本来の測定という行動は単にその最終的な部分をなすにすぎない。すなわち一方には、通常それを明確に規定する概念や名称の欠けている、川や山や建物などの立体的諸形態のための概念をつくるという仕事がある。まず最初は(形象的類似性の範囲内での)『形』、次にはその大きさや大きさの関係、さらにくわえて、熟知され、不動のものとして前提にされている場所や方向と関連させて距離や角度を測ることによっておこなわれる位置の規定、これらのものにその概念を与えるという仕事である。測定術は、なんらかの経験的な基本形態を、実際上普通に扱うことのできる経験的な意味での個体に固定させて、それを尺度として選び出し、それとほかの物体の形態とのあいだに存在する(あるいは発見される)関係によって、このほかの形態に、相互主観的な、また実用上一義的な規定を与えうるという可能性を、実用のなかで発見する。このことは、はじめは比較的狭い領域(たとえば、土地の測量術)においておこなわれるが、やがては新たな形態領域にもおよぼされる。以上のことから、『哲学的な』認識、すなわち世界の『真の』客観的な存在を規定する認識を自覚的に得ようと努力した結果、経験的な測定術とその経験的、実用的な客観化の機能とが、その実用的な関心を純粋に理論的関心に転化させることによって理念化され、純粋幾何学的な思考作用へと移っていった、ということが理解されよう。こうして測定術こそが、結局は普遍的なものとなる幾何学と、その純粋な極限形態の『世界』との開拓者になるのである」――E・フッサール、「ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学」はその第九節、「ガリレイによる自然の数学化 a〈純粋幾何学〉」(細谷恒夫・木田元訳)より。
後年、白痴とは知の欠如をいうのではなく、私たちの窺い知れぬもうひとつの知の在りようなのではないかと、私は思ったりもしました。私たちに果して知と呼べるほどのものがあるとするなら、私たちのそれを黒い知とし、彼らのそれは疒(だく)を外した白い知! とでも。
深い謂れがあってそんなことを思ったわけではありません。そうとされる彼らをほとほと観察するに、そのような感想を持ったまでのことでした。今にあっては、私は彼らに、しばしば彼らが見せる深い忘我の表情に、私のもうひとつのお手本を見たりもします。言痛(こちた)く申せば、反知性ではなく知のもうひとつの在るべき姿を、「非―知」の知を――自力では到底及ばぬ願いと知りながら、また、私風情が陳べるには余りに小賢しい言い草だと、重々、承知の上で。
では、私たちは何を病んでいるというのでしょうか、「黒い知」などとは。「知識は言葉の病い」と道破したのはメキシコの詩人オクタビオ・パスでした。その文言は確か、彼の「マルセル・デュシャン論」の中にあったはずです。ならば、そのパスの言葉尻を捉えて、病気とは欠如のなせる業というよりは往々にして過剰の形式なればこそ、私としては言葉をして「実存の病い」とすることもできるのでした。
☆☆☆
ジョルジュ・バタイユは「非―知」を以下のように定義付けています。
「死にうるために生きる、歓ぶことを苦しみ、苦しむことを歓ぶ、もはや何も言わないために語る。『非』とは、知らないことの情熱的受苦を目的とするーーないしはみずからの目的の否定とするーーある認識の媒介項である」。
更に続けて言います。
「その先ではもはや言うべきことが何もないという地点がある。その地点には遅かれ早かれ到達するのだが、そこに辿り着いたが最後、もはやわれわれは戯れにうつつを抜かしているわけにはいかなくなる」。
――(「非―知、閉じきる思考」西谷修訳、平凡社ライブラリー)より。
バタイユの言を、ここで殊更めかしくフォローする必要があるでしょうか。そんなことをすれば「もはや何も言わないために語る。『非』とは、知らないことの情熱的受苦を目的とする」に抵触しはしないでしょうか。「その先ではもはや言うべきことが何もないという地点がある」、その文言をこそ噛みしめよ、です。そこでは「もはやわれわれは戯れにうつつを抜かしているわけにはいかなくなる」、この「戯れ」こそ、まさしく私の言う「黒い知」によるエクリチュール、そのことであったのですから。
さてこそ、蛇足(と反復)を承知で書けば、オンツァマを巡る考察は夙に農夫の会話に尽きているのでした。
――オンツァマに計られたか。
――ああ、どうやら計られたようだ。
付記
「このへんの子供は、物見高いですね」と、その疎開画家が云った。「僕が写生をしていると、子供が十人も十五人も集まって来るんです。それもいいが、僕の耳もとで洟(はな)啜(すす)りあげるのは閉口です。あれは棒になって垂れさがる洟ですね」
「縄釣瓶のように、左と右と、かわりばんこに出たり引っ込んだりします」と、娘さんが云った。このへんでは、あんな洟を「蜂の子」と云っています。あんな子は丈夫に育ちます」
――井伏鱒二「乗合自動車」(「かきつばた・無心状」新潮文庫所収)より。
昔この里に一人の老翁があって、毎日山に行って枯枝を拾い集め、それを関の町へ持出して売るのを渡世にしていた。
ある日其薪が売れないので、町の中を流れる川の橋の上に休んでいたが、何と思つたが背の薪を取りおろして、竜神を念じつつそれを橋の下の淵に沈める。そうするとなんともいえないよい心持になった。
その時に水の中から、美しい上臈(じょうろう)が小さい、ほんとうに小さい一人の子を抱いて現れてきた。「爺よ、お前が正直で毎日よく働くのを、竜神はたいへんに喜んでおられ、その褒美にこの子供をお預けなされる。この方の名はハナタレ小僧様といい、お前の願い事はなんでもかなえて下さるが、ただ毎日三度づつエビナマスを供えることを忘れぬように」といって、美女は淵の底へ帰っていった。
爺は大喜びでそのハナタレ小僧様を抱いて帰り、それを神棚の側に座らせて、毎日海老(えび)の膾(なます)を上げることを忘れなかった。
それからというものは米でも金でも、どうかお授け下さいというたびに、ハナタレ小僧様がフンと鼻をかむ音をさせると、ほしいと思うだけ爺の前に現れた。もう山へ行くに及ばぬことになった。家も大きなきれいなのを出して下さいというと、たちまちフーンと音させて、驚くほどりっぱな家ができた。倉がいくつも建って米や宝で一ぱいになり、わずかな間に爺は長者になった。
爺の仕事は毎日町に下りていって、膾にする海老を買うことだけであったが、それがしまいにはめんどうになっいぇきて、ある日ハナタレ小僧様を神棚の側から下して、「もうあなたにはなにもお願いすることがありませんから、どうか竜宮へお帰り下さい。そうして竜宮様へよしくお伝え下さい」といった。そうすると小僧様は黙って家の外へ出ていった。しばらくして家の前でス―と鼻を吸う声が聞こえたかと思うと、たちまちりっぱな家も倉もなくなって、以前のとおりあばら屋だけが残った。爺はびっくりして、飛び出して見たが、もうどこにもハナタレ小僧様の姿は見えなかった。
――柳田国男「海神少童(はなたれ小僧様)」(「桃太郎の誕生」角川文庫所収)より。
(2019/6/25)
(2020/10/10 改稿・付記追加)
******次回は、7月5日の予定です******
HOME
|