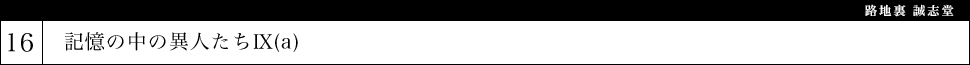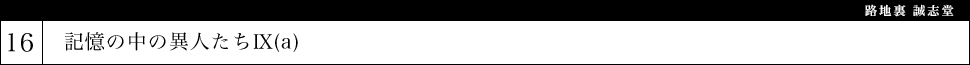写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
西郷信綱はその著、「古代人と夢」の書き出しの中で「昔を想い出すことが忘れていた今を思い出すことであるような、そういう思い出しかたがありそうな気がする」と陳べていて、何気ない物言いですが、その文意は中々に含蓄深いものです。少なくとも、私にはそう思われます。さなきだに、私はロートレアモン伯の「思い出はしばしば事実よりも苦しいものだ」の一行を知っています。思い出はしばしば事実よりも苦しいものでしょうか、私は村道を疾風のように往来する老婆のことを、ここで採り上げたいと思います。
時に、彼女は私の記憶の中をそれこそ一陣の野分のように過(よ)ぎります。「風の老婆」、私は記憶の中の彼女をそう名付けました。
〔風の老婆〕
麦藁帽子を目深に被り、老婆はその面を手拭いで覆っていました。頬被りというよりは、西洋のギャング式に口元を覆い隠しているのです。そして、深々と腰の折れた格好で、彼女は足音を潜め、足早に村の裏道を行き来するのでした。
子供たちは彼女に出喰わすと一瞬たじろぎ、呆然と見送ります。私は彼女が村の誰やらと挨拶を交したり、立ち止まっているところを見かけたことがありません。私が見知っている彼女の姿はどのような所用があってのことか、往来を飛ぶように行き来する姿だけです。子供ならずとも、その異様さの理由(わけ)は問わずには要られないものでした――なんで、なあ、なんで。
家人に拠れば、一廉の農家の出である彼女は、その若き日、近隣の村の名のある旧家へ嫁入り、その嫁ぎ先で口の大きさを詰られ、果ては離縁、以来、その口元を人目に曝さないのだと。果して、こんな説明が私を納得させたでしょうか。そんなことくらいでなぜこのようなことになるのか、子供心に訝しくも思い、それ以上を尋ねても家人は一様にそれ以上のことは分らないとしました。
確かに、色白、おちょぼ口が器量良しの必須の条件だった時代はありました。思えば、私の祖母などは自分の器量の話になると、私は色黒だし、おちょぼ口でもないと取りつく島もありませんでした。だから、その辺の事情は分別できるとしても、やはり私には根深く疑問が残りました。
それはそれとして、子供たちの間では、彼女の口は耳元まで裂けているというもっぱらの噂でした。しかし、そのようなことをまことしやかに言う子供はどこにだっているものですし、当の子供たちにだってどこまで信じていたかは定かではありません。大方の子供たちは話半分に聞いていたのではないでしょうか。が、それにしても、口裂け女の存在はいつの時代にもどこの土地にも登場するものです。そこにはどんな「集合的無意識」が、あるいはどんな「民俗社会の心性」が関与していたものか、中々に興味を惹く課題ではあります。
彼女の口元に如何なる真相が隠されていようとも、家人の言葉を額面通りに受け止めれば、その振る舞いの謂れは彼女の心の傷の裡にあったことには違いがありません。私は大口とは大食漢のことではなかったか、と穿った考えを持ったこともありました。実はそのようなことが充分、嫁として不適格の烙印を押されても致し方のない時代もあったのです。そんな嫁の戯画化された妖怪談だってこの国には結構あったはずです――(江馬務の「日本妖怪変化史」に見える「頭の後ろにも口が出来て食物を両方から摂取する」、いわゆる「二口女」などはその好例と言えないでしょうか)。
しかし、貧しい時代とはいえ、肥沃な米処の村です、その説は採れません。豊かな農家にあっては食のか細いひ弱な嫁より、よく食べ、よく働く、そんな嫁こそ貴重な労働力として何より期待されたことでしょうから。やはり嫁ぎ先で、不器量をいいことになんやかやと執拗に嫁いびりをされたのでしょうか、気が違(たが)えるほどに。
ここで余談。子供時代に祖母から聞いて、なにやら印象深く、今なお憶えている話があります。以下、その小話――嫁入りしたばかりの嫁に姑が訊ねました、「あなたは茶請けには何を好むか」。ここは滅多なことは言えないと、嫁は心して答えます。贅沢な茶菓子の類を慎重に避け、最も粗末なものとして、いつもの、しょっぱいだけの漬物の名を挙げたそうです。わが祖母が言うには、嫁の答えは姑を満足させませんでした。どころか、その答えによって、彼女は離縁されたと。な、なんと!
姑の言い分はそんな漬物のお茶請けでは切りがない、いつまでも、とめどなくお茶を飲む羽目になり、それではとても身上が持たないということでした。子供心に、これはかなりの悪意のある言い掛かりだと思いました。が、それはそれとして、このアネクドートになにほどかの語り継ぐ教えがあるとするなら、その真意は奈辺にあったのでしょうか。思うに、ここで問われていたのは奢侈や質素のことではなく、就労に差し障りなき茶請けは何であったか、だったのです。約言すれば、そこに問われていたのは「倹約」ではなく「勤勉」だった、それがこの話に対する私の現在の所感です。
話を戻します。
後年、ある筋から、彼女の遠戚に中る者からだったと思いますが、彼女の口はさほど大きいわけではなかったとの情報を得たことがあります。無論、口など裂けてはいません。それなら納得がいきます。大きいのは心の傷であったのです。そして、申すまでもなく、彼女は深い心の傷と共にその生涯を貫きました。
しかし、遥かに後年、私はとある一事に思い至って愕然としたことがあります。そのことが彼女の真実だったのかどうかはわかりません。ただ、私は自分の積年の蟠りが氷解する思いがしました。大きな口とは女性器、ヴァギナのことではなかったか? つまり大陰、鰐口。色事の世界にあっては余りに月並みなこのような揶揄も、日常生活においては反って見逃されがちなものです。果して「足入れ婚」というような習俗が未だ村に残っていた時代のこと、私の唱える説は充分にあり得ることです。家の大人たちの煮え切らない態度もこれで納得がいきます。いや、当の大人たちでさえ、そこまであからさまに思い至っていたわけではないのかもしれません。 要は婚姻に纏わる暗い話です、そこを突き詰めていけば自ずと性の周辺にその原因を求めざるを得ないのです。そのことを暗に感じていて、彼らは彼らで大人らしい賢明な判断停止を設けていたのではないのでしょうか――「庶民の結婚についても、だいたい久しく婿入り婚が一般的に続いてきているが、婿入り婚と嫁入り婚とのあいだの過度的な形が『足入れ婚』であった。足入れのことは戦後もしばしば世間の話題になって、それが一種の試験婚であり、嫁に対してすこぶる残酷な婚礼であるということをいうものが多い」(日本の民俗6和歌森太郎「女の一生」河出書房刊)。
老婆は決して口など裂けてはいませんでした。
では、なぜ、彼女は口を覆ったのでしょうか。
こんなことは何も深層心理学の用語を事々しく持ち出すこともないと思います。顔の口が大きいとされる方を彼女は望んだのです。だから、私は今の今、親たちの暗黙の掟を破り、それ以上に酷いことには彼女の心の奥底にまで土足で踏み込み、彼女の尊厳を心なくも踏み躙っていることになります。それを承知の上で、私は書いています。私の理解が正しければ(今の私にはそうだとしか思われないのですが)、大口に託けてそのような辱めがあったとするなら、若い女性にとってこれほどの侮辱はないはずです、傷ましいことです。至上の悦楽であるべきはずの性の営みがこれほどの残酷を生みます。
私たちの「性」はどこで、そして、どこまで拗れてしまったのでしょうか――「わたしが君たちに、君たちの官能を殺せと勧めるのではない。わたしが勧めるのは、官能の無邪気さだ」(「ツァラトゥストラ」手塚富雄訳)。ニーチェが言うおおどかな「官能の無邪気さ」などは、もはや、私たちに取り返すべくもないのでしょうか。
鎌鼬と云う現象があります。私の子供の頃によく取り沙汰された話です。何をしたというわけではないのですが、痛みもなく手足の皮肉が裂ける現象です。小さな旋風が惹き起す真空のなせる業だと説明されていました。私は「風の老婆」にこの鎌鼬を感じることがあります。彼女の精神的外傷(トラウマ)をそのように、つまり世界の真空なのだと説明したいのではありません。私にとっては老婆の実存がひとつの真空、彼女が世界の亀裂なのです。
彼女の記憶に触れる者は無痛の裡にもどんな傷を負うことになるのでしょうか。風の老婆よ、あなたは今なお、私を襲います。
******次回に(9月20日の予定)に続く******
HOME
|
|