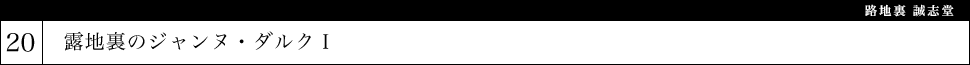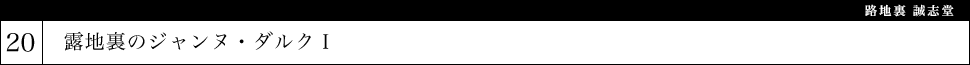写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
拙著「筑波の牛蒡」の「傷自慢」の項に、「近所でのことなら、かくれんぼやエス陣や石蹴りの数々、女の子なら鞠つきやゴム跳び、男の子同士なら、メンコやビー玉、ベーゴマと遊ぶアイテムにはこと欠かなかったわけですから、家にいる暇などはなかったのです。また、放課後の近所の路地裏での、年上の女の子や年下の男の子もいっしょになって夢中になった遊んだ思い出は、(中略)、ボルヘスの詩句(鼓直訳)の一部をエピローグに借りて、別に小説仕立てにして書いてみたい思いが私にありますので、その辺の事情をここで詳しく紹介することは遠慮したいと思います」とあります。
さて、という訳で、数年を閲した今ではありますが、私はその約束をここに果たしたいと思います。尚、「路地裏のジャンヌ・ダルク」は、このシリーズの当初にあった「田園のモービィデック」に対応した作であることは言うまでもありません。
☆☆☆
「露地裏のジャンヌ・ダルク」
狭い露地には、人を幸せに
するだけの空があり、
壁は暮色に染められていた。
――ボルヘス詩集から「扉のエレジー」(鼓直訳)より。
(Ⅰ)
そのかみ、私らの幼年時代、学校などの目立った場所では男の子は男の子同士、女の子は女の子だけで遊んだものだが、近所でのことならば男の子だって女の子と平気で遊んだりもした。但し、戸外の遊びに限ってのことだった。幼いとはいえ、まがりなりにも男の子、女の子とお部屋の中でいちゃついたりすることは御免蒙る。女の子たちは私たちを頻りに家の中へと誘い込みたがったが、私たちはそのことを潔しとしなかったのだ。それが村の男子たる者の暗黙の了解事項、少なくとも表だっては。だから裏腹に申せば、戸外で男の子たちと率先して遊ぶような女の子は相当のお転婆さんともいえたわけで、自他ともにそのことは認知されていて、そこでは性差などは思いのほか意識されなかったと思う。と、殊更に記すのも、子供に性差の意識がないなどとは大きな嘘で、子供ほどそのことに敏感なものもないからだ。
とまれ、年嵩の女餓鬼大将とも呼べそうな、男勝りの女の子は必ずご近所にひとりくらいはいるものだ。私の場合にもご多分に洩れない、そんな少女はいた。私の近くの大人たちは何かにつけ、彼女は「おとこおんな」だと軽い揶揄をこめて特別視したものだ。私ならこの思い出の中の少女を「路地裏のジャンヌ」と呼んでみたい。ジャンヌとは無論、ジャンヌ・ダルクのことだ。
そして、そのようなことを、私はこれから語ろうと思う。
朧な記憶の中でも、露地裏の私の「オルレアンの少女」は際立って色黒だった。色黒ではあったが、目鼻立ちには曖昧なところが微塵もなく、そのひとつひとつは実にしっかりと造られていた。のみならず、寸詰まりの上向き加減の太目の鼻や、めくれあがった口唇には独特の愛嬌があった。鼻と口唇が造る人中の窪みも見事ではあったが、めくれあがった厚めの口唇から覗くやや反り気味の歯並びは美しく、村の少女にあっては奇跡的なほどに清らかで、上から真っ直ぐ伸びた二本の門歯はどこか齧歯類の小動物を思わせた。彼女の口元の愛嬌は、実は時折り見せるそんな門歯を含む歯並びのせいだったかもしれない。しかし、その口は常に片頬に歪められていて、それが私には皮肉な表情と受け取られていたが、今にして思えばそれは彼女の笑みだったことに気付く。そうとでもしなければ、どうして私だけが彼女から「あのように」依怙贔屓されたのか理解ができない。なぜなら、私はいつもそのようにして彼女に凝視られていたからだ。そのことは追って語ろう。
目は吊り目勝ちで決して大きい方ではなかったが、有体に申せば東南アジア人によく見かける類いの、それはアーモンド型に属するものではあったろうか。しかも、黒い瞳は重たげな瞼の奥でいつもずる賢く煌めいていて、幾分、そこには斜視が含まれていたようにも思う。成人するに連れて、そのような斜視が気にもならない程度に治ってしまう事例を私は知っているが、それは少女期特有のものなのか、それとも個人差によるものなのか。さあれ、どうとあれ、私の思い出の中の少女の眼形が、年経るにしたがって愛嬌よりは下世話な気分が先に立つ、あの大きいだけが取り得の団栗眼でなかったことだけは幸いとして措く。なぜにとは問うまい。私は一重であれ二重であれ、眦の長く切れ上がった眼(まなこ)を何より美しく思うからだ。
とまれ、彼女の面立ちを語る最も特徴的な点を挙げれば、ひょろ長い首の上に乗った頭部は小振りではあったが、その張った頭蓋のお鉢と、つまり、おでこと目立って突き出た頬骨のことだ。前者は彼女を利発に見せ、後者は彼女に野卑な印象を齎した。更に言えば、不細工の汚名さえ着せたかもしれない。さなきだに、彼女の鰓骨(えら)は張っていた。要は、彼女は当時の美少女の条件からは著しく逸脱してはいたが、ある視点を採用するなら独特な魅力を持つ少女といえば言えなくもなかったのだ。曰く、蠱惑的!
色々と論ってはみたものの、総体に彼女の印象を伝えようとするなら、ラテン・アメリカはクリオーリョの少女を思い浮かべて欲しいと書くべきだろう。なぜなら、インディオの血を色濃く残す少女たちの映像の中で、主には都市部のスラムの少女たちの中に、私は当時の彼女の面影をありありと見出す時があるからだ。
さてこそ、その歳の頃や姿恰好のことなども語っておく。
小学校に入るやいなやの私たちからすれば、彼女は相当のお姉さんと思われたが、実際、もう中学生ではなかったか。とすれば、同世代の少女たちと較べてなんともはや子供染みた少女ではあったろうか。身体つきにもどこか子供っぽいところを残しており、決して矮小ではなかったし、その骨組みだって脆弱ではなかったが、如何せん、細すぎた。か細いと言ってもよかった。華奢だからといって貧弱なのではない。そのしなやかな身のこなしはゴージャスで、私はある種の野生動物の剽悍な身のこなしや佇まいを見るにつけ、そこに一種の豪奢を感じる。だからこんな修辞も許されたいーー今にして思えばあれは少年のものだった、稀にそのような少女はいる。
では、その人となりについて語ろうとすれば私に何ほどの材料があっただろう。ひとえに口数の少ない利かん気な少女、それだけかもしれない。その表情はいつも不機嫌そうだったが、だからといって陰気であったわけではない。
私たち幼い男の子は彼女を「黒姉え(クロネエ)」と呼んだ。これは女の子たちが口にしていた「黒姉ちゃん」の簡略形だ。別段、奇異なことではない。同じ年頃のお姉さんたちだって、親愛の情をもって彼女を「クロちゃん」と呼んだだろうし、近所のお兄さんたちだって、一種の畏敬をこめて「クロ」と呼び捨てにしていた。クロは本名であろうはずがなく、勿論、彼女の肌の色合いから来ている。
ここで彼女の常の髪型に触れておけば、豊かな黒い髪を無造作に伸ばし、それを癇症なほどにひっつめたポニー・テール、時にお下げだった。その上で、私は彼女が好んだ形(なり)などを説明してみる。
彼女は男の子ような半ズボン姿で村を闊歩した。そうでもなければだぶだぶのズボンの裾を捲りに捲って、小鹿のように引き締まった脹脛をもろに覗かせ、なるほど彼女の歩みはいつだって軽快そのもので、そこには肩で風切る風情さえあった。私の見るところ、両の手をポケットに突っ込み、口笛さえ吹き兼ねまじい中々のお兄哥さん振りだったが、彼女のズボンの腰周りでは、その腰は細すぎるほど細かったので、まるで巾着の首を紐で結わえでもしたかのように、粗末なベルトがズボンの胴周りを締め上げていた。その上には男もののよれよれのカントリー・シャツ、それがお決まりの彼女のスタイルだった。尚のこと、暑い季節にはそんなシャツも脱ぎ捨てられ、私たち男の子同様に、その上半身は肩きり(ランニング・シャツ)と呼んだ下着姿で通したものだ。
しかし、そうと見えたのは子供の早とちりか、あれは所謂、婦人用下着、シュミーズではなかったか。当時の女の子はそんなものを身に着けていたものだ。だから、私にそうと見えていたのはノー・スリーブのシュミーズの上半身。すると彼女は家の中ではそのようなものだけで歩き回り、外へ出る際、その上からそそくさとズボンを穿く、あり得ることだ。ここで周章てて付言を致すと、少女用のシュミーズはレースなどで縁取られてはいない。また、そんなもので縁取られてはいけない。因みに、子供の私の目にする大人のそれらはいつだってしどけなく着られていて、その胸元や裾にはたっぷりとレースの縁飾りが施されている。それらは決って粗笨なものだったから、なにかとほつれ易い上に、いつもどことなくくすんで見え、つまり薄汚れた感じがして、子供の私には目を背けたくなるほどおぞましいものだった。よしんばそれが母の姿だったとしても、だ。元来、私は装飾過多の少女のコスチュームを好まないが(リボンは好ましいがフリルは苦手だ)、ここは更な木綿の布地を型通りに裁断したままがよいのだ。それ以上は少女に不要の飾り。そのことは私が言うのではない。私の嗜好もそこにはあるが、私の中の黒姉えがそう語るのだ。
とまれ、シュミーズであれ、肩きりシャツであれ、彼女の深く抉れた襟刳りには左右の鎖骨が危ういほど露わに見えており、かたや、あけっぴろげの黒姉えの腋窩は鋭利に削げて、その腋の下からはアズキ豆ほどの乳首が覗いた。しかし、そこはあくまで「少年」のままであったので、彼女は固より私たちもさほどには気にも掛けなかった。寒さの季節に到れば、黒姉えは厚手のシャツや手編みのセーターを何枚でも重ねて済ました。だからといって、冬の彼女になぜか着膨れた印象を持たない。得な体形だ。私は着膨れに着膨れた幼女を愛くるしく見るが、着膨れた少女は御免蒙る。その癖、豊頬の美少女は好む。妙な話ではある――閑話休題。
彼女の衣服の大方は、お兄さんたちからのお下がりもので賄われたはずだ。黒姉えはその身の上に歳の離れた三人の兄を持っていたから、供給源にこと欠くことはなかったといえる。家人はこれは助かると思っていたかは私の関知するところではないが、彼女の好きに任せていたことは否めない。その姿は村でも異彩を放っていたらしく、口さがない村人の口の端にしばしば上った、ほんとにかまわない家なのだから。しかし、そんなことは私と黒姉えに言わせれば余計なお世話だし、余計なお世話ではあったろう。
黒姉えのお家のことだ。
彼女の家はバス通りでもある村のメーン・ストリート(!)から随分と引っ込んだ位置にあり、長い露地が彼女の家と本通りとを結んでいた。露地の門口には、稀には娼家を兼たかもしれない村唯一のお茶屋があり、お茶屋は間口の狭さの割には縦長の敷地を持ち、もう一方が元は地主であられた長大なお屋敷だった。そういうわけで、露地の片側では「粋な黒塀」が露地の半ばまで続き、その反対側はそのかみは庄屋も務めたという地主様の、手入れの行き届いた丈の高い槇の垣根が長々と続いている。私たちはそんな生垣を古い言葉でクネと呼んだが(江戸後期の風俗百科とも呼ぶべき「嬉遊笑覧」には「垣をクネといふはくべ也」とある)――そして、茶屋の背後は狭いなりに空き地になっていた。だから、露地はその中頃で大蛇(おろち)が獲物を呑んだように膨らみ、私たちに手頃な広場を提供した。そして、再び窄んで、二、三の農家へと解消する。
果して、その農家の一軒が黒姉えの家だったが、もう、その向うは見遥かすばかりの田園なのだ。とりも直さず、その一帯は村を貫通する一本の主要道路より低まり、梅雨とはいわで淫雨(ながあめ)の時などはなんともじめじめした沮洳地と化した。実際、黒姉えの家の前には浅く小振りな溜め池さえあり、雨の日の露地を洗う流水を受け止める。受け止められた雨水は私たちがミヨと呼ぶか細い掘を通して水田に導びかれる。そして、池には常に数羽の家鴨が放し飼いにされていて、その水面は平地には珍しい山毛欅(ぶな)の木の鬱蒼たる樹枝に覆われていた。
(2019/12/1)
****** 次回に続く ******
HOME
|
|