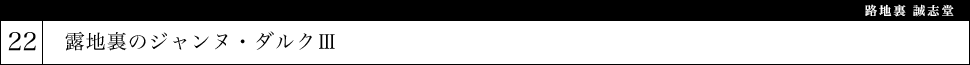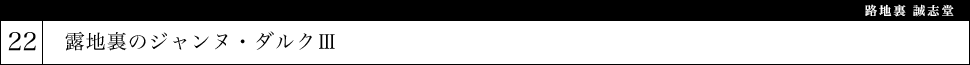写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
(Ⅲ)
これは、土の広場に
大きな影を落としていた、長方形の
扉のエレジーである。
これは、黄昏が空き地に
投げかけていた、長く弱々しい
光を偲ぶエレジーである。
(狭い露地には、人を幸せに
するだけの空があり、
壁は暮色に染められていた)。
これは、頼りない記憶の線で描かれ、
忘却という小さな死の中に消える
パレルモのエレジーである。
…
――(J・ボルヘス、「扉のエレジー」より)。
遊びにはひとり遊びに始まり、二人きりで遊ぶ遊びもあり、その一方で、全員参加で楽しむ遊びがある。その中でも二手に別れてその輸贏、つまり勝チ負ケを競う遊びがあって、そのことはエス陣やトッカンで語ったわけだが、では、そこでは子供たちはどのように組分けされたのだろうか。以下、そのことを語ってみたい。
遊びに参周した子供たちの選別に中っては、好き嫌いよりもその前提となる個々人の身体能力が優先されたようにも思う。まずはシードされる年長者を軸に、幼少のもの、性を異にする者、非力な者、それぞれのハンディキャップを考慮し、双方のチーム能力の公平が期される。そりゃあね、子供のことだ、あの人のいる方に私は入りたいの、そんなわがままがひとつや二つはあったかもしれないが、わかった、わかった、お兄さんやお姉さんたちがそこはよきに計らい、概ね、参加者の誰もが納得できる人員の配分がなされた。としても、そんな際、幼少の者たちに最も人気を博するのが黒姉えだ。なぜかとは問うまい。彼女は既述した通り、決して大柄の身ではなかったが、その身体能力には恐るべきものがあった。その具体的な例のひとつばかりを挙げれば、黒姉えはその小学校時代、運動会の徒競走では常に一学年上の然るべき者たちと競い合った。つまり、その足の速さが同学年の児童たちとは雲泥の差があったということで、それは先生方の苦肉の策ではあったのだ。それでも尚、彼女はぶっちぎりで勝利した。その逸話はしばしば私たちも耳にもしたが、その能力が普段の遊びの場に於いても発揮されないことはあり得ない。そして、発揮された。だから、件の逸話は愈々その信憑性を高め、私たちの間で囁かれ続けるのだった。つまり、伝説化してはいたのだ。
彼女はどんな集団遊戯に於いても常に勝利の女神なのだ。そして、私は強いてそのことを望まなかったけれど、なぜか黒姉えの側、即ち、彼女のチームにいつも組み込まれているのだった。そこに何ほどかの配慮が働いていると、薄々とは感じていたかもしれないが、それが決定的にそうなのかと思わせたのは、黒姉えに纏わりついては何かと彼女を煩わせている女の子の、なんとも下卑た一言からだった。その子は子供の目にもいやにオンナオンナしていて、その頃の私のもの言いでいえば、ナヨナヨしていてメソメソしている。その上、滅法、小理屈にも長けていて、要するにムズカシクテ――私は家人の誰某かの口真似で、当時、このような言い回しをものにしていた。そして、何かといえばそのフレーズを口にし、近在の大人たちの笑いを買っていた。大人たちは予め笑いを含んだ口調で私に問う、むずかしいの? 私はご期待に背かずに答える、うん、あの子はむずかしくて。つまり、彼女は私が最も苦手とするタイプの女の子だった。
偶々のこと、私は遊び場に遅れて着いたものだ。ちょうどその時、その日のゲームが始まらんとしていて、とても間が悪く、スエテ(容れて)などとは自ら言い出すことも憚れて、幼いなりに私は戸惑いの色を隠せなかったことがある。すると、黒姉えはさも面倒臭げに私の手を曳き、有無をいわさなかった、強引ともいえる遣り方で自分の側に容れてしまった。その子はまさにその時だ。絶妙のタイミングで、彼女はその時の時を狙っていたのだ、彼女の「黒姉ちゃん」を横目に窺いながら、擦れ違いざまに私の耳元で囁いたものだ。マーメッチョ!
私は己が耳を疑った。なんだって、マーメッチョ? 私は私を尻目に立ち去る彼女を、只々、目で追うばかり。呆れて口も利けなかったのだ。
どだい、このような言葉は女の子から出てくる質のものではない。というのも、それは当時の私たちの囃し言葉のひとつ、それも性に纏わる極めて卑猥な部類の一節なのだ。有体にその上の句を紹介してみよう。男の子と女の子とが睦まじく二人きりで遊んでいようものなら、私たち男の子は多分にヤッカミ半分で、中には心の底からの憎悪を露わに示して、以下のように囃し立てたものだ。「男ト女デ、マーメッチョ、マーメ喰イ喰イ、何ヤッタァ」。私には子供心にもこの「マーメ」が妖しかった。なぜ、よりによって豆なのか。なんでそんなものを食べながら何をすると云うのだ、そこには曰く言い難い謂れがありそうだ…。
後年、このマメが女性器の陰核を意味するなどとは容易く知り得ることとなるが、どうしてどうして、その程度の解釈では私は意に満たず、そこにはマメマメしい、勤勉である、が含意されているだろうと踏んでいたところ、果たせるかな、その手の本に拠れば男陰の俗称としての「まめやかもの」があり、そのことに「達者」の義を挙げていた。幾つになってもマメなことよ、達者なものだ。まあ、男女を問わず、相身互い、この件に関する限り人はそのようなものなのだろう。さてこそ、余りにもアケスケなその下の句のことだった。果して紹介するほどのことがあろうかと自省もされたが、書き記して措く。「マーメ喰イ喰イ、エロ、ヤッタァ」! この囃し言葉の効果は抜群で、そんな上の句と下の句を妙な節回しで、
――男ト女デ、マーメッチョ、マーメ喰イ喰イ、何ヤッタァ!
――マーメ喰イ喰イ、エロ、ヤッタァ!
交互に、執拗に、繰り返されでもしたら、どんな男の子だってそそくさとその場を離れ、女の子の方は大体が泣き出してしまう。因みにここでの「エロ」とはエロチシズムのエロではない。「色」のことだ。私たちが生れた地域では「イ」と「エ」がとかくに曖昧で、色鉛筆が「エロ・インピツ」に転訛する。また、ツクイ(机)とエス(椅子)などとも取り違う。
そうだ、私たちがよく口にした卑猥な囃し言葉と言えば、この「マーメッチョ」と双璧をなすものがもうひとつあった、どうしたものか。ものはついでだ、書き残して措こう――これは単純な罵倒のフレーズで、喧嘩別れした相手に向って声の限りにかく叫ぶのだ。「オ前ノ母チャン、出ェべェソォ。出臍ノ下ニハ何ガ有ルゥ」! さて、その下の句は「…出臍ノ下ニハ、大×××!」である。×××の単語はご想像にお任せする。
とまれ、私と黒姉えは歳も離れている。その上、私たちはいつだって皆と一緒、常にオープンで明朗そのものじゃないか。あんたなんかに後ろ指を指される筋合いはどこにもない。それに誰があんな黒姉えと、私にとってこれほど意想外な言葉はなかったのだ。だから、彼女は血迷ったのだ。黒姉えを慕う余りの言い掛り、私は等閑視を決め込んだが、ふと、黒姉えは私を贔屓にしている! 卒然とそんな疑念が私の脳裡をよぎった。そのことは、私に並々ならぬショックを与えた。まさかとも思われたが、そうと言われてしまえば思い中る節がないでもなかったから。
黒姉えは戸外の遊びだったら、なんでもこなし、当時、女の子の遊びとされたゴム跳びも毬突きも、はたまた、そこに多彩な遊びようを誇った石蹴りなどもお手のものだった。ただし、ままごとなどはもっての外、お手玉やお弾きなどには目もくれなかった。が、ままごとは論外だとしても、お手玉やお弾きはやればやったで彼女のことだ、なんなくこなしただろう。どんな加減からか、私はそんな場面に出喰わしたことがあるが、近在のお姉さんたちが幼い者と縁側に屯し、それらの類いで遊んでいると、通り掛かった黒姉えがひょいと横から手慰みでするそれらは、舌を巻くほど巧みなものだった。でも、目を丸めた幼い女の子たちがそれ以上をおねだりしても、彼女は口を歪めて二度とは手を出さない。縁側に上がり込んだりはしないまでも、そんなところに場違いにも! 馬鹿面を晒して侍っている私を眇に見遣り、ぷいと立ち去った。
私は羞じた。羞じてはその場を後にするが、でもね、黒姉えだって女の子、並みの男の子だったら決して振り向きもしない綾取りなどは嗜むのだ。私は知っている、山毛欅(ぶな)の木のいつもの場所で無聊を託つ時など、彼女は幹にその身を預け、無心に「ひとり綾取り」に興じている姿を度々目にもしていたから。と同時に、私は当時の女の子がそれぞれの彩りの、それぞれの綾取り用の毛糸をネックレースのように首に掛けていた姿を思い出す。そんな毛糸のネックレスはちょっかいの種にこそなれ、私たち男の子にはなんの意味もなさなかったにしろ、ある情趣とともに今や老いた私の目にも浮かぶのだ。
さて、ここに留意のひとつもあるとするなら、黒姉えは男の子の好む勝負事などにはいっかな興味を示さなかった。メンコやビー玉やベーゴマ(貝独楽)の類いのことだ。このことは当時の彼女のような存在を理解する上では一考に値することかもしれない。が、私はペンを進める。
彼女は子供たちの遊びの中心人物だった。そのことは既に語ったが、しかし、黒姉えのより好んだ遊びは「トッカン」や「エスケン」、(「ドコユキ」に関して言えばさほどには好まなかった、そんな印象を私は持つ)、その他各種の鬼ごっこ、中でもかくれんぼの一種である「缶蹴り」、冬ともなれば女の子も男の子と混じってよくした「押しくら饅頭」や、とりわけ好んだ大波小波やお入んなさいの「縄跳び」などは申すまでもなく、男の子が専らとするブタンマ(豚馬)と私たちが称した「馬乗り」さえも。彼女はそれらを率先して主宰した。その際、黒姉えは男の子も女の子も、はたまたどんなハンディキャップを背負った子も、そこには彼女なりの実践的な配慮はなされていただろうけれども、一切、区別も差別もしなかった。彼女は幼い子供たちを率いて遊ぶことを好んだことには違いがないが、むしろ、近在の子供たちが性差を問わず、年の差も忘れ、彼女を必要としたのだともいえる。もう、そんな際での彼女の異能ぶりをここで詳らかにすることもなかろう。今更、想像に難くないことだ。いざともなれば、黒姉えには不可能なことなどなきが如しだった。
その一例を既に詳述した「トッカン」に採れば、彼女はプレー開始からその最終まで一度足りとも自陣に戻らずに延命することも可能だったろうし、なぜなら、黒姉えに触れることなどどんな子供にも不可能と思われたから。年嵩の少年たちにあってさえ、彼女に言わせればそうは問屋は卸さない、黒姉えを捕えることなど至難の業だ。だから、敵を出し抜き、味方の捕虜救済などは彼女にとってはお手のものであったが、そして、私はしばしば彼女の恩恵に与ったことはいうまでもない。どころか、私の危機一髪の際、その身を犠牲にしてまで、私を助けてくれたことは一度や二度ではなかったのだ。ああ、それなのに、あの子にあんなことを耳こすりされるまで、その程度のことに私は気付きさえもしなかったのだ。黒姉えにあってはそんなことは当たり前なことではないか。その身を犠牲にしてまでの救済にさえ、私は当然なこととして意にも介さなかったのだ。
しかし、「トッカン」に於いてかほどに万能の力を示した彼女であっても、その勝利を約束するバンザーイ! のタッチは容易にしなかった。その辺りが黒姉えの面白いところだ。今にして思えば、彼女も亦、勝チ負ケに拘泥って私たちと遊んでいたわけではなかったのだ。
黒いラ・ピュセル!
私たちの乙女よ。
黒姉え、私のラ・ピュセル!
私の乙女よ。
(2019/12/15)
****** 次回に続く (12月22
日の予定)******
HOME
|

1485頃に描かれた
ジャンヌ・ダルク

ゲームのキャラになった
ジャンヌ・ダルク(2018)
|