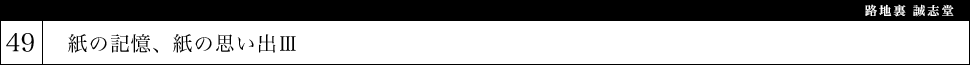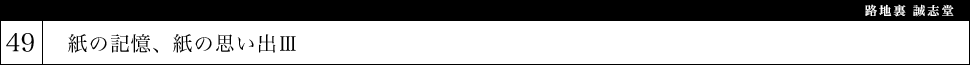ここで確認をしておきます。
私は出来得れば紙そのものを、少なくてもその周辺を忖度したいのであって、そのようなつもりでペンを進めてきたのでしたが、だから、日光写真のネガ紙やポジ紙、塗り絵や写し絵、はたまたそのものずばりのメンコなどの「玩具になった紙」の思い出をここで語りたいのではありません。そんなことに一旦手を染めたら、その数限りないアイテムに収拾が付かなることは目に見えていますから。
あっ、でもね、周章ててひとつだけ特筆しておきたいものがありました。なにやらの紙片を甘く味付けした駄菓子があって、私たちはそのシートになった紙片を5円程で購い、ちぎりちぎりしてはしゃぶるのでしたが、あれはなんであったのでしょう。今にして思えば、随分と怪しげな代物があったものですが、さすがに隔世の感を持ちますね。ふと、思い出したので「紙の思い出」のひとつとして記しておきます。得体の知れない紙片をしゃぶっては、口からペッぺッとしゃぶりカスを吐(ほ)き出している田舎の子らのプリミティヴな姿が、どうにも捨てがたい景色と思われましたので、そうは思われませんか。
それにしても、あんなに子供の口唇愛におもねた駄菓子もなかったかもしれない、なんて感心します。
もとい、また、教室でみんなで作る七夕さまの色紙の笹飾り(町場育ちの若い女先生の妙技の数々に、私たち村の子どもたちは目を瞠りました)や、村祭りに際しての、白と桃色のちり紙で作られる花飾りのこと(集会所に隣接した村唯一の西洋館のご令嬢、歯科医院の「いい言葉」を使う美人姉妹のお手を煩わせ作って頂きました)や、ともかく、そのようなアネクドートを殊更に語りたいわけでもありません。
更には、今思えばどこか小児性愛者(ペドフィリア)めいた置き薬の薬屋さんが座敷の上がり框でお見世を開いては、そんな時には必ずそこに侍っていた私たちにプレゼントされた四角い紙風船に纏わる怪しからん話(彼は私を女の子と誤認していて、景品を餌に何かと体の一部を触りたがるのでした)や、F・ラブレー的にアレンジされた紙の思い出(では、君はあの模型ヒコー機の翼の紙めいた紙でお尻を拭いてみたいとは思わなかったのか)などを語ってみたい気もしますが、しません。
そのような種々については、いずれ、語る機会もあるだろうというわけですが、ただ、この小稿を収束するに中って、私は牛乳瓶の丸蓋については触れておきたくなりました。
「牛乳瓶の蓋」
当時、私たちに給食のシステムはありませんでしたが、昼食時に、180CCの瓶での牛乳のサービスがありました。私たちは食後の気晴らしに、牛乳瓶の丸蓋を拇指と人差し指に挟んで、押し出すようにピュッと飛ばして遊びましたが、そんな戯れに目もくれないで紙の小円盤を小まめに集めていた色白の男の子の思い出です。とても勉強のできる子で、村の子どもとは違い、いつも小奇麗な身なりをしていて、そうそう、左ぎっちょだったことも憶えています。
彼は父母と遠く離れて(そこにはどんな事情があったのか、それはまた別なお話です)、母の故郷である私の村で祖母と暮らしていました。ちなみに、彼の両親は西の日本を代表する大都市である0市に在住していると聞いていましたが、その遠さは私たちの想像の埒外でした。
私は牛乳瓶の紙の蓋など蒐めたりはしませんでしたが、メンコ(私たちはパーと呼びました。私はこれをペーパーの約まった形ではないかと思っていますが、どうでしょう)やビー玉(ラムネと言いました、正確には訛ってランモネです。ビー玉はビードロ玉ですね)やベーゴマ(これは貝、ベイの独楽です)を、村の子どもたちのご多分に漏れず貯め込んだりはしていました。でもね、彼の牛乳瓶の蓋の蒐集は、私たちのそれらとは趣を異にする、損得を離れた、なにやら気が利いた感じが致しました。
そんなわけで、私はその子の色々なコレクションを見せて貰いに、季節は初夏、日曜日の昼下がり、彼の祖母の家を訪ねたことがあります。彼が祖母と起居を共にしている住まいは、旧家の大きな屋敷林の中にある、母屋とは違う離れ風のところでした。
私が約束通り現れると、彼は私を屋敷林の木漏れ日が当たる縁側に導き、そこで色々なコレクションを開陳しました。彼も私の訪問が嬉しかったのでしょう、いそいそと次から次と、彼の宝物を惜しげもなく見せてくれました。そこにはフィルムの切れ端や色ガラスの破片、もの珍しい鉱石、田舎の少年ではとても入手が見込みそうもないバッジの数々や、なにやらコーティングされた光沢を持つ紙のワッペン、外国の切手(三角の切手!)など、どれもこれもが私の得心のいくものばかりです。私はそんな蒐集の世界があることに驚き、度肝を抜かれ、内心、私のそれまでの人生観が一変するほどの、今の言葉で言えばカルチャー・ショックを受けたのでした。
やがて、円形で大振りのブリキの缶に、それらとは別個に牛乳瓶の蓋が収まってい、おもむろに開陳されました。けっこう多彩なメーカーのものが取り揃えてあり、並べてみると、その多岐にわたるデザインの面白さに目を奪われ、あの牛乳瓶の蓋がねえ! 私はあんなものでもこうして蒐めて見れば、なにほどかのものになっている事態に吃驚りしているのでした。 ほほう、なるほどねえ、ほほう、私は骨董を前にしたオヤジのような嘆息を挙げていました、そのことを、われながら可笑しく思い出します。
総じてそれらは清潔にしてありましたが、手に取ると一枚一枚、仄かに乳の匂いが残っていました。そして、やはり、そこにも防水加工の蝋めいた艶やかさが見て取れないこともありませんでした。
小学校入学時から一緒だった彼は、5年生になる前に両親の住まうО市に戻りました。以来、彼とは再会することがありませんでした。
さてここで、蛇足めきますが紙ではない紙の話の記憶二、三付け加えて、私としてはこの私の「紙の記憶、紙の思い出」を切り上げようかと思います。一つは紙のように薄い紙石鹸のお話。そして、もう一つは隠喩としての紙、ジャンケンの紙を巡る駄弁です。
紙石鹸についてはあの使用中の寄る辺なさについて、一言あっても然るべきだと思えたのです。
「紙石鹸の話」
建前はどうであれ、駄菓子屋で売られていた紙石鹸はあくまで「ごっこ」としての石鹸なのであって、手を洗うためにというよりは、掌の中で泡立ち、みるみる消滅していく、その様を愉しむところに、その本領があったのだと思われます。
もとより、衛生観念の希薄な私などは自らそんなものを買い求めたりはしませんでしたが、校舎の傍らの洗い場で、同級生のお澄まし屋さんの少女がある条件のもとに、その一枚を惜しむように分け与えてくれたことがありました。その条件とは手をキレイにしたら、と言うのです。そんな汚い手をした子に、こんな奇麗なものを、何故あげられましょうか、というわけです。
私の手はいつもお猿さんのようでしたから、つまり、余りに手が汚いと石鹸は泡立ち難く、だから、彼女の言い分も尤もだと思い、私はしぶしぶ、水でじゃぶじゃぶ手を洗う仕儀と相成りました。その上で、初めて私は紙石鹸の恩恵に与るのです。
お約束通り、洗い立ての私の掌の上に半透明の薄く奇麗なものは載りました。それを合掌した形に挟みクチュクチュやると、掌の中が泡立ってきます。たびたびその存在を確かめながら、両の手をすり合わせていると、紙のような石鹸はもう、桜の花弁ほどになっていて、気が付くといつしか消えているのでした。
その儚さはいかばかりだったでしょうか。なんだか肩透かしをされたような不如意な感覚を持て余し、私は照れ隠しに、件の少女に悪態のひとつもついて、なんだ、つまらない、その場から駆け去るのでしたが、駆け去りながらも、両の掌の、今や非在の紙石鹸の残り香を交互に嗅いでみたりもするのでした。
ああ、そうでした。こんな思い出なら、まだありました。
私は癇の強い子でしたから、と祖母などは申しました、小粒な楕円のドロップとかはいわでものこと、硬くて大きな真ん丸の飴玉などもついつい噛んでしまい、その最後まで舐めきることなどは滅多にありませんでした。それでも、何かの加減でそんな場合もあったりして、しゃぶっていると、それらは舌と口蓋の狭間で淡淡と溶け、やがては消えてゆくのですが、まさに消えなんとする際のその刹那の感覚は、私をして一瞬途方に暮れさせました。
そんな私に託けて書き募ると、その頃、近所の顔見知りの幼女は飴玉はもとよりドロップなども必ず嘗めきるタイプで、というより、幼すぎて噛めやしなかったのだろうとも考えられますが、コンタクトレンズのようになった寸前のそれを、桃色の舌の先っちょに載せて、チロりリと舌を出しては見せびらかしたりしました。見せびらかしては再び口に含み、幼女は惜しみ惜しみ神妙な面持ちで残りのドロップをしゃぶります。当時、私はそんな彼女を眇めで見て相手にもしませんでしたが、幼女の一連の奇矯な振る舞いは妙に印象に残っています。
彼女はドロップや飴玉を嘗めきったと思われる頃、何かに問いかけるような面妖な表情を必ず作りました。眉を顰め、黒飴のような黒目を鼻のつけ根に思い切り寄せ、しかる後、照れ臭そうに破顔し、ない、ないと舌鼓を二度ほど打つと、両の手をばたつかせ、不意と踵(きびす)を返し、たどたどしくスキップを踏んでは私の元を掛け去るのでした。あの子も多分、あの刹那の喪失感を享受していたのだと、今の私には思われますが、どうでしょう。
実は以上を認めた後、ヌキ(抜き?)という飴の駄菓子があったことを、卒然と思い出しました。切手大の板状の飴になにやらの像が刻印されていて、嘗めながらその刻印(花や小動物の類いでしたか)の形を抜くのですが、破損することもなく上手にヌいては駄菓子屋の店主に提示すると、その判定に従い、大・中・少のべっ甲飴の景品が貰える、確かそのようなことだったと思います。
性分的にこの手のものは、私の得手でなかったと思いますが、口に含んだ際、その飴の小片はニッキで味付けされていて、舌先にピリリとした刺激があったと、味の記憶が蘇えりました。以上、怪しいところもありますが、子どもの口唇愛と射幸心におもねた懐かしい駄菓子の思い出ではありました。
さて、じゃん拳の与太話です。
それを習い覚えた頃、私はじゃん拳の紙がどうして石に勝つことになるのか、いくら説明を受けても、子ども心に得心がいきませんでした。鋏が紙に勝ち、石が鋏に勝つほど、その理由が明解とは思えなかったのです。石を包むことがなぜ紙の勝ちになるのか、おっしゃる意味が分からないではありませんが、牽強すぎはしまいか。後々、そんな勝ち方もあるのだろうと納得させてみましたが、長い間、私は腑におちませんでした。
しかし、今にして思えばなんとも他愛ない話で、私の不信のありどころは、紙対石の勝負には石対鋏、鋏対紙に較べてバイオレンスが欠けていたまでのことでした。紙が石を包む、平和的手段の裡に、勝負事が決すこともあってもよかったのです。
☆☆☆
私にとって紙の魅力とはなんだったのでしょうか。そのことは既に述べたと思います、それは紙の紙たる所以である薄さにあると。では薄さとはなんでしょう。ある儚さです。儚さ以外どんな内実もそこに持たないことです。だから、色や柄にではなく、モノそのものとしての紙の美しさがあるとすれば、曰く「白痴美」! しかし、物質の美しさとはおしなべてそのようなものではないでしょうか。美しい子どもが美しいように美しい。
紙、内実などという曖昧で恣意的な概念に頼らず、常に一枚の表層としてそこに留まること、その努力(無償の困難への愛!)のひとつの形式。それはどこか鏡の在りように似てはいないでしょうか。鏡の内実など誰が想像できるでしょう。鏡の内実とは表層そのもののことです。
鏡とは一枚のガラス板と水銀箔だと言ったところで、それは要素に還元したまでであって、鏡ではありません。しかも、私たちは鏡自体を見ることは不能、出来ない相談なのです。鏡自体を目の当たりにすることは、私たちに許されていません。なぜなら、鏡は常に何かを反映してしまうから!
さてこそ、私はモノを巡る私たちの思いもそんなことかもしれないと思い中るのでした。どんなにモノを叙してみたところで、それらはモノに映る自分を語っているに過ぎないのです。そうではなかったでしょうか。
かくして、私はこの小稿のペンを擱きましょう。と同時に、長かった「子どもの領分」も、この「紙の思い出、紙の記憶」を以って、ひとまずの了としたいと思います。
※※※※※
「あと書きにかえて」
私は庭の柿の木の下にいます。近所の遊び仲間の子らが三、四人、私を取り囲んでいます。柿の実がようやく色付き始めていましたから、初秋の頃だったでしょうか。早い秋の木漏れ日を浴びながら、私は遊び仲間に向かって、なにやら力説しています。その内容は以下のようなことでした。私は生まれてこの方、今までのことで忘れたことはなにひとつない、そう言い募っているのです。私たちは未就学児童でしたから、3、4歳、いやいや4、5歳の頃のことだったでしょう。では、なぜ、そのような発言が私にあったのでしょうか。
ある出来事(その件がなんであったかは今となっては不明)が、果たしてあったのか、なかったのか、その記憶の真贋について、私と彼らは言い争っているのでした。私以外の子らはそんなことはなかったと言います。そんなバカな、けっこうな昔(私たちにも昔はあったのです!)のことなので、みんなはすっかり忘れている、私はこんなによく憶えているのに、その落差に焦れて、その揚げ句の発言が「生まれてこの方、なにひとつ忘れたことはない」になったのでした。
私はここで、三島由紀夫の「仮面の告白」で有名な、あの「産湯の盥の縁に耀う陽の光」の類いの記憶を申しているわけではありません。ただ、その時の私の心情としては、それまでに起こった出来事を、私はよく憶えているということなのでした。ましてや彼らと共有してる過去の事なら、私にはその一つひとつをありありと思い出せることができるし、なんで忘れることがあり得ましょう、という思いだったのです。
では、その過去はいつまでかとなって、生まれて以来の強弁になったのでした。が、みんなは勿論、そんなことあり得ない、嘘だということなったのでした。
そこで、私の次なる発言がありました。嘘じゃない、だったら、その私の記憶力の証に、今ここでこう君たちに述べたことを、私はいつまでも憶えていると宣言したのでした。あなたたちがよもや忘れても、私は死ぬまでこの「宣言」を忘れないだろう! 私の遊び友だちは呆れた顔で、私を眺めていましたっけ。
思えば、あの日からもう七〇年近くを閲したわけですね。もちろん、私はその発言は憶えていますし、その時の私の口吻、遊び友だちの一人ひとりの反応、その一々を今の今、とてもくっきりと思い出すことができます。思い起こせば何事も一瞬間の出来事ですね、まさに「地上とは思い出ならずや」(イナガキ・タルホ)です。
ということで、以上の極めて子ども染みたアネクドートを記し、以って、私は私の思い出の記「子どもの領分」のあと書きとしましょう。
付記(エピローグ)
F・アリエスによれば、私たちは17世紀に「子どもの無垢性」を発見します。その1世紀後には「子供の無垢というこの観念は人びとに共有されるもの」となるでしょう。
これが無垢の年代
地上の我らの希望となる
未来の幸を楽しむために
誰もが皆、立ち戻らなければならぬところ。
全てが許される年代、
憎しむことも無く、
悲しみとて無い年代。
人生の黄金の年代、
悪魔もものともしない年代、
生の苦しみも少なく
死の恐れも少ない年代、
天も開かれている年代。
教会の若き笛に
やさしく柔らかな心を。
そをおとしむる者は皆
天の怒りに触れるなり。
「F・ゲラールの版画の題辞」よりーー(フィリップ・アリエス著「子どもの誕生」杉山光信・杉山恵美子訳、みすず書房刊)。
(2020/11/1)
HOME
前回へ
|