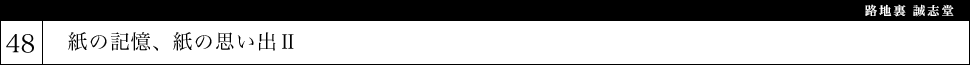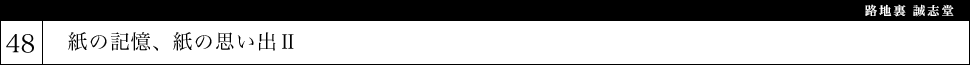写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
「紙の思い出、紙の記憶」
私は習字の課業が嫌いでしたが、習字紙も嫌いでした。薄いといってもあの薄さはどこか頼りなく、私には情けないものでした。
ここで想定されているのは廉価なそれですが、いかにも和紙めいた高価なものだって、情けないとは言えないまでも、詰まらなさには変わりはないのでした。それを殊更にするような高級和紙(美濃紙)などは、私は未だに毛嫌いします。どちらかといえば、私は加工された紙を好みます。稀に、紙で指を斬ったりしますが、そんなプレスの利いた紙の方が潔くて、私は好きなのです。
余談の部類に入るかもしれませんが、私はこの国の文人たちが甚だしく好む、表は白くはあるがどこか薄汚れたような、あのぶよぶよした矩形や短冊状の紙製品ほどおぞましく思われるものはないのでした。果たして、言いすぎだったでしょうか。
同様に、どんな障子紙も好みません。冬の陽に映える、あのピンと張られた障子紙の佇まいなどは悪いはずもありませんが、ここでの私の評価は紙自体のこととご理解下さい。
但し、色付きの仙花紙(屑紙を漉き返したもの)の類いなら面白く思います。それらは廉価な漫画本の紙質に代表されますが、あのザツザツした感触は好きです。かつて、市販の干し海苔と大きさを同じいするほどの粗末な落とし紙があって、それを大量に束ねた代物などを、私は悪くないと思っていた時期があります。
それらの紙の塊(マッス)には無造作な風情と共にどこか依怙地な気分があって、そこには不細工な愛嬌とも呼べそうな魅力がないでもなかったからです。強いてその魅力を語るとするなら、あくまでも私が一匹の猫と仮定をした上での話ですが、そんな紙のマッスに今のところはさしたる用事はないけれど、とりあえずは肢の指でも研いでおいてやろうか、といったような誘惑を感じるのでした。
果たして、こんな説明で、私の気分がお分かりい頂けたでしょうか。例えば、遥かに後年、古紙集積場のボロ紙の圧倒的な集積を目の当たりにした時、私はある種の美的感動に捕らわれたことがあります。そのような気分のさきがけがそこにあった? まさか、われながら、あまり上手な説明とも思われませんが、それはそれ、お話を続けましょう。
とまれ、私は模造紙が好きなのでした。大判で多色の模造紙が学校には常に用意されていましたが、あんな紙を私用に使えたらどんなにかいいのにね、と小学生の私は思ったりもしたのです。だって、模造紙は教材として私たちに供されるものではなく、ハレの日の特別な紙だという趣きが常にあったのでした。つまり、運動会や学芸会、入学式や卒業式、夏休みや冬休みのあれやこれやの告知のためなどに、学校側から大いに振る舞われ、活躍するのです。それらは凝りに凝った花文字や花模様で身を飾り、教室や廊下のあちらこちらに貼りだされます。
しかし、そんな「学校の紙」も高学年のお兄さんやお姉さんでもなければ、どうこうする機会を持ちえないのでした。色味はくすみ加減でケバケバしさがなく、パステル・カラーの調子や紙の質感はどこか懐かしく、私には素晴らしく乙りきなものに受け取られていました。
でも、模造紙はこよなく愛しましたが、私はボール紙はさほどには好みませんでした。図工の時間に細工めいたことをさせられた時の、あの紙の頑なさに手を焼いたからでしょうか。いや、そればかりではないような気がします。今にして分かるのですが、子どもの私はその風合いに、どことなく馬糞を感じていたと思います。当時にあっては藁色の馬糞は私たちの身近なシロモノでした。道のあちこちに見かけたものです。
段ボールだってそうです。あんな箱には気のすむまで入っていたいと思いますが、紙そのものは人生的(生活臭?)すぎて好きになれません。英語で言えば、ボール紙も段ボールも、それらはペーパーではなく、ボードなのでした。
それなら、今も昔も藁半紙の方が断然、私には好ましい! 貧しくも健気な少年を感じませんか。この頃はとんとその名を聞かなくなりましたが、私はその気分を今に伝えている再生紙のメモ帳などを文房具店の店先に見かけたりすると、その健気さを思い、取りたてての用もないのについつい購入したくなります。
では、画用紙はでうでしょうか。稀少性に欠けます。ケント紙は? 余所行きすぎますね。セロファン紙やパラフィン紙ともなると、紙というよりは何かしらこちらの窺い知れない物質の「膜」というか「箔」を感じたりします。もう、それは紙以上ではないでしょうか。どちらかを選べと言われれば、私はセロファン紙の「ヒステリック」よりはパラフィン紙の「エキセントリック」の方に一目置きます。
セロファン紙やパラフィン紙が登場した以上、私としてはここにハトロン紙(クラフト紙)のことも取り上げざるを得ません。紙らしい紙といえば、私の中ではこの紙だと言えなくもなく、大きなものから小さなものまで、ハトロン紙はなんだって包みました。そのことは今なおそうでしょう。でも、包むツールとしての紙の領分を決して逸脱しないこのハトロン紙に、私は多大な好感を持ちこそすれ、今、この紙そのもの自体をとやかく言うつもりはありません。というのも、当時から、殊更に、この紙自体を有り難がっていたわけではありませんでしたから。
しかし無闇矢鱈に大きなそれが手に入るようなら、有体に申せば、村の綿屋さんから届いたばかりの、綿打ちの済んだ布団の綿を包(くる)んでいた薄茶色の紙が不用になる機会を、私は決して見逃しはしませんでした。家人に執拗に請い、なぜなら、このような大振りも大振り、拡げれば優に畳二畳分ほどもあろうかと思われる、しかも丈夫な包装紙は家人にとっても何かと再利用の道があったのですし、それでもなんとか頼み込み、決して破いたりはしないからと、私はその一枚をそっくりそのまま手に入れたりします。
手に入れるやいなや、私は早速身に纏い、自ら包まれてみたりするのでした。包まれては、奥座敷にひとり転がっていたりするのでしたが、そんな様を姉などは私のいつもの悪ふざけと受け取り、不必要に無視しました。ツンツルテンの、当時、簡単服と呼ばれたワンピースから、竹ひごのようなヒョロッコイ(か細い)脚を剥き出しにして、さも用あり気に一、二度、そんな私を跨いだりもしたくせに。多分に、下手に反応して図に乗らせても煩わしいとの用心からでしょうが、お生憎さま、それこそ私にあっては無用の配慮で、私としては奥座敷の薄暗がりの中でそのように自ら包まれ、蹲った形に寝転んでいさえすればそれはそれで大変、結構なことなのでした。
なんだか甘悲しいような、春のひと時の思い出ではありました。
ここで余談のひとつもあるとすれば、成人してからのことですが、私が路上で寝る羽目に至った場合の心得として、新聞紙の温かさについて、然るべき人からひとくさりの講釈を受けたことがあります。その断熱効果のほどは思いもかけぬほどで、新聞紙を下着と上着の間に挟みこんで、更には外側からそっくり新聞紙を纏うことが可能なら、その身が寒中のさ中にあってさえも、あなたは汗ばむほどの暖が得られると。
当時、私はそのような境遇に立ち至ってはいなかったものの、ああ、そういう日も近い将来ないとは言えだろうと、舌を巻く思いで傾聴したことではありました。
閑話休題。
私が私かに憧れた紙のことを語ろうと思います
近所の、私が懐いていたお兄ちゃんの所で手にした英語辞書(コンサイス)のことです。後々、その用紙がインディアン・ペーパーなるものと知りますが、子どもの私にはその紙の佇まいはただ事とは思えませんでした。私の「紙の記憶」の中でも、その地位は別格です。
一枚の紙のとしての魅力もさることながら、一冊の紙の束として、これほどの緊密さを実現しているものを、私は初めて目にしたわけです。手にするや、私はこの小振りでしなやかな紙のマッスを、心ゆくまで弄くっていたいと思いました。そして、出鱈目に、何度も何度も頁を括ったりしました。括っては、その中の一頁でも破ってみたいと無性に思いますが、しません。
そこで、私は思うのでした。「紙」や「箔」や「膜」は、そのようなモノの存在形式は破られることによって、あるいはその予感の裡に物性を、その本質を露にする。しかも、子どもたちにはそのことが夙に承知されていて、いわば共犯関係を担うのではないのかと。
その好例が、冬、村の小川や池や天水桶に張る薄氷です。それらは決して子どもたちの目を逃れることが出来ません。罰を蒙らないというだけで、目ぼしい所は必ずといってよいほど、私たちに割られてしまいます。私なども寒い朝の通学時には、砂利道のそこここで朝日にキラキラと輝く水たまりの氷を、地団駄をを踏むようにして割っては道草を喰いました。
薄さとは多分、そのような誘惑であり、美しさなのです。だから、私たちの手にする童話の中の少年少女は「幸薄く」あらねばならないのですし、絶世の美女は「薄幸」でなければならないのでしょう(この行の文意は松岡正剛氏の先の「フラジャイル」に負います)。
美ははかなく、移ろいやすい。はかなさとはもろさであり、先鋭化され、余りに研ぎ澄まされたものは壊れやすい。美はことほど左様に、のっぴきならない事態なのです。独逸の数理哲学者、O・ベッカー教授なら「美のはかなさと芸術家の冒険性」(久野昭訳、理想社刊)の中で、かく語るでしょうーー稀なもの、選りぬきのもの、弛みなきもの、あれかこれかではなく、総てか無かに従うもの。それ自身にのみ所属し、決して繰り返さないもの、つまり、一回切りなもの。そして、それら一切に属するもの、それらは美しい。美はだから、己の裡に自ら悲劇性を含み、限りなく一回性を、言葉を換えれば「永遠の今」を生きるのです(朧げな記憶のままに、適当に改変して引用)。
そして、今に今、私は少年時代に遭遇したひとつの光景を思い浮かべるのです。
ある晩い秋の早い朝、どこか遠方の少年の飛ばしただろう模型ヒコー機が、村の高い木の梢に遭難し、その梢の先端で、今しも入射した旭光に一瞬の裡に白く燃え立った姿を。と同時にその様を目の当たりにした時の、あの名状しがたい異様な感情もまた、蘇ります(「模型ヒコーキの庭で Ⅲ―d」の「夢の名残り」参照)。
当時、私はその節のその感情を持て余しましたが、それは「美しい」とする感情なのだと知るのはもっと後々のことでした。
私は再び思いますーーあれが私が生まれて初めて抱いた「美しさ」の体験だったのだと。しかも、かの模型ヒコー機はかの梢の先端で、今もなお、朝陽に照り輝いているのだろうか、などと。
(2020/10/20)
****** 次回へ ******
HOME
前回へ
|
|