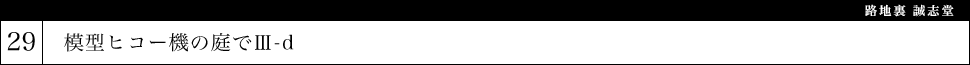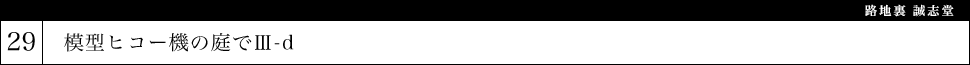写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
模型ヒコー機の庭でⅢ-d
〔光る竜〕
キリュウ? 私はお兄ちゃんを仰ぎ見ました。
お兄ちゃんは小さく頷きました。
そうか、そうか、やはりキリュウ、気流に乗ったんだ、私はなん度もなん度も心の中で頷きます。すると大きな渦が私の頭上で湧き立ち、ある形、ある姿を採りました。
「竜」です。
私は見たのでしたーー空の色に見紛うばかりに透き通り、そのものは確かな形を保ったまま、ゆっくりと私たちの頭上を越え、空の向こうへ流れ出します。クリスタル状の数多の鱗が秋の光に煌めき、無限軌道(キャタビラー)のような腹部をくねらせ、私は見たのです、「竜」は大きく波打ち蛇行します。
私は息を呑み、言葉を失い、その流れ往く姿を呆然と眺めました。
すると地上では、大きなものの影とも思しき小暗きものが、矢庭に、こちらから向こうへと疾走りだしました。かつては流れ海であったとされる、広濶な沖積平野に拓けた鬱金のフィールドを、限りなく透明な小暗きものが一陣の疾風(はやて)のように襲って往くのです。それはなんであったでしょう、空の陰り、「竜の影」でとでもいうのでしょうか。
目を戻せば「竜」は、その遠近に散在する竹薮や小さな社の叢林や、眼路の限り、ずっと向こうに点綴する幾筋もの集落の屋並みを越え、今しも、遠く飛翔するお兄ちゃんの模型ヒコー機を呑み込むところでした。呑み込みます。お兄ちゃんの機をまんまと呑み込んだ「竜」は地平線上の僅かな隆起、蒼い丘陵のラインの上に、淡く黛を掃いたように覗く山脈(やまなみ)へとうねり、揺蕩(たゆた)い、流れて往きます。私はその姿なき姿ともいうべきそのものを…………………………………、長大な光の帯状のものを、固唾を呑んで見送ります。
天空の「竜」はお兄ちゃんのヒコー機ともども遥か彼方の虚空へと消え去ろうとしています。もう暮れ泥む気配を見せている浅葱色の空の一点に、「竜」はみるみるたくし込まれていきます、まるで逆回されたフィルムのように。果たせるかな、砂時計の砂が落ち切る際にも似た静かな一瞬があって、時は溶け、私は我に帰りました。
その時でした。凍ったように後ろ姿を見せていたオンツァが、模型ヒコー機の消えた彼方を双手で示し、双手で彼方を指し示したまま振り返り、瞠目し、キリュウ! と声なき声で、私たちに訴えました。
お兄ちゃんは深く頷きました。
私は、私がまざまざと見た「竜」を、オンツァもまた見たに違いがないのだと、なぜか確信しているのでした。
〔光の影〕
私はその後、「竜の影」ともいうべき現象をなん度か体験しています。
例えば、それは夏休みに設けられた登校日のことでした。遠足の日の前夜とも違う、運動会の朝とも違う、この独特の日の奇妙な気分については、どなたにも思い当たる節があるのではないでしょうか。それは「学校の日」なのか、それともあくまで夏休みに帰属する「私たちの日」なのでしょうか。先生たちの形(なり)も物腰も、この日に限ってはどこか普段着めいています。思うに、登校日は「休みの休みの日」なのでもあり、どこかうら悲しく億劫な気分もありますが、夏休みのあの煩わしい課題や宿題はなお、執行猶予されています(刑は引き延ばされている!)。だからかなのか、この日の登校はなにやら気楽で、遊び半分の楽しさがないわけでもありません。
思えば、私の半生は夏休みの登校日、そのような宙ぶらりんな日々の連なりではあったでしょうか。とするなら、では、そこでは何がモラトリアムされていたというのでしょう。いやいや、そんな由なきことはさて措き、夏休みの登校日、その早過ぎる放課後、私は小学校の校庭にいます。
真夏の昼下がり、すべての物象はその陰影をくっきりと際出させ(あゝいゝな せいせいするな/風が吹くし/農具はぴかぴか光ってゐるし)、見渡せば田舎の小学校特有の広い校庭に、なんと、私はたったひとりなのでした。まだまだ校舎には帰りそびれた子供たちもいて、遠い声ではありましたが、あんなに楽しげな歓声も聞こえるというのに、学校の庭には誰もいません。校庭に隣接する農家の納屋からは、白色レグホンの間断を措かぬ鳴き声さえ聞こえます。奇妙な静謐に充ちた、白昼の真夜中とも呼び得るこんな一刻があるものなのですね。時の狭間に陥ったとでもいうべきでしょうか。はたまた、この身に神隠しが現象したとでもいうべきなのでしょうか、もし、そうとするなら、神に隠されたのは世界の方です!
とまれ、その寄る辺のなさは途方もなく、私はこの世ならずもひとりぼっちなのでした。すると、白く耀う無人の校庭を、透き徹った巨大な刷毛が薄墨色のものを刷いてゆきます。校庭の幅いっぱいに翼を広げ、大きな翳りが疾走り去ります。私は思わず空を見上げますが、そこには雲ひとつない漆黒の、と形容したいまでの群青の空があるばかりです。それでは、あれはなんであったのでしょうか。流れる雲の影でないとすれば、それでは最早、風の影とでもする外はない、さもなければ、光の影です。
〔家路〕
私たちの秋の一日は暮れました。
私たちはそれぞれの家路に着きました。茜の雲が西の空から放射状に棚引き、西の空そのものは真赤に燃けています。
私とお兄ちゃんも帰ります。私は後ろを振り返り振り返りします。オンツァはまだ、ヒコー機の飛び退った空を眺めています。秋の落暉は早く、残照の中で、オンツァは村のそちこちに佇つ石地蔵のひとつのようでもありました。
彼のぐるりでは、まだ今日の日の塒に帰りそびれた赤い蜻蛉が静かに舞っています。
私はお兄ちゃんの手を取りました。お兄ちゃんは私を見ました。私は目顔で尋ねます、失われた模型ヒコー機のこと、気流のこと、今日の日のすべてのこと。お兄ちゃんは黙って二、三度頷くと、遠く、ぐるりの空を仰ぎました。
西の、低い山脈の入日があった辺りに、淡い光の噴水とも呼ぶべき黄道光を、今日の私たちは見ることができるでしょうか。いつものせっかちな一番星は、暮れ泥む夕空にもう輝き出しています。頭(こうべ)を戻せば、東の空の方には熟れた鬼灯のように朱い、秋の大きな月が顔を覗かせています。
私は声に出して言いました、明日は何して、遊ぼう?
お兄ちゃんは繋いだ手を解(ほど)き、私の肩に手を置きました。

黄道光(ナショナル ジオグラフィックより)
〔夢の名残り〕
晩い秋の日の朝まだき、私たちは思いがけないところに、思いがけなく遭難した模型ヒコー機を発見することがありました。模型ヒコー機は村の高い木の高い梢の尖端に引っ掛かっていたりします。それは村の少年のものでは決してありません。なぜなら、私の村は小さな村なのでしたから、別のグループの模型ヒコー機だったとしても、そんな事態ともなれば、私たちの耳にニュースはすぐに届くのです。しかもそういう場合、私たちのものなら、私たちはなんらかの手立てをそこに講じ、その日の内に模型ヒコー機は必ず取り戻されたはずなのです。
だから、村の高い喬木の梢の尖端で、一夜をやり過したかの遭難機は遥か遠方の少年のものに違いがないのです。とすれば、その模型ヒコー機はどこか遠いところの、もうひとりのお兄ちゃんと私たちの夢の名残りといってもよかったのでした。
朝の光の裏側には既に、冬の到来を告げる冷気が含まれていて、やがて、私たちの秋は終るでしょう。今や、誰のものでもない模型ヒコー機は、少年の夢の名残りは、高い木の梢の尖端で、晩秋の鋭い旭光に的皪と輝き出します。
☆☆☆
〔「気流」について〕
「荘子」は逍遙遊篇、その劈頭早々に、九万里を天翔る「鵬」という大鳥の記述があります。曰く「鵬の南冥に徙(うつ)るや、水を撃つこと三千里、扶揺を摶(う)ちて上る者九万里」云々と。実はこの巨鳥こそ取りも直さず東南アジアを吹き渡る季節風、かのモンスーンのことだと、漢字学の世界的泰斗・白川静博士の著述(岩波新書「漢字」ほか)に見つけて、私ははたと小膝を叩いたことがあります。なぜなら、幼少時の私にはこの中国古代人のヴィジョンにも似た、それこそ夢のような記憶があったからでした。無論、そのスケールに関していえば余りにお粗末な話ではありましたが、以上、そんなことを伝えたく、模型ヒコー機の思い出をスケッチしてみましたーーかの「鵬(おおとり)」がモンスーンの形象化なら、多分に「竜」はトルネード、文字通りの竜巻きでしょう。そして、私の「気流」が「気竜」であったとしても、私には少しも可笑しくなかったのでした。
私たちは私たちの模型ヒコー機が、その唯一の動力源である糸ゴムを解け切らしても、天高く、それこそ「逍遙遊」し始める現象を、稀に目の当たりにしました。その際、私たちは「キリュウ」という言葉を使いました。あれはキリュウに乗ったのだ、と。そして、そのキリュウに乗せることが当時の私たち、ヒコー機飛ばし屋の、少年たちの夢でもあったのです。
後々、地上を離れること一万メートル上空に、東へと流れるジェット気流の存在を、私は知ることになりますが、その気流を「竜」に見立てることも、中々にエキサイティングなことではあります。数多の航空機をその只中に含んで、西から東へ、ぐるりと地球を巻くように飛翔する、巨大竜ですね。
しかし、そのヴィジョンはここでの私のお話を遥かに越えています。私たちの竜は、太陽光に暖められた地熱が作り出す上昇気流、せいぜいが地上二、三百メートル内外の出来事ではあったでしょうか。だから、先の巨竜、ジェット気流について語ることは、別の機会があればその秋(とき)に譲りたいと思います。
――「模型ヒコー機の庭で」、了。
付記(をお許しください)。
「永遠の今」を巡って――ノートから。
雲の信号
あゝいいな せいせいするな
風が吹くし
農具はぴかぴか光っているし
山はぼんやり
岩頸(がんけい)だって岩鐘(がんしょう)だって
みんな時間のないころのゆめをみてゐるのだ
その時の雲の信号は
もう青白い春の
禁慾のそら高く掲(かか)げられてゐた
山はぼんやり
きつと四本杉には
今夜も雁もおりてくる
宮沢賢治「春と修羅」は「雲の信号」に「みんな時間のないころのゆめをみてゐるのだ」の一行を見出した時、私は忽ち、かの孤高の論理学者・ヴィトゲンシュタインの著作(「論理哲学論考」)の中の「永遠を時間の無限の持続とするのではなく、無時間性と解するなら、現在のうちに生きるものは、永遠に生きる」を思い出していました。と同時に、本文にも引用したエックハルト師の「永遠の内には昨日も明日もなく、そこには現なる今があるだけである」に思い至ったのでした。
そして、このように定義された「永遠」こそが実はわが折口信夫が恋慕い、この国の祖(おや)たちが「魂のふる郷」とした海(あま)の彼方の「妣が国」もそのような事態の裡にある、つまり、常世などの「常(トコ)」はそのような事情を指している、に思い中りました。「常夜(とこやみ)・常暗などの云うトコは、永久よりも、恒常・不変・絶対などが、元に近い内容である」(折口信夫「国文学の発生―第三稿」)ーー折口もまた、「常(トコ)」とは時間の無限の持続(=永久)ではなく、無時間性(=不変)にあると申していたのです。
尚、西郷信綱の「古事記の世界」には「神話の世界は無時間であり、それは時間がないということではなく、無時間性という独特の時間である」が見えますし、更に「集合的無意識」の発見者、ユングならさしずめ、折口の「妣が国」や西郷の「神話の世界」を支配するのは「現在、過去、未来が一つであるような無時間状態のエクスタシー」(「ユング自伝」、みすず書房)とでもするでしょう。そこで再度エックハルト師に戻るなら、ここにこそ師の「永遠は常に新しい」との明言が甦るのです。二度引きになりますが「常に新たであるのではないとしたならば、永遠は永遠なるものではないことになるであろう」。つまり、本文に認(したた)めた通り、永遠はいつだって「ぴかぴか」なのでした。ワーオ!
M・デュシャン共に、二十世紀はアバンギャルドの神々の一人であったジョン・ケージも、「文学的なるものはすべてメルヒェン的でなければならぬ」と「青い花」の巻頭に掲げたノヴァーリスも、そして、そう、ユングもまた敬愛した、わがマイスター・エックハルト師の言葉はいつだって、迷い多き私たちの、少なくても私の聖エルモスの灯(ファイアー)なのでした。
****** 次回へ ******
HOME
前回へ
|
|