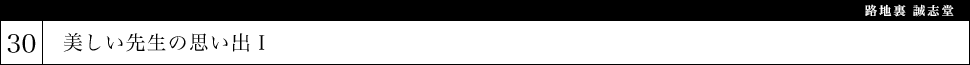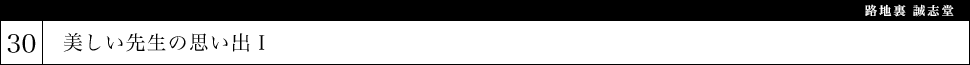写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
思えば、私はお兄ちゃんの作るような模型ヒコー機を家人に請うて、一笑に付されたことがあります。頭ごなしに、家人は私の無謀をたしなめます――作れもしない癖に、と姉。大きくなったら、と母。
では、あんな模型ヒコー機は当時、幾つくらいの子のものだったのだろう、と考えることがあります。大きくなったら、と大人たちはことあるごとに言います。言いますが、この「大きくなったら」は、彼らのもうひとつの口癖の「こんどね」と同様かなりの曲者なのです。私の経験則でいえば、彼らの「こんどね」の今度なんて、一度だってあった験しがないのでしたし、大きくなったらなったで、更に「大きくなったら」が繰り返されることが常でしたから。
では、その「大きくなったら」というのは幾つくらいを指すのだろうかと、常々、私は思い悩んだりもしたものですが、模型ヒコー機のそれなら推測が付きます。お兄ちゃんのいる子は別として、やはり小学五、六年生あたり、早い子で小学四年生。その下の子はもっぱら、穴の開いた硬貨一枚で購えたボール紙製の紙ヒコーキで遊んでいたと思います。
ということで、ここで、私はその紙ヒコーキに纏ろう思い出を語ります。
当時、私たちは模型ヒコー機に対してこの紙の玩具を「紙ヒコーキ」と端的に呼びましたが、所謂「折り紙ヒコーキ」と区別するため、以下、「ボール紙ヒコーキ」と呼称します。
〔ボール紙ヒコーキ〕
私はこのボール紙ヒコーキがことのほか好きでした。かなりの年嵩までそれで遊んだ記憶があります。頑是ないといわれればそれまでの話ですが、そして、私は何かに付け家人にそう言われました。
ガンゼナイ?
そう、ガンゼナイの!
その意味性ははっきりとは分かりませんでしたが、何度も言われれば、朧には彼らが何を言いたいのかくらい分かりますから、聞きわけがない、強いては子供っぽいほどの語義かと察してはいました。が、でも、子供に向かって子供っぽいとはどういうわけかと、ここはひとつも絡みたいところですが、まあ、よいとしましょう(子供っぽい子供がいても少しも可笑しくはないでしょうから)。
ボール紙ヒコーキは購入時には機体、主翼、尾翼と三つのパーツに別れています。購入後、私たちはこれを組み合わせます。取り立てて申すほどのこともありませんが、説明してみると、二つの翼(主翼と尾翼)を水平に、機軸となる本体の前後の切れ目に差し込めば、はい、出来上がり。デザインは前世紀中葉の世界大戦で名を馳せた主に日米の戦闘機。それらの拙劣な意匠も今にしてみれば、反って好ましく思い出されます。
機軸の後部は垂直尾翼も兼ねて迫り上がり、最前部には重しとして鉛粒が挟まっています。その機首に中る本体の下位置には、ゴムを引っ掛けるための刻みが入っていました。棒切れの端に結わえたゴムで(当節はそんなゴム付きの棒切れをゴム・カタパルト、飛行機射出装置と呼ぶそうですが、気恥ずかしいような大袈裟な物言いですね)、要はパチンコ(私たちがゴムトと呼んだゴム銃のこと)のようにして飛ばしもするらしいのですが、私たちにあっては、そんな気障な飛ばし方は終ぞ、誰もしませんでした。ゴムで飛ばすなんて、とても軟弱で気取っていると、村の子供たちには感じられたのです。
私たちは膂力だけで飛ばします。幼いわりに私は上手でした。高く遠く飛翔させようとして、空に向かって投げてはいけないのでした。そういう飛ばし方もあったのでしょうが、私は違いました。翼の反りを微妙に調節し、地面に叩きつけるようにして飛ばします。これは中々に勇気のいることでしたが、なぜなら、ヘタをすれば地面に叩き付けてしまう間抜けを演じるわけですから、でもね、あるコツを得ると紙ヒコーキは地面すれすれに滑空し、やがては急激に双曲線を描いて矢庭に上昇します。上昇してはブーメランのように身を翻しては、なんと飛ばした我が身の方に舞い戻ることさえあるのでした。その姿はまるで飛燕! これがなんとも面白く、私はこの紙の玩具を子供時代を通して愛したのです(思えば、このような技もオンツァのコーチングの賜ではあったでしょう)。ですから、私はこのボール紙ヒコーキで、随分と飛ばしっこをして遊びました。そんなわけで、私は誰彼となく相方を探し、見境もなく挑発したものです――サシデ勝負!
この日も、ボール紙製のヒコーキを掲げては近所のお姉さんたちを見かけると、私は彼女たちの面にヒコーキを突きつけてはこのサシデ勝負!を連発し、至るところで顰蹙を買っていました。今となっては弁明の余地もないほどに愚かな心情だったと認識しているのですが、サシデショウブの語感に、私は何ほどかの男の子らしさを意識していたと思います。そうに違いがないのです。しかも、軽い侮りを交えた異性への甘えた気分と共に。
なぜ、そんなことが言えるのか、それはどんな甘えにも相手への軽い侮蔑が含まれるからです。だから、甘え合っている愛人同士は互いに侮蔑し合っているともいえるのですし、実は、そこにこそエロティシズムの秘密の一端が覗いているわけですが、いやいや、ここでの私のペンはこれ以上、そちらには向かうことはありません、悪しからず。
〔サシデ勝負!〕
私の勝負事、「サシデ勝負」は試しに験した姉などは鼻でせせら笑い、お話にもなりませんでしたが、けれどもひとりの女性がその挑戦に応えてくれました。彼女は身を屈め、その鼻先を私の鼻先に突き着けて(あゝ、いい匂い、こんなにいい匂いってなんだろう)、私の目を深く覗き込み、よっしゃ、勝負すっかとわざとのように蓮っ葉に言い、でもどこかに真剣な響きを込めて、私の挑発に乗ったのです。
そう、来たか、子供心に私は戸惑いました。本当にショーブする気なのだろうか、だって、なんと彼女は私の担任の先生だったのですから。
彼女は学校出たてのお嬢さんで、私たちが最初の受け持ちだと常々語っていました。今思えば、まだうら若き女性であったはずです。どこか遠い所の、町場の出である彼女は、私の村の商家の離れに下宿住まいを余儀なくされていました。当時、女の人を美醜の形容の下で見ることなど思いも及ばないことでしたが、美しい人は子供には眩しく輝いて見えるだけです。
美しい先生でした。学校のない日になど、私は近所で出会う先生を、先生ではない先生を、いつも不思議な気分で眺めるのでした。そんな際、彼女はまるで近所のお姉さんのような砕けた口の利き方をすることもあったのです。私はそんな彼女の口ぶりに誘われて、「命ガケ(サシデ勝負!)」を口走ってしまったのに違いがないのです。
学校のない日、秋の暮れとはいえ、逢魔が時と呼ぶにはまだまだ間のある時分、先生はどこかへのお出かけからの帰りと見受けられました。近くのバス・ストップの界隈で私たちは出会ったのです。彼女は呆然と突っ立っている私を、私たちが「お山」と呼ぶ村の集会場の庭へと誘いました。彼女は普段のブラウスとは質の違うブラウスを身に纏っていました。襟元が眩しいほど大きくはだけていて、今ならわかります、あのたっぷりとした胸元の揺らめきを包んでいたのはサテン、絹のものではあったでしょう。
若い先生はその袖口を、もう、捲り始めていました。
その腕捲りを見てしまっては、私としては何を躊躇することがあるでしょう。ここは後を見せるわけにはいきません。まして、男子は四の五を云わず然諾を旨とします。ですから、私はきっぱりと受けて立ったことは論を俟ちません。どころか、尋常に勝負だの、飛んで火に入る夏の虫だのと、随分と芝居掛かった台詞を、あることないこと繰り出していた記憶が、私にはあります。実は、このようなもの言いは当時、男の子なら誰でもが夢中になった熱血少年漫画、剣道の防具の胴が赤いことをもってその名も高き、我らが少年剣士の賜物だったでしょう。あるいはその手の類いの紙芝居のものではあったでしょうか。
とまれ、その中でも私の最もお気に入りの台詞は、むむ、殺気を感じる! でした。常々、その使用の機会を探していましたから、私はこの機会を利用して、むむ、殺気を感じる! 心の裡で呟いたに違いがありません。事実、その節の美しい先生にはそのような気配がないこともありませんでしたから。
私たちは日が暮れるまでの、小半時もボール紙ヒコーキに興じたでしょうか。勝負の結果は火を見るが如くに明らかで、語るほどのこともないのですが、私の敵ではもとよりありませんでした。
今や、美しい先生は既に私とのカワリバンコの「サシデ勝負」を諦め、美しい顔を美しく紅潮させ、私に教えを乞うたりしました。私はオンツァ直伝の秘技を、他でもない先生だから、だからねと念には念を押して伝授しました。まるでツバメのように飛ぶからね。
燕?
そう燕!
彼女は案の定、飲み込みが悪かったのですが、まあ、その辺を過度に期待もしていませんでしたから、所詮、先生とはいえオンナなのだし、私としては適当にあしらっていたところもありました。軽い侮蔑! ところが、彼女はその持ち前の頑張りで、終には私の遣り方をまんまとマスターしてしまったのです。やるな、私は侮れない気持ちを抱いたことを憶えています、ただの女(アマ)っ子先生でなんかあるものか、大変なお転婆さんだこと!
彼女は私のボール紙ヒコーキを少女のように興じ、つまり、何かと一喜一憂するは、いちいち嬌声を挙げるは、上手に飛ばせたりした時には自らの成功を自ら祝し、スカートを鮮やかに翻したりしました。小さな女の子が余所行きのスカートを身に着けた際に必ず行う、あの身を回転させる遣り方で。全く、彼女たちはなぜあんなことをするのでしょうか。当時、その所作は私にはとても理解し難いことのひとつなのでしたが、それは人間の女の子特有の、動物ではオスの習癖なのですが、これこそ動物行動学(エソロジー)でいうところの求愛ディスプレーではないのでしょうか(失礼!)。
それはそれとして、大人の女の人がまるで小さな女の子のようになってしまう時があること、なんだかそれが切ないような気がすること、そんなことを、私はこの日の彼女から学んだようにも思います。
キミ、と彼女は不意と先生に還り、それでも悪戯っ子のような気分を目の輝きに留めて、幾分改まり、私を真っ直ぐに見ました(思えば「キミ」、それが彼女の私たちへの呼び掛け方でした。その呼称の鮮烈さにはひと頻り、クラスのオラとオメたちの間で話題となったものです。キミ、キミ、キミキミ、卵の黄身と、私たちは互いを呼び合って巫山戯たものです)――キミ! キミのいう通りだね。燕? 燕! と言うなり、ありがとうと私の耳元で囁き(いい匂い!)、緩くフレアーの付いた裾広がりのスカートを颯爽と翻して、私の前から消えました。
うら若いご婦人が幼い男の子と対等に、しかも真剣に応対する姿は悪くないどころか、今にして思いますが、とても佳いものです。そこには一片の侮蔑もないのでした。
女先生と別れた私は暮れ泥む家路を走って帰りました。ボール紙ヒコーキを頭上に掲げて、もう一方の手は勿論、水平です。空飛ぶものを手にして走る時はこうでなければなりません。どんな場合でも私たちはそのことを疎かにはしないのです。(つづく)
****** 次回は、 4月20日頃の予定 ******
HOME
前回へ
|
|