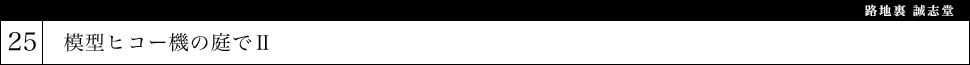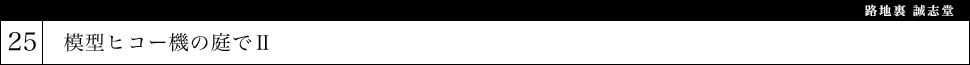写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
模型ヒコー機の庭でⅡ
私たちは首輪を外した、もう、子犬のようなものでした。
確かに、私たちは子犬そのものでしたが、そういえば、私たちの仲間に少年たちの愛犬が加わっていたという記憶がありません、なぜでしょう。一匹や二匹、彼らが混在していたとしても少しも可笑しくはないのに、模型ヒコー機への危惧とその配慮からだったのでしょうか、それとも単なる私の記憶の脱落なのでしょうか。とまれ、女の子たちが参加していないことは理解できますが、それは村の子供たちの習俗のひとつに過ぎなかったのですから、と書きかけて、不意と、女の子がそんな私たちの中にいたことを思い出しました。
女の子といってもほんの幼女に過ぎなかったのですが、それはこの日のことであったか、あるいは他日の同様な日のことであったか、今となっては定かではありませんが、そのことに少しく触れてみます。
[塚の上の幼女]
空高く舞う模型ヒコー機を追って、田圃の中を駈けずり回っている、そんな時です。何気なく鎮守の森の塚に目をやると、私はその天辺の祠のところに何やら紅いものを認めました。ん? 目を凝らすと、なあんだ、紅いべべを纏った幼女でした。彼女は着膨れに着膨れて、その立ち姿は遠目にも、どこの家のお茶の間にも必ずひとつや二つは飾ってある女(め)の童、あの「こけし」を思わせました。
幼女は空の模型ヒコー機などには興味がなさそうで、時に空のあらぬ方を見遣ったりもしましたが、彼女のお目当ては何より、この私たちであることは私の目にも一目瞭然でした。何が面白いのか、両の手を懐手にして、只々、田圃の中で大騒ぎを繰り広げる私たちを飽かず眺め入っているのでした。
もしかすると、彼女は眼下で遊ぶ私たちというよりは、彼女のお兄ちゃんを目で追っていただけなのかも知れません。年長者にはそういうことは皆無でしたが、私たち年少者の中には大して年の差もない妹を子守り代りに、家人に押し付けられるケースはあったのですから。中には、何かといえばお兄ちゃんお兄ちゃんと、お兄ちゃんでもなければ夜も日も明けない妹御もいたりして、常に金魚の糞のように、お兄ちゃんの後を付いて回る子もいたのでした。私なんかと同じ年格好の遊び仲間にもそのようなタイプの兄妹がいて、私はそんな女の子にけっこう辛く当ったりもしたことを憶えています。男の子同士の遊びの中で、時に鬱陶しいような、何かと邪魔ッ気な気がしたのでしたし、ある時なんかその遊び友達の目を盗んで、彼女のお鉢の張った頭を小突いたりしたこともあります。あれはどんな質の衝動だったのでしょう。小突く明解な理由など何ひとつなかったのですから、可愛いさ余ってのことだったのでしょうか、まさか。
でも、そうであったかもしれません。なぜって、私にもそのようなものが一人ほどいましたが、常日頃、邪険に取り扱っていたとはいえ、その癖、妹なる存在を何やら悪からず思っていたような節がないでもなかったからです。ああ、それなのに、どうした弾みからか、そのお鉢の張った幼女のお頭を見ると、わけもなくコツンとやりたくなってしまうのは、我ながら実に面妖なことではありました。
閑話休題。
塚の天辺の幼女も、我がヒコー機の庭を駈け回る、きっと誰かの妹なのでしょう。まあ、そんなところが相場だと思われました。
それにしてもどこの子なのでしょうか、私の知る遊び仲間の中ではとんと見かけぬ女の子でした。でも、今はそんなことに忖度している暇(いとま)はありません。日ごろから慕っているお兄ちゃんのヒコー機を追い求めなくてはならないからです。だって、その模型ヒコーキはお兄ちゃんの手元で手始めから出来上がるまで見守り、その完成をしかと見届けたものであったのですから。
私は模型ヒコーキを追いました。
私以外の子供たちもそれぞれの担当するヒコーキを追い、もう、必死です。なぜなら、模型ヒコーキが地上に舞い降りた際は誰よりも早くヒコーキに駆け寄り、確保しては、それぞれのお兄ちゃんの元へ届ける任に、私たちにはあったのです。とはいえ、私たちの空には模型ヒコー機が一機も飛翔していない、そんな非在のひと時が必ずあって、そんな時こそ私たち年少者のいっぷくの時間です。ひと息を入れに塚に戻る、戻ろうとして、そうだ、塚の祠の辺りを窺うと、件の幼女はもう、いませんでした。
塚に戻るや、私はさも用あり気に鎮守の塚をぐるりと巡り、奈辺を左見右見しながら探ってもみましたが、そこにはどんな人影もありませんでした。そんな余りの脈絡のなさに居心地が悪く、私は目星を付けた二、三の仲間にやんわりと問い質したりもしたのです。すると、そんな女の子は知らないし、見てもいないと一様に彼らは頭(かぶり)を振りました。そんな馬鹿な話があってよいものでしょうか。どこの家の子かは知らないけれど、また、知る由もないけれど、ひとりでお家に帰ってしまったのでしょう、自分なりにふんぎりを付け、私は自分を納得させてみたことではありました。
しかし、たとい、彼女が私たちと幽明界を異にするものだったとしても、なんら驚くには中りません。なぜなら当時、度々とはいわないまでも、私は人が見ないとするものを見たりする傾向があったからです。多分に、私には放心癖があったのです。
そして、ここに御託のひとつもあるとするなら、どのような形式の下であれ、見たということは見えた者にとってはその限りに於いてうつつの体験ではあるのです。寝て見る夢だって、夢見そのものについてはうつつの経験といえるように、そこにどんな不思議もありませんーー「眠っている時、どんな夢でも私を楽しませてくれるが、すぐにそれが夢だとわかってしまう。そんな時私はいつもこう考える。これは夢で、私の意志でどうにでもなる純粋な娯楽である」(J・L・ボルヘス、堀内研二訳「夢の本」国書刊行会)。
一方、ボルヘスとともに私が私かに敬愛するトーマス・マンなら「錬金術的教養(成長)小説」とも呼ぶべき「魔の山」の中で、吹雪の山で遭難しかかった主人公のハンス・カストルプに、その黙示録的な夢見の後で述懐させますーー「夢だとは思ったさ」、そして続けます、「…己(おれ)にはそれがわかっていたんだ、みんな自分で作りあげたことだ」と。その上で尚、「夢は、自分の魂からだけではなく、それぞれに違ったものであっても、無名で共同でみる、と己はいいたい。己はその一小部分にすぎない、大きな魂が、たぶん己を通して夢みるのだろう、己の場合は己なりにの形で、その大きな魂がいつもひそかに夢みている…」(高橋義考訳)。
さてこそ、私はここに問うのです、思い出の中の白日の夢も、自分の意志でどうにでもなるものであったでしょうか、と。別言すれば、書かれたものは書からざるを得なかったものなのか、あるいは何ものかによって書かされたものなのか。いやいやそうではなくて、やはり、あくまでも私の恣意にすぎない? 果たして、そこのところはどんなものなのでしょう、私のアポリア。
……
そして 語ってもなお
ぼくは思い出せないだろう
あの美しい
幻
いつまでも
ぼくは思い出せないだろう
ぼくは友だちに言う
すばらしいことはみんな夢の中で起こった
ぼくらはそれを思い出せないで暮らしている
……
――辻征夫詩集「学校の思い出」(思潮社)より。
****** 次回へ続く ******
HOME
前回へ
|
|