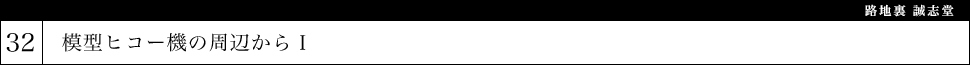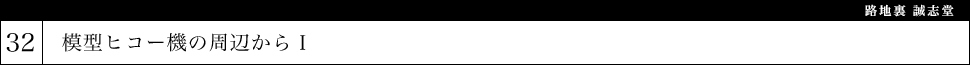写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
ボール紙ヒコーキに纏ろう思い出を語った以上、もう一つの紙ヒコーキ、「折り紙ヒコーキ」にも触れておきたいな、そんな気がしました。これから私は、まずは「折り紙ヒコーキ」、継いで「ペーパー・プレーン」のお話をします。
〔折り紙ヒコーキのことなど〕
朝の新聞に挟まっていたチラシやなんかで、とり敢えずは折ってみる紙ヒコーキは、幼い私には詰まらないシロモノでした。私にしてみれば、これらは「飛ばないヒコーキ」であったのです。そんな遣り方があると知り初めた頃、私はなん度か試み、その果てに、こんなものちっとも飛びやしない、子供騙しもいいところだと子供なりに喝破し、本気を出してかかずらうことなどなく、せいぜいがひとり無聊を託つ時の手慰みにすぎませんでした。
でもね、今に至って、そんな紙ヒコーキだって紙質を吟味し、折り方の工夫次第では信じられないような飛翔を見せるということを、私は知っています。究めれば、その世界も中々に奥深くあるらしいのだとも了解しています。あんな手折りの一枚の紙っぺらを野外に於いて、なんと、12秒間も滞空させるというようなロマンティックな試みさえあると聞いています。これが可能なら大変な偉業といわざるを得ないのです。だって、その秒数はかのライト兄弟の初飛行記録に匹敵するのですから。航続距離の方は確か、36メートルでした(それらを以って、あれは飛行ではなくジャンプだったなどと言うのは、後出しじゃんけん的評言の典型です)。たとえ挑戦者たちが、その挑戦にことごとくに失敗せざるを得なかったとしても(私は成功を祈っていますが)、その志は偉としなければならないでしょう。私は偉とします。
「それは、一九〇三年十二月十七の朝、十時三十分のことだった。木と帆布と針金でできた貧弱な飛行機が、アメリカの北カロライナ州キッティ・ホークの砂浜に作られた滑走路から飛び上がった。そして、ふらふらと十二秒ほど飛んだかと思うと、地面に突っ込んだ。その速度は時速十一キロメートル、音より早いジェット機が一日で大西洋を往復する現代から見れば、まことにあわれなものである。だが、これこそ歴史上、もっとも偉大な瞬間であった。鳥のように空を飛びたいという数世紀以来の夢が、この時はじめて実現したからである。」――(J・テイラー著「大空にいどむ」橋本英典訳・岩波少年文庫)。 (引用文 2020/11/1追記)
なお、立体折り紙ヒコーキ「スペースシャトル」の製作者である戸田拓夫氏に拠れば(「折り紙ヒコーキ進化論」)、とあるテレビ局の企画で、パリは凱旋門の天辺から飛ばした折り紙ヒコーキは、なんと「時間にして一分二四秒、凱旋門から約二五〇メートル離れた」ところまで飛んだそうです。では、平地に於いてはどうなるでしょうか。第一回全日本折り紙ヒコーキ大会(03・3・21)の最高記録として、室内(体育館)とはいえ、16・14秒の飛行が報告されていました(氏自身は18・10秒の飛行記録を持つと言います)。
ただ、当時の私にあっては如何せん、如上のような種々に理解が及ぶまでには余りに年端がいかなかったのです。ですから、私は折り紙ヒコーキを貶めようとしてこれを書いているわけではありません。私は私の不明こそ詫びるべきです、ここに遅ればせながら、紙ヒコーキ愛好者たちの皆さんにご容赦のほどを願います。
でもねえ、幾ら齢(よわい)を重ねても所詮、そこにあるのは一枚の紙じゃないか、というメカニカルな面でのもの足りなさと、愛好者ならそこが妙味と仰りたいのでしょうが、わかります、わかりますが、その一枚の紙の制約を、私には味わい深いものとはとても思われなく、遺憾なことに、単に不自由としてしか受け取れなかったのも事実なのでした。
くどいようですが、私だって人並みに紙ヒコーキは折りました、気が向けばちゃんと帳面も破きました。このような紙ヒコーキは先生の目を盗んで、時折、退屈な教室の空に舞ったりはしなかったでしょうか。としても、それは決して私の仕業ではありません。なぜなら、新聞に挟まったチラシはもとより、目ぼしい紙を見つけた折にはその紙で、時には切ったり貼ったりまでして趣向を凝らし、色々と試してみましたが折り紙ヒコーキはいつだって私を満足させなかったのですから。
それは多分に、私のせっかちと不器用のせいであったでしょう。と同時に、その飛翔に関して、私の思い描く理想が高かったことも一因だったかもしれません。手首を利かせたスナップでキュッと飛ばせば、わが機はわが意を得たように、あの大空に、まるで野鳥の飛翔のように飛び退っていく(まさか、ねえ)、そんな折り紙ヒコーキの姿を思い描いていなかったとは言えないのですから(勝手なものです)。しかし、そんなことは金輪際あろうはずがなく、早い話が、私によって折られた紙ヒコーキは二、三度試みられた末に、いつだってクシャクシャと丸められてしまうか、丸めてぶん投げられないまでも、そこら辺に打遣らかし。
再度、ここに陳謝を謀れば、先に挙げた参考図書「折り紙ヒコーキ進化論」には一読、目から鱗が落ちたとはこのようなことをいうのでしょうか、感興著しいものがありました。紙ヒコーキについてこれほどに教えられたことはなく、私は改めてその魅力を認識したのでした。その上、そこには著者自身の手になるオリジナル作品の中から(その創作機は五百を数えるといいます)、10数点ほどの折り紙ヒコーキが写真と図解で紹介されていて、これが一枚の紙? その多彩な一点一点を私は刮目して見ました。だけでなく、ついつい、折り方の図解にそそのかされて、その中のなん点かは実際に折ったりもしたのです。
果たせるかな、どの一機を採っても完成されたその姿は飛行力学に則って、斬新かつ優雅で、それぞれがそれぞれの機能美に溢れています。そのことに、私は何よりも感心したのでしたし、実際に飛ばしてみれば(二、三のタイプだけでしたが)、それらは私の折り紙ヒコーキの先入観をぶっ飛ばすように、よく飛びました、驚きました。
ちなみに「折紙ヒコーキ」とは「一枚の紙で、貼ったり切ったりせずに折り挙げたもの」と、戸田氏は簡明に定義なさっています。
尚、紙ヒコーキの「飛行の神髄」を知るためには恰好な方法があります。以下「飛行の科学入門」と銘打たれた「鳥と飛行機どこがちがうか」(ヘンク・テネケス著、高橋健次訳)からその実験のさわりを紹介しておきましょう。
用意するものはハガキ一枚と大きめのクリップです。ハガキを(紙ヒコーキの要領で)そのまま飛ばしてみれば前方には飛びません。後方に宙返りしてはひらひらと舞い落ちるだけです。そこで、折り目を付け、その中央線の先端にクリップを挟みます。これで、ハガキの重心が中央部分から前方に移りました。飛ばしてみれば先程よりは前方に舞いますが、よく飛ばすためにはクリップを前後にこまめに調整しなければなりません。正しい位置に重心があれば、紙ヒコーキは「適切なトリム(平衡状態)」がとれ、より滑らかな滑空が約束されます。このことで学ぶことは紙ヒコーキは「重心の位置にきわめて敏感だ」ということです。しかる後、ハガキの後部両端を縦にちょっと折り上げ(垂直尾翼ですね)、ハガキを中心線から二つ折りにします。その折りの角度も大変微妙で、紙ヒコーキは「操縦翼面」の変化にも敏感なので、何度も飛ばして調整します(以下、略)。
と、まあ、ことほど左様に、私たちは一枚のハガキを上手に飛ばすことさえ、それなりの工夫と研鑽が必要であることを知ります。以上は、あくまでも紙ヒコーキによる「飛行の神髄」を学ぶための試みでしたが、このような操縦翼面の角度のこまめな調整や、重心の補正で、私たちのより良い飛行を求める努力は、紙飛行機も航空機も同じだと同著にありました。
なるほど、今さらながらですが、端倪すべからざるは折り紙ヒコーキですね、というような結語でこの項は取りあえずの〆としましょう。
「創り出す人々」Vol.1 紙ヒコーキ作家 戸田卓夫さん
〔ペーパー・プレーンのことなど〕
今や、そんなわけで、私は折り紙ヒコーキのすこぶる怠惰ですが隠れた信徒、そのシンパサイザーであることには違いがありません。とはいえ、私にはやはり五円玉一個で購えた、かの「ボール紙ヒコーキ」のことも忘れられないのでした。
今ともなれば、駄菓子屋で購えたあんなボール紙ヒコーキを手に入れる術もないのでしたが、ふと思い立って、私は工作専門店に足を運んでみたことがあります。すると、無論、私の求める当のものはあろうはずもなかったのですが、ペーパー・クラフトのヒコーキ・キットが売られていました。早速、ニ、三種ある中から良かれと思う一つを買い求め、私は部屋で作ってみざるを得なくなったのです。
その紙片は思いのほか薄く、既に四つのパーツに、機軸である胴体と、主翼、尾翼、垂直尾翼とそれぞれが復数枚ずつカッティングされていました。それらの薄めの紙片を差異を持たせて、つまり胴体などは機首に向かって順次に厚く、糊で貼り合わせていきます(その最大に厚いところは七重にも)。主翼は二重です。尾翼は一枚の紙片の薄さのままでした。しかる後、その四つの部位を組み立てます。完成までの手順はやや煩雑ですが、構造的には私の愛したボール紙ヒコーキと変わりません。
然るべき人が然るべく設計したものらしく、その紙ヒコーキは機体と翼とのバランスや、そこかしこの紙の厚みの捉え方に独特な工夫が見られました。無論、空気力学的にもそれなりに吟味されているのでしょう、完成してみるとその姿は実に洗練されていて、少年のように美しい少女を思わせ、私には大層エレガントに見えました。私にとって美少女とは見目形だけをいうのではありません。その存在から女性性が節約され、限りなく少年に近付く者です。
さればこそ、エレガンスとはその機能を実現するに最も倹約された形をいいます。換言すれば、最小努力の法則、あるいは思考節約の原理とでも称されるでしょう。そして、その元を糺せばあの「オッカムの剃刀」ですね――14世紀の神学者、オッカムが口うるさく唱えた思惟原則、ある事態を説明するにあたってはいたずらに仮説を立てるものではないとします。
その原理はやがて、音速の単位にその名を遺す、19世紀の物理学者、E・マッハに引き継がれ、彼の「思惟経済の原則」へと発展します。私たちの認識は現象と感覚の関数的関係の裡にあり、その認識の記述が科学的と呼び得るためには可能な限り簡潔でなければならないだろう、約言すればそのようなことだったでしょうか。わが田に水を引けば、最短に語れ、而して優美であれ、という戒めになります。
更に話を継ぐと、以上のようなことは「無生物・生物・精神過程・社会過程」を問わず、どんな「システム(相互に作用する要素の複合体)」にも言える原理原則です。これがいわゆるシステム工学でいうところの「最善の世界」、すなわち「おそろしく複雑な相互作用の網目の中で最小の費用で済む最適を保証」する「最小努力の最大効果」と呼ばれるものです、なるほどね――この段の「」内の文言は「一般システム理論」(F・ベルタランフィ著、長野敬・大田邦昌訳、みすず書房)からの引用。尚のご興味を持たれた方はどうぞ当該図書に中ってもみて下さい、好著です。
ところで、複雑な方程式があれよあれよとシンプルな数式に解消していく、どんな方程式のシステムも美しいものですが、そこにも同様な消息が関与してはいないでしょうか。しかも、私はその解消の軌跡にはある種の工作物の抽象された飛跡をすら感受します、などと申せば余りに牽強なもの言いだとお叱りのひとつもあるところでしょうか。ともかく、数学者は数式を審美的(エステチック)に見るそうですが、その上、そして、式の真贋は式の美しさに現れるなどとさえ言います。真なるものは自ずから美しいだなんて、たとい不可逆的にとはいえ、よくも言えたものです。ス・バ・ラ・シ・イ!
とにもかくにも、私たちが所有する美しい数式といえば数ある中でも、その代表選手はE=MC2でしょうか。こちらの方はまずは異論のないところと思います。なぜなら、このたった数文字の数式には私たちの宇宙の秩序(コスモス)が表徴されているのだし、そうだとするなら、この簡明な方程式には宇宙大の典雅が偶有されています。そして、そのことは当のアインシュタインの信仰でもあったわけでした。神は骰子を振らない!
しかし、神の中には不届きものの神もいて、ボーアやハイゼンべルクの量子力学の神などは「不確定」の骰子を振るのですが、それはまた、別なお話です。とはいえ、そのさわりの一端をここに陳べれば、我々の極微の世界は確とは定め得ず、常に確率的にしか語れないという原理があります。すなわち、極微を構成する素粒子の速度を確定すればその位置が測定できず、位置を確定するなら、その速度は確率的にしか確定できないというジレンマのことです(ハイゼンベルグ「不確定性原理」)。量子力学的に「わかる」とは素粒子の位置と速度の確定を俟って成立するわけですから、私たちの極微の世界は「確率の雲」に覆われているということになります(ただし、その確率の幅は厳密に計測されます)。
ここにおいて、絶対と思われていた古典力学的物質観・世界観はそのパラダイムの変更を余儀なくされました。哲学者のホワイトへッドの言を借りれば、サイエンスに絶対的真理などはなく、あるのは過程(プロセス)、常に発展的に展開される「半真理」なのですね(「ホワイトヘッドとの対話」ルシアン・プライス編、みすず書房)。その証左に、「確率の雲」に覆われた私たちの素粒子の向こう(クォーク)には、なにやら「ヒモ状」のものが朧に見え始めてはいるようですから…。
果たして、こんな説明でおわかりいただけたでしょうか。アインシュタインはとても納得できず、その量子力学陣営を代表するボーアとの論争の果ての捨て台詞こそが、先の「神は骰子を振らない」でした。
閑話休題。ともあれ、無地無色の瀟洒なペーパー・プレーンは、その主翼と垂直尾翼に英字のブランド・ロゴがさりげなくプリントされ、それもまたよし、私は私の手になる小振りな紙細工を頭上に掲げ、色々と角度を変えては眺め眇めつ、飛魚のような「すばしっこいカタチ」をしばし愉しみました。その後の部屋でのテスト飛行も上々で、何より当の紙ヒコーキが部屋の空気を切り裂く、そのライン・ドライヴの軌跡の美しさには、そうそう、これだよね、「燕? 燕!」の思いを強く抱いたことでした。今様を衒っていえば胸がキュン、とでもするところですか。
戸外で試みることは、未だに控えています。どこか面映く、それはもちろん第三者に対してですが、自分にもどこか気恥ずかしい気がするのでした。だから、今のところは部屋での飛行だけでお茶を濁していますが、思いの丈が高まれば、いずれそんな屈託も雲散霧消するはず、その日その時までのお楽しみとしておきます。
☆☆☆
以上の稿を認めた後、乱雑に積んである図書の中から、偶々そこにあったベルトルト・ブレヒトの「ガリレイの生涯」(岩淵達治訳・岩波文庫)を手にし、興に任せて一気に読み果(おおせ)たのですが、そこには、ガリレオもまた自分の科学体系の構築においては審美的にアプローチしていた旨の台詞があり、おやおやと心動かされました。以下に、ちょくちょく起こる「読書の共時性(意味のある偶然)」に驚きながら、その台詞を、その訳注ともども以下に掲げます。
ガリレオ
「かつて工匠が私を使って
神プリアプスの像を造ろうか床几を作ろうかと
決めかね、結局神の像を造る決心をしたとき、
私はあまり役に立たぬ、イチジク剤の切れ端だった……」
君はホラティウスが、たとえばこの床几という言葉をやめて、机という言葉におきかえてもいいといったと思うかい? なあ、君、僕の美的感覚は、僕の世界像のなかで、金星が満ち欠けをしないと損なわれてしまうのだよ! 僕らは眼の前の最大のメカニズムである天体を研究してはいけないといわれたら、川から水を揚げる機械をつくるメカニズムを考え出すことはできないよ。三角形の角の総和は、教皇庁の要求があったからといって変更はできない。飛行物体の軌道を、私は箒の柄にまたがる魔女の飛行を説明するようには計算できない。…
さて、その訳注に曰く、「詩人が自作の詩のなかのことばを簡単に他のことばで置き換えられないのは、美的感覚の問題である。ガリレオがこの美的感覚を理解できるのは、彼がしばしば自分の科学体系の構築に当って、このような美的感覚に似たものも使っていることを示す」とありました。つまり、ブレヒトはガリレオの科学的な美的感覚を詩人の美的感覚と対比して激白させているわけです(これもブレヒト特有の「異化効果」を狙ったものでしょうか)。だから、別な箇所の訳注には、ブレヒトの言として「…それどころか今日では、自然科学の美学さえ書けそうだ。ガリレイはすでにある種の方程式の優雅さ、とか実験の機知などということを言ってるし、アインシュタインは、美的感覚がある種の発見に働くという」が挙げられています。宜なるかなです。
(☆☆☆から 2020/5/11追加)
付記
私の購入したペーパー・プレーンを以下に挙げておきます。
・ペーパータイプ競技用機「ホワイトウイングス(設計・二宮康明)」(株)A・G・
・空気力学的な考慮から、各パートを薄い紙片で貼り合わせる、という発想には驚かされました。機軸は翼よりは丈夫であって欲しいから、強度を保つためにはある程度の厚みが必要です。だからといって機軸全体を厚くしないで(軽量化)、厚みにグラデーションを付けるという配慮――頭部はより厚く、中央はやや厚めにし、後方に向かって薄くなっていく、その繊細に計算された工夫は秀逸です。
(2020/5/1)
****** 次回へ ******
HOME
前回へ
|

大空にいどむ
(岩波少年文庫)

紙ヒコーキ世界王者に密着
|