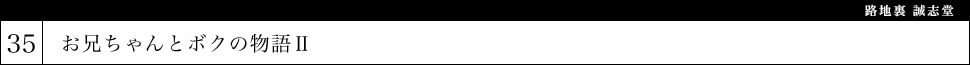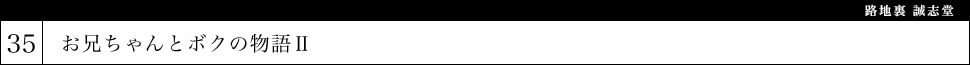私は私の路傍の石について語らなければなりません。
〔路傍の宝石〕
まずは、当時の村の道路事情を語っておきます。
私たちがケンドーと呼ぶ村のバス通りは、当たり前なことに舗装などされてはいません。その頃のこの国の道路事情のご多分に洩れず、砂利道です。しかも、その道幅は狭く、乗合いバス同士の鉢合わせがあれば、場合によっては女性の車掌さんが路上に降り立ち、オーライ、オーライのひとつも演じられました。つまりはそのようにしてしか擦れ違えないほどの道幅なのです。としても、私たちにとっては、その砂利道はそれはそれで随分と立派なものと認識されていました。だって、あとは車の往来とて稀な細身の脇道や横道、村人たちが呼んだ行政用語を持ち出せばソンドーにすぎなく、他には青き踏む野良道、ノードーがあるばかりなのでしたから。
再び、県道の方に話を戻せば道の所々にはやや幅広になっている場所があって、その道路端には道路修復用の砂利の小山がありました。そして、その小山は私たちが無聊を託つ時の遊び場のひとつにもなっていて、そこで、必要な時にはいつでも礫となる小石を好きなだけ調達できました。いつなん時、私たちにそのようなものの必要になる事態が出来しないとも限りません。また、中でも平たい小石は水切り用のものとして貴重なものなのでしたから、私たちにあっては常に怠りなくポケットに確保されているべきだし、大振りの平たいそれなら石蹴り用の石として、近所の女の子たちにプレゼントされてもよいでしょう。
ことほど左様に、いわばそこは私たちの宝の山でもあったのです。そして、その砂利の山が私にとって文字通りの宝の山と化してしまったことがありました。小石の中には穿たれた洞を持つものがあって、ごく稀にですが、その中に米粒ほどの水晶が発見されます。純粋な結晶体にはほど遠い石英の粒にすぎなかったかとも思われますが、いやいや、あれは確かに水晶でした。
その頃のことです、私はそんな珍かなものを近所の洟垂れ小僧から示され、それこそ嫌というほど見せ嬲られたことがあったのです。あんな道路端の砂利の山にそんなものが潜んでいようとは! 口にこそ出しませんでしたが、私はどんなにか羨ましく思ったことでしょう、羨望で目が眩むほどに所有したいと思いました。俄然、私は同様なものを、今や私の目には光り輝くばかりの砂利の小山に求めました。そんなものをひとつでも見つけることができれば、名実ともにその小石は私の「宝もの」となるのでしたから。
とはいえ、私の宝の山の探索は余りに不毛を極めたのです。幾たびも砂利に脚を取られ、転んでは剥き出しの膝小僧に擦り傷を作り、まるで悪夢の中でのように、下手に踠けばもがくほど崩れる砂利の堆積にはほとほと手を焼き、時には犬の糞まで掴まされ、私なりに辛酸を嘗め尽くしていたのです。
しかし、私は諦めません。
近在の砂利の山を目の届く限りは調べ尽くしていましたが、私には切り札がありました。そう、お兄ちゃんのお出ましを願ったのです。ひとりではとても行く気にもなれない村はずれの方まで、私はお兄ちゃんを引き連れて遠征することにしました。それは「神話的ともいうべきひとつの成功」(R・カイヨワ)を求めた、私の最後のチャンスといってもよかったのです。
「石が書く」(叢書・創造の小道、新潮社)の名著を持つわれらがカイヨワは、子どもたちの「宝もの」、すなわち「金銭などに決して還元できない豪奢な架空の富」について、すこぶる示唆に富むことを陳べています(以下、野村二郎・中原好文訳「本能―その社会学的考察」所収、「秘密の宝もの」からその訳文を適宜に改変して綴ります)――「宝もの」とは無価値であって何よりも高価なもの、取りに足りぬものであって限りなく高貴なもの。別言すれば子供の想像力、各自の「物語」によって聖別され、子供たちの「外的な魂」とさえ言い得るもので、宝ものという観念ほど経済の観念から、つまり有償性からほど遠いものはなく、むしろその否定ですらあるように思われます、と。事の正鵠を射たなんともスリリングな定義でしょう。更に続けて、それは「魔法の次元に属する」ものなのだと明言します。
しかし、そのようなものが、果たして、そう易々と探し出せるものでしょうか。「困難と危険と幸運」、これこそが当のものに最も確かな魅力を保証するのだし、また、そうでなくてどうして「宝もの」などと揚言できるでしょうか。そんなことは重々、当時の私にさえわかっていたことなのです。だって「努力と犠牲と神慮」を俟って初めて宝ものは真の宝ものとなるのですから!
その日の、季節は問わないことにしましょう、果して「その時」はあったのでしょうか。そのことを語ろうと思います――「時が満ちるとき、一切の時間的事物がその人の内で死する時! そこに『恩寵』が生れるのである」(田島照久編訳「エックハルト説教集」より)。
〔「恩寵」はあったか〕
私とお兄ちゃんは村はずれの、その界隈の目ぼしい砂利の山のことごとくを探索し尽くしていました。
しかし、私たちにどんな成果もありません。残すはあとひと山でした。私の顔は一丁前に汗と埃でダンダラ模様になってもいたでしょう。お兄ちゃんは時にそんな私を横目に窺い、俯いてはクスクスと笑ったりもしました。一所懸命であることがそんなに可笑しいものでしょうか。私は両の拳を腰にあてがい、肘を張り、頬をこれ見よがしに膨らませ、無言の抗議で応えます。すると、お兄ちゃんの笑みはとうとう堪えきれずに爆発するのでした、失礼な。親しき仲にも礼儀あり、私は一層気難しい表情を作って応対するのでしたが、反って火に油を注ぐ結果となり、終にはお兄ちゃんの屈託のない笑いに負けて自らも噴き出す始末。
私たちは最後の山に移動しました。しかし、そこでも一向に、水晶を内蔵した小石など見つかる気配もありません。お兄ちゃんは相変わらず黙々と捜し続けてくれていましたが、当のご本人である私の方はひとつも成果が上らないので、わがことながら、もう、飽き飽きしていました。
陽は傾き、わが常陸国の風土記の形容を借りれば、ギラギラと「陽の煎(い)る夕べ」が私たちの下にも落ちて来ました。砂利の埃もいっぱい吸いました。私の咽喉(のど)は渇き、実際へとへとでした。私のイノチガケ、「懸命」もこと切れました。もはや、これまで! 目指すものを探しあぐねた挙句、私はイジャケ(意地が焼け)、自暴自棄になりました。お兄ちゃんのご足労への済まない気持ちも多少は手伝ったのかもしれません、最後の山の最後の最後の時、もう、いい、この事態に踏ん切りをつけるべく、私は足元の手頃な小石をいい加減に掴んだものです。そして、そこには幾分、巫山戯た気分を篭めていたとは思いますが、後先も考えずに叫んだのでした。
あった!
お兄ちゃんはハッとしたような顔で、私を振り返りました。
どのタイミングで、どのような口調で「ウッソォ」と言おうか、私は思案し、一瞬のうちに腹を括り、何気なく手にした小石に目を落としました。すると、あろうことか、そのものの中にキラリと小さく光るものがあったのです。私は息を呑みました、果して水晶でした。
私はこの事態に度肝を抜かれ、力なく破顔しました。そして、お兄ちゃんに掌の小石を示し、みるみる涙ぐみ、言葉もありません。お兄ちゃんはそんな情けない私の顔を訝しげに、いつまでもいつまでも凝視めていました。
私は今でもそのことを不思議に思います。そんなことってあるものなのでしょうか。あるとするなら、でも、あったのです、私の時が満ち、あれこそが恩寵? とするなら、私に、私の人生の初期に恩寵はあったのです。と思う一方、土壇場に追い詰められると、いつもいつも夢のような僥倖を当てにする、私の脇の甘い性格はひとえにこの出来事、この記憶に起因するのではないかなどと考えたりもするのです。
以来、私の人生にこのくらい見事な幸運の到来は、絶えてありません。
(2020/6/1)


ブログ「激辛唐辛子男日記 あらため チビ水晶」より
石の挟まった小さな水晶の画像がいろいろ載っています →
****** 次回へ ******
HOME
前回へ
|