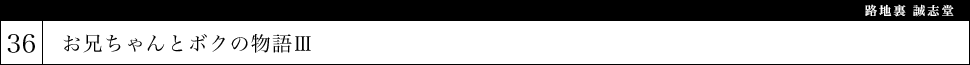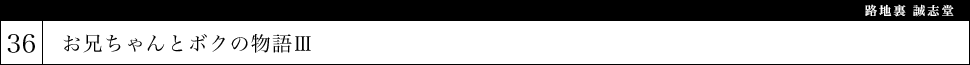写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
〔蜜蜂のささやき〕
お兄ちゃんのところで、私は色んな宝ものを知りました。そのことは語りました。でも、まだ語り足りない気がします。
たとえば、乾電池に接続して遊んだお母さんの乳首ほどの豆電球。この豆電球を私かに口に含まなかった子供などいなかったのではないでしょうか。私なんか、まさか人前でしゃぶりこそはしないものの、ふと気付くとそのものがなぜか口元にあって、時に半ば咥えていて、おい、おい、お兄ちゃんの失笑を買ったりもしました。それが専用のソケットに嵌まった恰好といったら、まるで萼を着用した団栗です。ところで、私たちはこの光る団栗でいわば配線の妙を愉しむのでした。あちらが光ればこちらが灯らず、こちらが灯ってあちらも光る、そのようなことです。工作少年のお兄ちゃんは当時、そんな点滅を司るサーモスタットさえ手作りしていたかもしれませんーーあり得ることです。なぜって、数年後には掌サイズのラジオ(鉱石ラジオ!)さえ作ってしまったのですから。
そのような私たちの工作の延長線上には小型モーターがありました。電源に接続されたモーターは微かに唸り声を挙げる小動物を思わせましたが、その回転音だけを形容すると、庭の花壇で漏れ聞く「蜜蜂のささやき」、あの幽き羽音とでもするべきでしょうか。思わず手に取って、そんな金属の小物体のささやきに耳を傾けた憶えがあります。掌に乗せたそのものはズシリと身の結まった重さがあって、私はそのもの自体に啻ならぬ存在感を覚えたりもしました。多分に、こんな思い出は私だけのものでもないでしょう。
思うに、我が少年時代の最も畏れ多いこのオブジェの周辺には秘密めいて、いつもある固有名詞が取り沙汰されていた記憶があります。お兄ちゃんの口の端に上ったメーカーの名は私たちの神々の名前のようにも聞こえるのでしたが、果してあれはなんというブランド、「聖なる名」ではあったでしょうか。お兄ちゃんに言わせれば、その名の下に、私たちの工作シーンは一変したのだそうです。当時、そう言われた意味がよく汲み取れませんでしたが、今ならわかります。その登場は当時の工作少年の感性、その在りようさえ変えたかもしれないのです。ここにはゴムやゼンマイなどとは質の違った「動力」が顕現していたのでしたからーー私たちの工作の将来が、そう、新しい地平が拓かれたといってもよかったのです。それは大袈裟を大いに承知して申し上げれば、ワットの蒸気機関の発明が、英国は18世紀から19世紀に掛けての産業革命を用意した、そんな歴史的事実に比すべき事態ではあったのです。
同時代の同様な思い出をもって生きた方々なら、私のこのような大仰なもの言いもきっとご理解されると思います。その証拠に、つい輓近のこと、同世代の友人の口からある思いを篭めてその名の語られたことがあって、私はなんとも名状し難い感覚に囚われたことがありました。
マ・ブ・チ!
そうそう、そうだった、マブチ・モーター。
言葉へのこのような曰く言い難い記憶もまた、一種の物質の記憶、「物の思い出」といえば言えはしないでしょうか。単なる名辞としてではなく、物そのものとしての言葉――言葉にだって「物性」はあります!
(参照)
・マブチモーター「RE-140RA―モーターセット―」マブチモーター(株)。
付記
「もしもウォットがこれ以上のことをしなかったとしても、彼は、英国の発明家たちの最前列にその地位を占めることが出来たであろう。しかし彼は、いかに偉大な発明であるとはいえ、単なる蒸気ポンプの改良に満足していることはできなかった。彼は永いあいだ、往復運動を回転運動に換え、それで機械を動かそうと余念がなかった。(中略)一七八四年には平行運動が誕生し、一九八八年には遠心調速機(governor)なる見事な発明が生まれた。この調速機によって、比較的精巧で複雑な工業的作業のための原動力には欠くことのできないかの運動の規則性と平滑性とを増大することが出来た。
回転式機関の登場は重大な出来事であった。(中略)それは数百万の男女の生活条件をすっかり変革してしまった。(中略)この新しい機関の最初のものが設備されて以後、英国に技術的革命が起こっているということがはっきりしてきた。(中略)この新式の動力と、いま一つ、以前は手や筋肉でなされていた仕事をこの動力が営む際に媒介となる伝道機構とが、産業が近代へ飛躍する際の旋回軸となったのである」――「産業革命」T・S・アシュトン著、中川恵一郎訳(岩波文庫)より。
〔乾電池の話〕
少年時の「物質の記憶」の中でも忘れ難いもののひとつに、乾電池の中から取り出した炭素棒があります。その記憶を遡れば、当時の乾電池の表装は厚手のボール紙ではなかったでしょうか。なぜなら、私は乾電池を水にうる浸(か)しては、その灰褐色の詰め物の中から漆黒の芯棒を手に入れたような気もしますから。
では、取り出した炭素棒を私たちはどうしたでしょう、どうするもこうするもないのでした、そのような物を生(き)のままに手にすることがひとつの冒険ではあったのです。生粋なる物、それが取りも直さず私の意味する「物性」です。物性とは「物それ自体が持つ固有の属性」のこと。とするなら、物それ自体がその属性を倹約し、その成分が益々純一化すること、かくなる事態は物質の高貴化と言えないでしょうか。そうであればこそ、私たちはその物にとことん魅了され、当のその物を熱烈に手にもしたいと思うのですし、また、そのような努力をこそ、敬虔なる冒険と言えたのでした。そして、その成果が私たちの外なる「高貴な魂」のひとつになるのです。聖なる書に曰く「あなたの宝のあるところに、あなたの心もある」(マタイ六・21)、そういうことです。
果して、このような機微がかつて少女であられたご婦人方にはおわかり頂けるものでしうか。と問うのも、折角手にしたそのようなものを、当時の少女たちにいくら見せ嬲ったところで、いっかなこちらの期待する反応が得られないばかりか、終には手酷くうるさがられ、挙句の果てには鼻でせせら笑われた記憶を私は持つからです。私の姉などはうるさく付き纏う私の手からそのものを奪うや、顔に薄い笑いを浮かべてポイと道端のドブに捨て去りもしたのです。なんという所業、なんという仕打ち、私はこの一連のことの成りゆきに呆然自失、声もなかったことを憶えています。
さて、私は当時、同年代の男の子から、乾電池の〈+〉の極と〈-〉の極を指で挟んで持ってはいけない、などと脅かすように注意をされたことがあります。なんでも、そのようにすると、電池内に蟠踞する電気が待ってましたとばかりに奔流し、ともすれば指に孔が開けてしまうとのことでした。まさかとは思いましたが、当分の間、私は気味が悪くてそのようにすることを憚った記憶があります。確かに、リード線を直に両極に接続することは、電池をショートさせることであって、もちろん危険なことです。熱を帯び、やがては当体が破裂する事例もあるとします。だから、彼自身は信じきっている風ではありましたが、その言わんとすることはそのようなことへの警告だったと解釈することができます。そのことは同時に、まだまだ乾電池が相対的に高価で、私たちにあっては珍貴なものであったことを物語っています。多少の無知や迷信は過度期のユーモアとして受け取るべきかと思います。
やがては乾電池とミニ・モーターを搭載した模型ヒコー機が空を飛び、モーター・ボートが水上を疾駆する時代が来るかもしれませんが、当時、私たちが汎用する動力はゴムやゼンマイが主流であって、乾電池は時期尚早、その端境期にあったのです。そして、私が勤しんだのはもっぱらその「使用済み」を蒐める方でした。そのことを語ります。
使用済乾電池は、お兄ちゃんのところから稀に貰い受けたりはしていたのですが、それよりも何より、近在の自転車屋さんが私の大のお得意さんでした。時に、なぜか大量の空の電池が放出されました。だから、使用済みは取り立てての苦労もなく、私は小振りな木製の蜜柑箱が一杯になるほど蒐めたものです。蒐めたものはそれはそれで悦ばしいことでしたが、時には畳の上に並べては縦にしたり横にしたり、傍から見れば不可解としか思えなかったでしょうが、私のつもりでは自分を真ん中にして、〇、◇、△、☆、幾何学的図形を描いていたわけで、それはそれで結構楽しいことではあったのです。そんなさ中に家を訪う近所の大人の者があれば誰彼かまわず、とはいえなぜか女性とお年寄りに限ったけれど、私は残りの蒐集品をも開陳しては、おやおや、よくもまあ、こんなに蒐めたこと! と呆れさせ、それがお得意でもありました。私としては褒められた気でいたのです。
〔囲炉裏端〕
ところで、私には蒐めた乾電池を巡る切ない思い出があります。それはまだ寒さの残る早い春の頃のことでした。
その頃の、わが家の居間には簡易な囲炉裏が切られていました。寒の始まる晩い秋から冬、そして寒の残る春にかけて、そこには朝早くから熾った炭が日柄一日中埋けられます(炬燵櫓を設置すれば、忽ちそこは炬燵になります)。夏場になれば、囲炉裏は木の蓋で塞がれてしまいます。子供の私はその佇まいに季節の移り変わりを感じていたと思います。
囲炉裏端は言うまでもなく家族団欒の場になります。時には近所の懇意にしているお年寄りが来て、宵のひと時、家人との四方山話に花が咲いたりします。中でも隣りの爺ちゃんがよく来てお茶をしました。私は隣りの爺ちゃんにとりわけ懐いていて、爺ちゃんが来ると抱っこされます。胡坐の中にすっぽり入ってしまうのでした。そんな折、爺ちゃんが私のおでこを掌で愛撫してくれたことが忘れられません。ある一定のリズムで撫でてくれるのです。そのリズムがとても気持ちがよく、どうかやめないで欲しいと思った記憶があります。いつしか私は爺ちゃんのふところで寝入ってしまうのですが、爺ちゃんは幼児の気持ちがわかるらしく、ずっとそうしてくれました。
話を戻します。
囲炉裏端で、私は朝っぱらからお店を開いています、乾電池で積み木の真似事をして、朝の無聊を託っていたのです。職人であった父が仏壇の上の神棚に朝の水をあげた折、私の乾電池にけつまずき、そのひとつが炭の熾っていた囲炉裏に転がり落ちました。一瞬の間があって、乾電池が破裂しました。なにかが火中の栗のように弾けたのです(乾電池そのものは爆発しないと思いますが、とするなら、では、あれはなんだったのでしょう、プシューと勢いよく灰神楽が立ったのは事実ですから)。
後年、就学した私は学芸会の演目で「猿蟹合戦」の栗の役目を仰せつかったことがありますが、その栗の唯一の見せ場が囲炉裏に身を潜め、タイミングを見はらかって破裂し、ヒールの猿を驚かせる――実際のほどは口三味線でバーン! 擬人化された栗の絵を額に付けて跳ね出すだけのことでしたが、後々、乾電池の椿事を思い出すたびにそのシーンがかぶったものです。
父は猿蟹合戦の猿のように驚いたのですね。癇癪を起し、その場の乾電池を悉く庭先に投げ棄てました。一瞬とはいえ、大工の棟梁に自恃の念を持つ父は子の前でうろたえたこと、そのことに忸怩たるものがあったのかもしれません。拳骨の難は身を躱して、からくも逃れ、私は居間の隅に避難しましたが、父のその振る舞いには二の句が継げず、言葉もありませんでした。今もなお、鬼の形相の父の姿がスローモーションのように蘇ります。
ほとぼりが冷めた頃、私は父に放棄された庭のあちこちの乾電池を一つずつ拾い集めました。その時の心情を思い出す時、私に父への怒りや怨みもなく、どうにも遣る瀬ない悲しみのようなものだけがありました。本当です。そうとするなら、私は一つひとつの乾電池に託けて何を拾っていたのでしょう。それはどこか諦めに似た「寄る辺なき寂寥感」のようなものであったでしょうか。あゝ、そうであるなら、明恵上人様ではありませんが、私の場合は既に五才にして老いたのです! 勿論、冗談ですーー「十三歳の時、心に思はく、今は早(はや)十三に成りぬ。既に年老いたり。死なん事近づきぬらん。老少不定(ふぢやう)の習ひに、今まで生きたるこそ不思議なれ。…」久保田淳・山口明穂校注「明恵上人集(梅尾明恵上人伝記)」(岩波文庫)。
(2020/6/10 )
****** 次回へ ******
HOME
前回へ |
|