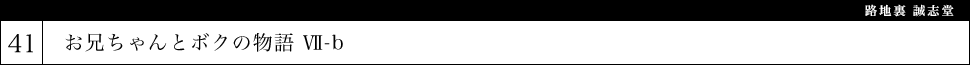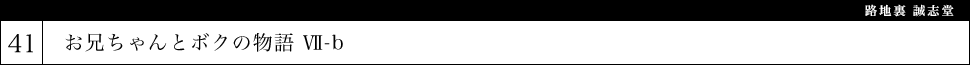写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
今回も、「模型ヒコー機の素材」の話を続けます。
〔ネオフィリア〕
抽き出しの把手のような主翼台。前後の脚で主軸に乗るのですが、その姿は跪座姿勢(クラウチング・スタイル)を取ったランナーです。あるいは野を疾走る野兎ですか、やや前傾、つんのめるように設計されています。
私たちの工作は、この主翼台を機軸にしっかり取り着けることから本格的に始まるでしょう(それとも翼作りからだったでしょうか)。
主翼は、主翼台の前後に装着したアルミニューム管を通して接続されます。では、垂直尾翼と機軸の関係はどうなっているのでしょうか。ここは自転車のスポークを車輪のリムに垂直に接続するネジ、あのニップルのことを思い出して欲しいところです(私はその驚きを「村の自転車屋さん」の項で書きました)。だから、この指摘は中々に深遠で、しかし、こちらの方の答えは簡明です。機軸に穴を開け、垂直尾翼の竹ヒゴを差し込む。なんだつまらない、そうかもしれません。
垂直尾翼そのものに関していえば、さして遠からぬ後年、垂直尾翼が下向き、つまり、機軸の下位置に装着された機種(モデル)を目にした時にはさすがの私も魂消ました、息を呑みました。どんな飛行力学からそのような事態になるのか、まずはそのアイデアの奇抜さに驚いたのですが、その姿はどこかハイカラ、どことなく乙りきな気がしたものです。その感じは都会的、あるいは未来的と言い換えてもよかったでしょう。
では、その意図とは? 多分にあれは、垂直尾翼に機の後輪の役目を兼備させる為の工夫と受け取れました。つまり、模型ヒコー機が接地する際、下方の垂直尾翼が機を後部で高々と支え、水平尾翼を地面との接触の衝撃から護るというのが当時の私の推測でしたが、その実際はどうだったでしょう。
あるいはやはり、あくまで飛行バランスを考慮した上でのことなのでしょうか。素人目にも、下向きの垂直尾翼の方が垂直尾翼としては理に叶っているようにも思われます。なぜなら、主翼との関係に於いて、下方のそれは位相を異にするだけに、進行方向に対し空気の流れを縦に切り裂き、果して機の安定を図るという垂直尾翼本来の仕事を、一層 、有効ならしめると、そんな風にも考え得るからです。
それでは、ここで尾翼そのものの存在理由のおさらいです。尾翼には水平と垂直があり、一般の飛行機においては垂直尾翼には方向舵、水平尾翼には昇降舵が装備されています。方向舵は進路変更の役目を担いますが、では昇降舵はなんのためにあるのでしょう。ズバリといえば、それは機の安定のために案出されたものです。
谷一郎の名著「飛行の原理」(岩波新書)によれば次のように説明されますーー「…釣り合いの不安定を除くには、主として揚力を発生する主翼の後に、尾翼として小さい翼面を備える必要がある。これはいわゆる水平尾翼であって、その位置が重心の後にあるために、もし機首が上がれば、尾翼仰角が増加し、それに働く揚力も増加して、その結果重心のまわりに、機首を下げようとするモーメントを生ずる。このモーメントは、仰角の変化を元に戻そうとする安定作用を与えるものであって、もしもこれが主翼の持つ不安定な作用を補って余るならば、飛行機は全体として、仰角の変化に対して安定になる」、なるほど。
なお、可動式の昇降舵についてはご説明するほどのこともないでしょう。上げれば揚力が減少し、下げれば揚力が上がる、それまでのことです。しかし、この昇降舵も使いようによっては機の安定に一役買いますが、その詳しいところは煩雑を避け、ここでは省きます。
では、機の安定とはそもそもどういうことか、と問えば、要は翼の仰角と速度にもとずく「揚力」と機体の「重心」のバランスのことを意味します。飛行条件により、重心の位置は一定ではなく、微妙に変化します。ですから、創成期、水平尾翼のない飛行機の場合には操縦者がその位置を前後させ、機の重心を微妙に変えてはバランスを取りました。え、そんな、と驚くなかれ、このようなバランスの取り方は私たちも経験済みのことです。自転車を操行してる時、私たちは皆そういうことをしています。自転車では無意識的レベルまで高まっていますが、飛行機の場合は極めて意識的になされるまでのことです。
ちなみに、ライト兄弟の「フライヤー」にも水平尾翼がありませんでした。あえて放棄したと谷一郎は言いますーー「無人の飛行機の模型飛行機の経験から、安定性の必要が固定観念となっていた当時に、兄弟がことさら不安定な飛行機を作り、それを操縦の熟練で制御しようとしたことは、一つのすぐれた見識と言えるであろう」。なにしろ、ライト兄弟は飛行の成功までになんとグライダーによる実験で「一か月の間に千回に近い滑空を繰り返して」いました。初飛行を前に、二人はすでにして飛行の熟練者だったのですね。
話を「下向きの垂直尾翼」に戻します。
思えば、私はお兄ちゃんの潜水艦で下向きの垂直尾翼は知ってはいましたが、ここでヨットのキール(竜骨)を持ち出してもよいでしょう。他日、その種の図書を覗いた時、セイル(帆)が水面上の翼だとすれば、キールは水面下のもうひとつの翼だとあって、私などは船体のバランスを取るためだとしか理解していなかったキールでしたが、実はその位置や形状次第では船の推進力に多大の影響力を持ち、更には推進力さえ生むとあったのには驚きましたーー「ヨットのテクノロジー(冒険と風のかたち)」(INAX BOOKLET)参照。
それなら、話を一歩進めて、空中の竜骨、模型ヒコー機の垂直尾翼にだって同様なことが言えないでしょうか。まあ、そのような忖度は愉しいことではあれ、所詮、素人考え、これ以上の詮索は控えます。が、ここでひとつだけ確認しておけば、男の子なら誰もが試みただろう折り紙ヒコーキの胴体部分、そこを抓んで私たちは飛ばすわけですが、何を隠そう、あの部分こそは構造的にキールであり、機軸に沿って延長された「下向きの垂直尾翼」そのものといえたのです。
ともあれ、飛行機の垂直尾翼が何も機軸の上方に位置していなくとも一向にかまわないじゃないか。しかも、模型ヒコー機だからこそ易々と可能な文字通りの新機軸に、私は大層感心したのでした。奇貨置くべし、理屈はどうとあれ、私はそのような新奇な姿を無条件に喜ぶ方です。
概して、子供はいつの時代にもネオフィリア、新しがり屋なのだし、私たちは常に羽目を外したいと願っているのです。工作少年だって人後に落ちません。いつだって逸脱を夢見ています。だから、そこでは因襲こそが敵なのです、少なくとも私にあっては!
さらに贅言を吐けば、この性癖は長ずるに従い、私の宿痾と化すでしょう。こう言ってよければ、爾来、それが私の信じるに足る唯一の「イデオロギー、正義の体系」(司馬遼太郎)と申してもよいのでした。だったら、私は逸脱に継ぐ逸脱をこそ、この拙稿に夢見てもよいというわけです。
プロメテウスは私の神。思えば小学生以来、私が科学者や数学者やエンジニアの生涯に敬意を抱き、彼らの一途な処世を知るにつけ今なお、身の引き締まるような思いを抱くのも、そのような私の嗜好、とどのつまりは癒しがたいインファンテリズムのなせる業ではあったでしょうか。なぜって、彼らの頭脳と人生は常に既成概念との闘い、奔放な「思考の冒険」と果敢な「実験の精神」に満ちているものはないのですし、そして、実はそれこそが子供本来の資質であるからです。
ところで、私たちの頃の模型ヒコー機はその機軸の最後尾をどうしていたでしょうか。正直なところ、この点に関し私の記憶は定かではありません。気休め程度の、クリップほどの金具を後輪として取り付けたのでしょうか。それとも、垂直尾翼の後ろのヒゴを機軸の下方にまで覗かせ、その後輪のつもりとでもしていた? まあ、そのようなところが相場だったでしょうか。
付記
「ネオフィリア」については、「生命潮流」(工作舎刊)で生態学に新しい地平を拓いたライアル・ワトソンに、その題名もずばり「ネオフィリアー新しいもの好き」(筑摩書房)なる図書があります。新しがりやが生き延びるという視点から進化の妙を考察した図書ですが、ご興味のある方はどうぞ覗いてみて下さい。
ちなみに、私のワトソン体験といえば「生命潮流」の中に紹介されている「100匹の猿」という事象に感銘したことに始まります。後々、立花隆の「サル学の現在」(文芸春秋社刊)でそのエビデンス(科学的根拠)は怪しいと知ることになりますが(ワトソン自身があれはガセだったとどこぞで申しているそうです。とすれば確信犯だったわけですね、いやはや)、興味深い話なので一応紹介しときます。
サツマイモの餌付けをされた幸島の二ホン猿の中の一匹が海水で芋を洗って食べ始めます。それを見た他の猿たちも、一匹、また一匹と真似し始めます。砂だらけの芋よりは無論、美味でしょうし、真似はもとより猿の身上です。これだけでも一種の文化革命で、最初に芋を洗った猿などは猿の天才かもしれません。
まあ、それはそれとして、更に興味深いことはその後にありました。芋を洗って食べる島内の猿が百匹を超えると、なんと幸島の猿とはなんの交流もない遠方の二ホン猿の間にもこの「芋を洗って食べる文化」の伝播が見られたというのです。百匹というのはあくまでも恣意的な数字で、その意味するところは、ある臨界値を超えるとそのような文化の伝播が現象するということです。
ねえ、エキサイティングなお話でしょう。
流行(ブーム)の発生のメカニズムの説明に、ワトソンの尻馬に乗って、私はこの「百匹の猿」を用いて得意気に吹聴してあるいたものです。ある地域である流行(例えば歌謡曲、映画、図書、あるいはファッションモード、ライフスタイル、政治思想ですら!)が一定数(臨界値)を超えると、爆発的に全国的な流行を一気にみる、などといったことです。
要は文化の同時多発現象のことですが、それが科学的エピデンスをもって語られたところがミソでした。何も、そのような科学的証拠を持ち出さなくても「文化の同時多発」現象はよく見かけます。歴史を紐解き、世界大に拡張して陳べれば、前5世紀頃、それぞれの文明圏に、人類の師とも呼ぶべき、プラトン、釈迦、孔子が同時期、それぞれに鮮烈なデビュ―を果たします。
まあ、そこまで大風呂敷を広げなくとも、科学的な偉大な発見の、僅差のプライオリティ争いは枚挙の遑もありません。交渉のなかったニュートンとライプニッツの微分・積分の発見も同時期でしたし、わが和算の雄、関考和もそれらしきものに、同時代、やや先んじて、独自に肉薄しています。
なぜか、機は熟するのですね。
わが田に水を引けば、ベルとエジソンの電話の同時的発明などがそのような事例になりますか。でも、電話そのものに関しての優先順位はどうやらベルにありそうです。が、エジソンのそれは双方向性の電話で、機能的にはベルの電話機よりは一歩先んじてはいたようです。つまり、ベルの電話では後年の無線機のように、片方が喋ると、はい、どうぞ、というスタイルでしたが、後発のエジソンのものは同時に喋ることができるものだったのです(このアネクドートは既出のM・ジョゼフソンの「エジソンの伝記」に拠る)。
結局、ワトソンの「百匹の猿」は文学にすぎませんでしたが、つまり、科学的にはガセだとしても、文学的フィクションとすれば、よくできたお話で(さすがワトソン氏、幸島の猿の芋洗いから、よくぞそんな与太話を思いついたものです)、私は今もなお、そこに科学的エビデンスなど不要の(説明原理として科学が唯一万能と思い込むことは迷信の一形式ですよ)、有効な文化社会学的概念だと思っています。
蛇足ですが、数あるワトソン氏の著作の中では、一世を風靡した感のある「生命潮流」はともかく、私のお薦めの一冊は「風の博物誌」(河出書房新社)です。文句なしの名著です。
(2020/8/1 )
****** 次回へ ******
HOME
前回へ
|

「ライトフライヤー号」
探検コム<グライダーとオーニソプター>「ライト兄弟・世界初飛行への道」より
|