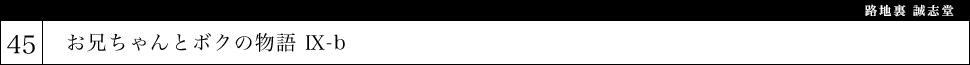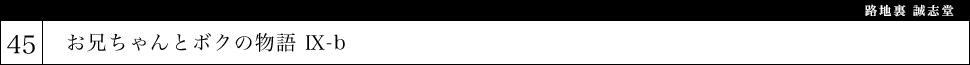写真 佐藤有(たもつ)
1937年生まれ
20歳の頃から身近な自然や子供たちを撮り続ける。
現在、茨城県龍ヶ崎市にて写真館を経営。

 
なつかしの昭和の
子どもたち
国書刊行会
文 田中秋男
1948年生まれ
CMプランナーとして約35年ほど糊口を凌ぐ。
50代半ば心臓に病を得、
職を辞して文筆業に励む。
 
筑波の牛蒡 敬文舎
|
〔竜の町〕
私たちに最も親(ちか)しい町はその名の頭に「竜」の一文字を戴く小さな城下町、村の西、昔気質の数え方をすれば三里ほど遠方に位置していました。私たちはその頭文字をリュウと上手に発音出来なく、リーと発声したりします。その「竜の町」には旧くからの高等学校があって、やがてお兄ちゃんはその市名に因む竜を象った徽章を身に帯びるはずです。しかし、それはまだ先々のこと。
幼い頃、私は母につれられよくこの町に行きました。思えば、私はこの町で中華蕎麦なるものを初めて食べたのでした。その印象はとても鮮やかでーー外側に稚拙な竜が描かれた朱色の瀬戸の丼ももの珍しく、内側は唐草模様に縁どられていました、そんな丼の中には赤味かかった薄い褐色の汁、その上に鳴門の桃色の渦巻を中心に、漆黒の海苔の矩形と麦藁色の支那竹と草色の鳳蓮草が配置されています。そして、その下には艶めいた縮れ加減の細引きの麺がこちらの気を引くように蟠っているという按配です。
子供の私はそれらの彩りを見るたびにどんなに麗しく目を惹かれたことでしょう。でも、いざ口にしてもみれば、中華蕎麦は大して美味しいとも思われませんでした。が、それは町の味でもありました。家人と連れ立ってお店で食事をする、それがそもそも町の体験なのですから、それはそれで充分、私を驚かせ、満足させるものでした。
ともあれ、幼児期の私の「竜の町」での思い出は中華蕎麦や、日本蕎麦屋で食べる恒例だった卵とじ蕎麦などのご馳走の上にありました。だから、町の観光スポットである観音様のお祭りに出掛けたことなどが何も一番の思い出となるわけではありません。ですが、観音様で見かけるこの町のシンボルである竜の肢は三本指なのだ、それはとても独特なもので云々、そんな大人たちの得意気な講釈もどきは妙に子供心に残っています。
観音様の正面の大きなテラコッタには、角の生えた馬面の太く長いものが描かれ、その肢はなるほど爪が三本で、なにやら光るものを掴んでいます。しかも、妙に着飾った細面の女の人が太く長いものの背の上に立っています。この女人が様付けで呼ばれる、たぶんカンノンで、その鱗を持った太く長いものが竜らしいのです。このものはどうやら空を飛ぶらしく、そこかしこには雲らしきものが漂っています。後々、これが雲竜なのだと知りますが、当時の私にはあれはお兄ちゃんの所にある少年雑誌の、南海の冒険譚などでちょくちょく見かける類いのアナコンダくらいに思っていました。それにつけても空飛ぶ大蛇とは! しかも肢があるのです、なんともはや。
確かに、「竜の町」には私の村などと違って、この観音様を始めとして由緒有りげな神社仏閣があって、その祭日には数多の露店が並び、近郊の村々から人々が押しかけます。その賑わいもまた町ならではの風情でしたが、さることながら、私にとっての町とは何よりも道路の佇まいでした。
「竜の町」の道路は、砂利道などではなく、当時ですら、すでにアスファルトで舗装されていました。それが町というものです。こんな道なら、雑誌で見かけるアメリカの少年のようにローラースケートを楽しむことも可能でしょう。そのようなローラースケートに代表されるボーイズ・ライフを、私たちは、少なくとも私は心ひそかに憧れたものです。
今ならさしずめ、サーフボードでしょうか。現在、日本の少年たちがサーフボードを楽々と熟し、その楽しむ姿を町場の光景の中に見るにつけ、私は正直、とても羨ましく、ああいいな、この「今の豊かさ」を充分に楽しんで欲しいと、ほれぼれと見蕩れたりします。
私たちは乗合いバスに乗って「竜の町」へと出かけます。母や姉は申すまでもなく、いつも小奇麗にしている町の人に笑われないように(!)、私などもムリヤリに余所行きを着せられ、いそいそと町へ出かけるのでした。そして、そのことは遊び仲間に必ず吹聴され、嬉し恥かし、文句なしに羨ましがられることではあったのでした。いいなあ、いいなあ、確かにそれはどんなに晴れがましく思われたことでしょう。
どんな用事であれ、「竜の町」へ出かけることは私たちにとって晴れの日なのです。家人の誰某かがその町へ行くともなれば、連れていって欲しいとせがんでは、泣き喚く子もいたのです。そして、どうにも事情が許さない場合は、彼は何やらのお土産の約束を家人から取り付け、銅鑼焼きがいい、白餡の、銅鑼焼きだね、あの大きい…、そんなやり取りの末、ようやく納得するのでした。
ワインダーはわざわざそんな「竜の町」へと出向き、しかも工作玩具を専門に取り扱う専門店で手に入れます。そのお店はバラック建てと思しき造りの、小さなお店の羅列の中の一軒でした。お店の羅列! それこそが幼き日の私のもうひとつの「町の定義」でした。そのプリミティブな定義は今尚、私の中に生きています。
そして、その一廓を私たちは「まあけっと」と呼んでいました。
近年、行政改革の流れの中で、私の村が町へと呼称を変えた時、私の脳裏に浮かんだことは、わが村のどこに「町」があるか、との思いでした。一軒一軒のお魚屋さんや雑貨商、食料品店などがあったとしても、どこにも「お店の羅列」は見受けられないのですから、それで町ですかと、私は面映ゆい思いをしたわけです。
と言ったからって、私はそのことついて、殊更めかしく苦言を呈しているわけではありません。以上のようなことは、私の根深い病理の一つであるインファンテイル(子供じみていること)の開陳にすぎません。
〔まあけっと〕
「まあけっと」と呼ばれる板張りの回廊を持つ一郭には、少年時の夢の商品を専らとするお店が立ち並んでいます。
トランジスタ・ラジオが陳列され始めたラジオ店。その店頭にズラリと万年筆を並べた文房具屋さん。軒先の大きな振り子時計が目印の時計屋さんには、お兄さんたち垂涎の的の腕時計が陳列されていて、片や誰もが「いつかは」と憧れに憧れた高嶺の花、写真機のお店があるかと思えば、そのお隣の眼鏡屋さんには天体望遠鏡や顕微鏡がありました。簡易ではあるが光学器械のお店を兼ねてはいたのですね。
ここで、慌てて、当時の私たちの習俗の一端を陳べて置けば、万年筆は中学生になって所持するもの。腕時計は高校生になって初めて許されます。なお、革靴は高校生になってから、中学生は運動靴です。カメラなどは大学生か社会人になって、しかも選ばれた者だけが所持するものでした。
話を戻します。
「まあけっと」を更に歩めば、単行本の漫画(赤胴鈴之助や月光仮面!)をズラリと並べたブック・ストアがあって(もしかしたら貸し本屋だったかもしれません)、やがてはお兄ちゃんがその道に勤しむことになろう軽楽器のお店があって(お兄ちゃんの部屋に一本の木管楽器があったことを今、思い出します。クラリネットと呼ばれるその楽器は結核で早世した叔父さんの形見だと、私は聞いたことがあります)、さあれ、いずれの日にか、その近所にはレコード・ショップが登場し、お兄ちゃんたちの溜まり場のひとつとなるでしょう。としてもそれは大分後々のこと。
靴屋さんには西洋人の男の子の履くような子供の革靴(!)があり、帽子屋さんには人気職業野球チームのロゴ・マークの入ったキャップ。でもね、私はそんなキャップより、その店頭にこれ見よがしに吊るされた、鞣し革の本格的なサン・バイザーが咽から手が出るほど欲しいと思いました。大きくなったらあんなのを被って模型ヒコー機を飛ばしてもみたいと、でもね、そんなことは誰にも言いません。
一方、その並びにはなぜか計量器具だけを取り扱うお店があり、どんな工具だって揃えに揃えた機械専用の工具店があり、ボルトやナット、螺子の類いだけを商うお店だってありました。
当時の私はそんなお店には差し当たってのどんな用事も持ちませんでしたが、なぜか心惹かれているのでした、機会があれば、いつの日にか心ゆくまでこんなお店の品々の一つひとつを吟味して歩きたいものだなどと。でも、この種のお店に一歩踏み込んだ時の、あの独特の強い臭い、あれは何だったでしょう。そう、グリースのような、私にはどこか懐かしい、良い臭いなのでした。
やがて、ブリキ製やセルロイド製の玩具を扱うオモチャ屋が「まあけっと」にはあって、そのお隣に、いずれはプラモデルを専門とするお店に変身する前の、我らが工作玩具専門のお店があるのでした。
そうして、そこに、高速ゴム巻き器、私たちのワインダーが売られていました。
以上、私たちは淡い憧れを持ってその一郭を、外国語などとは認識もせずに「まあけっと」と呼び習わしていたわけですが、こんな呼称に時代の匂いを、つまり、終戦時の進駐軍の名残りが感じ取れやしないでしょうか。
確かに、その界隈は旧い田舎町にあってはどこかバタ臭く、私は今でも「まあけっと」の特徴であった、あの軒下沿いの板張りの回廊をありありと思い出すことができます。それは随分とお粗末ではありましたが、コロニアル風とでもいうのでしょうか、アメリカ映画に見る西部劇の町のようでもありました。
付記
龍のツメの数に注目したい。龍のツメの数には「規定」がある。一般論でいえば、漢代が三本、宋代が四本、元代からは五本である。陶磁器にもよく龍の図柄がある。十三世紀の元以降、五本のツメの龍があれば、それは皇帝の専属の窯の作品である。
――池上正治著「龍の百科」新潮選書より。
(2020/9/20 )
****** 次回へ ******
HOME
前回へ
|
|